導入:なぜ今、専業主婦は「申し訳ない」と感じるのか?
「収入がないことがダメな人みたいな。家事だけやってて、ご飯食べてて申し訳ない」
これは、2年前に自らの意思で専業主婦の道を選んだ、あすかさん(35歳)の悲痛な声です。ネット上では「働かないでラクでいいよね」「生産性がない」といった心ない言葉が飛び交い、”専業主婦論争”がたびたび巻き起こります。しかし、その言葉の裏で、多くの当事者が声にならない息苦しさを感じています。
専業主婦は直接的な稼ぎには繋がらない。収入がないことがダメな人みたいな。家事だけやってて、ご飯食べてて申し訳ない
世間が貼る「ラク」というレッテルと、当事者が抱える「申し訳ない」という罪悪感。この大きなギャップは、一体どこから生まれるのでしょうか。
あなたも、言葉にはできない「見えない何か」に、生きづらさを感じていませんか? この記事では、データと当事者の声を手がかりに、その正体を紐解き、あなたが自分らしい選択を誇れるようになるためのヒントを探る旅に出たいと思います。
第1章:データが示す「専業主婦」の現在地 – “当たり前”から“少数派”へ
かつて、日本の家庭の「標準モデル」とされた専業主婦。しかし、その姿は社会の変化と共に大きく変わりました。まず、客観的なデータから、専業主婦の現在地を確認してみましょう。
労働政策研究・研修機構のデータを見ると、その変化は一目瞭然です。
1980年には1114万世帯と多数派だった専業主婦世帯は、年々減少し、2023年には539万世帯に。一方で、夫婦ともに働く共働き世帯は、1980年の614万世帯から、2023年には1278万世帯へと倍増し、1990年代後半には完全に逆転しました。
(グラフのデータから読み取れる内容)1980年代は専業主婦世帯が共働き世帯を大きく上回っていたが、1997年にその数が逆転。以降、共働き世帯は増加し続け、専業主婦世帯は減少し続けている。
今や、専業主婦世帯は全体の3割を切り、「当たり前」から「少数派」へとその立ち位置を変えたのです。
この背景には、元記事で奈良女子大学の岡田玖美子氏が指摘するように、「女性の高学歴化」や「ジェンダー平等の進展」といったポジティブな変化があります。しかし同時に、「夫の収入だけでは家計が厳しい」という経済的な理由から、女性が働かざるを得ない状況も大きく影響しています。
社会構造の変化の中で、かつての「当たり前」が通用しなくなった。この事実が、「なぜ働いていないの?」という無言のプレッシャーを生み出し、専業主婦が「肩身の狭さ」を感じる大きな要因の一つとなっているのです。
第2章:生きづらさの正体 – 私たちを縛る3つの『呪い』
「肩身が狭い」「申し訳ない」。この漠然とした感情の奥には、現代社会特有の根深い問題が潜んでいます。ここでは、当事者の声をもとに、その生きづらさの正体を3つの「呪い」として言語化してみましょう。
① 収入がない=価値がないとする『生産性の呪い』
「稼ぎに繋がらない。収入がないことがダメな人みたいな…」
この言葉に象徴されるように、現代社会は「金銭的価値=人間の価値」という考え方、いわば『生産性至上主義』に覆われています。年収や役職といった分かりやすい指標で人の価値を測ろうとする風潮が、収入を生まない家事や育児に専念する専業主婦を「生産性がない」と断じ、苦しめるのです。
これは専業主婦だけの問題ではありません。「一家の大黒柱」として稼ぐことを期待される夫もまた、「稼げなくなったら価値がなくなる」というプレッシャーに常に晒されています。この『生産性の呪い』が、夫婦双方を疲弊させているのかもしれません。
② 社会から切り離された感覚に陥る『孤立の呪い』
子どもに持病があり、やむなく専業主婦になったみえさん(37歳)は、「繋がりが欲しいし、社会に認められたい気持ちもずっと持っている」と語ります。専業主婦になると、これまで仕事を通じて得ていた社会との接点が急に失われることがあります。
例えば、美容院で髪のカラーリングしてもらうとき、「この髪色は会社的に大丈夫?」と聞かれる。そのときに「専業主婦だから大丈夫です」って言えばいいが、質問する側は、私が外でお金に繋がる仕事をしている前提で質問を投げかけているので、言いづらい。
あすかさんのこのエピソードは、社会の前提が「働く女性」になっていることを示しています。こうした日常の些細な会話のズレが積み重なり、「自分は社会から取り残されているのではないか」という疎外感、すなわち『孤立の呪い』を生み出します。日中の会話相手が幼い子どもだけ、という日々に孤独を感じる人も少なくありません。
③ キャリアを中断したことへの『もしもの呪い』
「このままで、また社会復帰できるんだろうか?」
「もし、夫の身に何かあったら、この家族を守れるだろうか?」
キャリアを中断した専業主婦の多くが、こうした漠然とした、しかし根深い不安を抱えています。みえさんが「どんな働き方ができるのか。いつからできるのか。そういうことを考えながら、いつも過ごしている」と話すように、未来への不安は常に頭の片隅にあります。
変化の激しい現代において、一度キャリアのレールから外れることへの恐怖。それは「選ばなかったもう一方の道」への後悔と結びつき、「あのまま仕事を続けていたら…」という『もしもの呪い』となって、現在の選択を揺るがすのです。
第3章:その『無償労働』、年収にしたら〇〇万円? – 家事・育児の価値を再定義する
「ご飯を食べてて申し訳ない」という罪悪感。その最大の原因は、自らの労働が「無償」であり、経済的な価値がないと思い込まされていることにあります。
では、もし専業主婦(主夫)の労働を外部サービスに依頼したら、一体いくらかかるのでしょうか?
ある試算によれば、掃除、洗濯、料理、買い物、家計管理、育児、子どもの送迎といった多岐にわたる業務を、それぞれの専門サービスの時給で計算し、年収に換算すると、その額は数百万円に達するとも言われています。
- 料理・後片付け:年間 約180万円
- 掃除・洗濯:年間 約100万円
- 育児・教育:年間 約250万円以上(年齢による)
※上記はあくまで一例の試算です。
こうして可視化してみると、「生産性がない」という批判がいかに的外れであるかが分かります。専業主婦の仕事は、「貨幣に換算されていないだけで、極めて高い経済的価値と、家族の生活基盤を支えるという代替不可能な価値を持つ労働」なのです。
この事実は、他者からの批判を跳ね返すための理論武装になるだけでなく、何より自分自身の自己肯定感を高めるための力強い根拠となります。あなたは決して「何も生み出していない」のではありません。家族という最も大切な社会の単位を、日々支え、育んでいるのです。
第4章:『肩身の狭さ』から抜け出すための具体的な処方箋
生きづらさの正体が見えてきたところで、次に私たちが取るべきアクションを考えていきましょう。現状を嘆くだけでなく、小さな一歩を踏み出すための具体的な処方箋を3つ提案します。
① パートナーとの対話:「申し訳ない」から「ありがとう」の関係へ
最も身近な社会である「家庭」での認識を変えることが第一歩です。罪悪感を一人で抱え込まず、パートナーと対話しましょう。
- 家計の完全共有:家計簿アプリなどを使い、家計を「二人で経営するプロジェクト」として捉え直します。「稼ぐ役」と「管理・運用する役」という対等なパートナーシップを意識しましょう。
- 感謝の言語化:「いつも美味しいご飯をありがとう」「君が家を整えてくれるから、仕事に集中できるよ」。お互いの労働への感謝を、意識して言葉に出し合いましょう。「申し訳ない」が口癖になっていたら、「ありがとう」に置き換える練習を。
- お互いのプレッシャーを共有する:専業主婦の「孤立感」や「不安」を話すとともに、夫側が感じている「稼ぎ続けなければならない」というプレッシャーにも耳を傾けてみましょう。お互いの大変さを理解することで、本当の意味でのチームになれるはずです。
② 小さな社会との接続:「会社」以外の居場所を見つける
「社会=会社」という固定観念から自由になりましょう。あなたにとって心地よい、小さな社会との繋がりを見つけることが大切です。
- 趣味や学びを起点にする:地域のサークル、図書館のイベント、オンラインの読書会、資格取得のための勉強仲間など、興味のある分野で人と繋がってみましょう。
- 短期・在宅ワークから試す:もし働く意欲があるなら、まずは週1〜2日のパートや、スキルを活かせる在宅ワークなど、無理のない範囲から始めてみるのも良い方法です。社会復帰への自信を取り戻すきっかけになります。
- SNSで発信する:育児の工夫、節約術、好きなことについてなど、自分の経験や知識を発信してみるのも一つの手です。同じ境遇の人との繋がりが、大きな支えになることもあります。
③ 自分軸の確立:他人との比較から降り、自分の「納得解」を見つける
SNSで目にする「キラキラしたワーママ」や、親世代の価値観。私たちは常に他人の物差しに晒されています。しかし、幸せの形は人それぞれです。
大切なのは、他人の「正解」ではなく、あなたとあなたの家族にとっての「納得解」を見つけること。あすかさんが仕事と家事の両立に限界を感じ、「リセットの意味」で専業主婦を選んだように、その選択はあなたと家族がより良く生きるための、尊い決断だったはずです。
「誰がどう思うか」ではなく、「自分たちがどうありたいか」。その自分軸をしっかりと持つことが、『肩身の狭さ』から抜け出すための最も強力な武器になります。
結論:すべての人が『自分らしい選択』を誇れる社会へ
専業主婦か、ワーキングマザーか。私たちは、つい二項対立で物事を語りがちです。しかし、問題の本質はそこにはありません。
本当の問題は、個人の選択を尊重せず、「お金を稼ぐこと」に偏った価値を置く『生産性至上主義』の社会そのものにあるのではないでしょうか。
理想は、誰もがライフステージや価値観に応じて、働き方や家庭での役割を柔軟に選び取れる社会。時には仕事に邁進し、時には家庭に専念する。そのどちらの選択も、等しく尊重され、賞賛されるべきです。不毛な対立を乗り越え、多様な生き方を認め合う社会を、私たち一人ひとりが作っていく必要があります。
最後に、あなたに問いかけます。
あなたにとって、そしてあなたの家族にとって、本当に幸せな生き方とは、どのようなものでしょうか?
その答えに、胸を張ってください。あなたの選択は、誰にも否定されるものではありません。


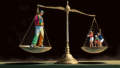
コメント