はじめに:「行ってきます」が、最後の言葉だった。ある交通死亡事故、遺族の9年間の闘い
この記事を書くにあたり、私は一冊の手記を読みました。それは、交通事故で当時15歳だった最愛の息子、大貴さんを亡くされた、中本佐智さんの魂の記録です。読み終えた後、私はしばらく席を立つことができませんでした。そこに綴られていたのは、想像を絶する悲しみと、理不尽な現実に対する静かな怒り、そして、それでも前を向いて「命の重さ」を訴え続けようとする、一人の母親の、気高く、そしてあまりにも壮絶な闘いの軌跡でした。
2014年7月13日、鳥取県智頭町のトンネル内で起きた、あまりにも無慈悲な事故。あの日から、中本さんの時間は止まったままです。「『行ってきます』が、息子と交わした最後の言葉になりました」——その一文に、どれほどの涙と後悔が込められているのか、私には想像もつきません。
これは、遠いどこかの悲劇ではありません。車社会に生きる私たち全員が、いつ加害者にも、被害者にもなりうる、すぐ隣にある現実です。この記事では、この事故を風化させることなく、その背景にある問題を深掘りします。そして、中本さんの声を通じて、ハンドルを握るということの本当の「重さ」を、あなたと一緒に考えていきたいと思います。これは、単なる交通安全の記事ではない。私たちの日常に潜む「凶器」と、どう向き合うべきかを問う、魂のための記事です。
【事件の再検証】なぜ息子は死ななければならなかったのか?時速178kmの暴走という「未必の故意」
まず、感情論の前に、あの日何が起きたのかを冷静な事実で再検証しましょう。
- 日時:2014年7月13日
- 場所:鳥取県智頭町 国道373号 志戸坂トンネル内
- 被害者:中本大貴さん(当時15歳)、自転車で走行中。
- 加害者:当時19歳の少年(無免許・無車検・無保険)
- 事故状況:加害者の運転する車が、法定速度60km/hを118km/hも超える、時速178kmで暴走。トンネル内で大貴さんをはね、その命を奪いました。
- 判決:加害者の少年は、危険運転致死罪ではなく、より刑の軽い「過失運転致死罪」で懲役4~6年の不定期刑となりました。
(出典:各種報道機関の報道、及び遺族支援団体「あいの会」の公開資料)
私がここで強く問いたいのは、時速178kmでのトンネル内走行が、本当に「過失」と呼べるのか、という点です。これは、もはや「うっかり」や「不注意」ではありません。「誰かを殺してしまうかもしれない」と認識しながら、それでも暴走を続けた。これは、限りなく殺意に近い**「未必の故意」**と呼ぶべきではないでしょうか。しかし、日本の司法は、それを「過失」と判断しました。この「法」と「遺族感情」の間の、あまりにも深い溝。これこそが、中本さんを始めとする多くの遺族を、今なお苦しめている問題の核心なのです。

「加害者の未来」と「被害者の命」。なぜ、日本の交通刑罰はこれほどまでに“軽い”のか?
なぜ、これほど悪質な運転が「過失」とされ、比較的軽い刑で済んでしまうのでしょうか。その背景には、日本の司法が抱える構造的な問題があると、私は考えています。
1. 高すぎる「危険運転致死罪」のハードル
2001年に創設された「危険運転致死傷罪」は、悪質な運転への厳罰化を目的としていました。しかし、その適用要件は「アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態」「進行を制御することが困難な高速度」など、極めて厳格に定められています。そのため、今回のケースのように、たとえ時速178kmで暴走していても、「制御が困難だった」という立証ができなければ、適用が見送られてしまうのです。結果として、より刑の軽い「過失運転致死罪」に落ち着いてしまうケースが後を絶ちません。
2. 「加害者の更生」を重視する思想
日本の刑事司法は、加害者を罰すること以上に、「更生の機会を与えること」を重視する傾向があります。特に加害者が未成年であった場合、その「未来の可能性」が過度に考慮され、結果として刑罰が軽くなることがあります。もちろん、更生は重要です。しかし、それによって、奪われた命の重さや、遺族の無念さが軽んじられて良いはずがありません。**「加害者の未来」と「被害者の失われた未来」。この二つが、あまりにも不均衡に扱われている**のが現状ではないでしょうか。
3. 社会全体の「車への甘さ」
そして最も根深いのは、私たち社会全体の「車への甘さ」です。誰もが運転する可能性があるからこそ、交通事故を「誰にでも起こりうる、不運な事故」と捉えがちです。しかし、無免許で、時速178kmで暴走する行為は、もはや「不運」ではありません。それは、**車という「鉄の塊」を、意図的に「凶器」に変えた行為**です。この認識のズレを、社会全体で是正していく必要があります。
「自分だけは大丈夫」という病。明日、あなたが加害者にならないためにできる“3つの約束”
「あんな無謀な運転、自分はしないから関係ない」——そう思った方もいるかもしれません。しかし、交通事故の多くは、特別な悪人ではなく、ごく普通の人が「自分だけは大丈夫」という、根拠のない自信によって引き起こしています。明日、あなたが加害者にならないために、今日からできる3つの具体的な約束を提案します。
-
- 約束1:「ながらスマホ」を、今日、本気でやめる
赤信号で少しだけ、渋滞中だから…。どんな理由があっても、運転中にスマートフォンを操作する行為は、時速178kmの暴走と同じ、危険な「未必の故意」への入り口です。その一瞬の油断が、誰かの一生を奪う可能性がある。その事実を、今日、改めて肝に銘じましょう。 - 約束2:自分の運転を「客観視」する時間を作る
ドライブレコーダーは、他者から身を守るためだけのものではありません。自分の運転を見返すことで、無意識のクセや危険な瞬間を客観的に知ることができます。「思ったより車間距離が近いな」「この交差点、一時停止が甘かったな」。その小さな気づきが、未来の事故を防ぎます。 - 約束3:交通死亡事故の「遺族の手記」を一冊読む
これが最も効果的かもしれません。中本佐智さんの『「行ってきます」が最後の言葉になった』など、交通事故遺族が綴った手記を、一度でいいから読んでみてください。ニュースの数字の裏にある、生々しい悲しみ、怒り、そして後悔。その魂の叫びに触れたとき、あなたのハンドルを握る手の重みは、きっと変わるはずです。
- 約束1:「ながらスマホ」を、今日、本気でやめる

結論:ハンドルを握ることは、他人の人生を背負うこと。その覚悟が、私たちにはあるか
中本大貴さんの命を奪った事故から、9年以上の歳月が流れました。しかし、母・佐智さんの闘いは、今も続いています。彼女が求め続けているのは、厳罰化だけではありません。それは、**「命の重み」が正当に扱われる社会**であり、**自分の息子のような犠牲者が二度と生まれない社会**です。
車は、私たちの生活を豊かにする便利な道具です。しかし、一歩間違えれば、いとも簡単に人の命を奪う凶器と化す。その当たり前すぎる事実を、私たちはあまりにも軽視しすぎていたのではないでしょうか。
ハンドルを握ることは、ただ車を動かすことではありません。それは、道路を共有するすべての人の人生を、その家族の未来を、自分の両手に背負うということです。その覚悟が、果たして今の私たちにあるのか。中本さんの静かで、しかし力強い声は、私たち一人ひとりの心に、その重い問いを投げかけ続けています。
📢 この記事をシェア
もしこの記事が、交通安全について改めて考えるきっかけになったなら、ぜひSNSでシェアしてください。
💬 あなたの意見を聞かせてください
交通刑罰のあり方や、私たちが日常でできる事故防止策について、あなたはどう考えますか? ぜひコメント欄で、あなたの考えをお聞かせください。


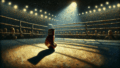
コメント