この記事のポイント
- 古舘伊知郎氏の指摘通り、中国など外国資本による日本の土地買収は今に始まった問題ではなく、バブル崩壊後の経済政策、特に規制緩和とグローバリゼーションの帰結である。
- 世界的に見ても、日本は外国人の土地・不動産購入に対する規制が極めて緩く、円安も相まって「買いやすい国」になっているのが現状。
- 安全保障上の懸念から「重要土地利用規制法」が施行されたが、これは土地の「利用」を監視するもので、「売買」そのものを制限するものではないため、根本的な解決には至っていない。
- 土地買収は経済活性化という側面も持つため、単純な脅威論では本質を見誤る。経済合理性と安全保障という二律背反の課題として、国民的な議論が不可欠である。
序章:古舘伊知郎はなぜ今叫ぶのか?「もう手遅れ」の警告
「中国人がガンガン、日本の土地を買ってるって、最近のことのように言うなよ」
フリーアナウンサーの古舘伊知郎氏が自身のYouTubeチャンネルで放ったこの言葉は、多くの人々の心に突き刺さりました。彼の警告は、単なる感情的なものではありません。それは、日本の土地が外国資本、特に中国資本によって買収されているという「中国 土地買収 問題」が、一朝一夕に生まれたのではなく、長年にわたる日本の政策選択の結果であるという、痛烈な事実を突きつけています。
多くの人が抱く「日本の国土が静かに奪われているのではないか」という漠然とした不安。古舘氏の指摘は、その不安の根源がどこにあるのかを指し示しています。それは、バブル崩壊後、経済再生を最優先するあまり、安全保障という視点が後回しにされてきた日本の歴史そのものにあるのかもしれません。
この記事では、単なる「中国脅威論」で思考停止するのではなく、古舘氏の叫びを入り口に、以下の点を徹底的に掘り下げていきます。
- なぜ日本はこれほどまでに「買いやすい国」になってしまったのか?
- 政府の対策は本当に機能しているのか?
- 経済的な利益と安全保障のリスクを、私たちはどう天秤にかけるべきなのか?
これは対岸の火事ではありません。日本の未来、そして私たちの子供たちの世代に何を残すのかを問う、私たち自身の問題です。
第1章:あなたの隣の土地も?日本で静かに進む「重要土地」の買収実態
「外国資本による土地買収」と聞いても、多くの人にとってはどこか遠い話に聞こえるかもしれません。しかし、その現実は着実に、そして日本の安全保障の根幹を揺るがしかねない場所で進行しています。
北海道から沖縄まで、具体化する安全保障上の懸念
例えば、広大な土地と豊かな水資源を持つ北海道。特にスキーリゾートとして世界的に有名なニセコ町では、外国人による土地購入が活発です。また、過去には中国資本が沖縄の無人島「屋那覇島」の約半分を購入したというニュースも大きな話題となりました。
2020年には中国人が沖縄の屋那覇島の51%を購入し話題に
「オーバーツーリズム」で話題のニセコ町も外国人の土地購入が多い
これらの事例は氷山の一角に過ぎません。より深刻なのは、日本の安全保障上、特に重要なエリアでの土地取引です。
政府が公表したデータによると、防衛施設周辺など安全保障上重要な土地や建物の令和5年度の取引において、驚くべき事実が明らかになっています。
政府が昨年12月に公表した防衛施設の周辺など安全保障上で重要な土地や建物の令和5年度の取引数は、中国人や中国系法人によるものが計203件と最多で全体の約55%を占めた。
実に半数以上が、中国資本による取引なのです。自衛隊基地や米軍基地の周辺、国境に近い離島といった機微なエリアの土地が、誰に、どのような目的で買われているのか。その実態把握が追いついていない現状は、国防上の大きなリスクと言わざるを得ません。問題は、もはや「噂」や「憶測」のレベルではなく、具体的なデータとして私たちの目の前に突きつけられているのです。
第2章:歴史検証|なぜ日本は『買いやすい国』になったのか?
古舘氏が「小泉政権の頃から始まって」と指摘したように、現在の状況は、過去の経済政策の積み重ねによって形作られました。なぜ、日本は世界でも類を見ないほど「外国資本に土地が買いやすい国」となったのでしょうか。その歴史を紐解いてみましょう。
世界でも異例の「規制なき市場」
まず、大前提として知っておくべき衝撃的な事実があります。それは、主要国の中で、外国人がほとんど何の制限もなく土地を自由に売買できる国は、日本くらいしかないということです。
実はほとんど制限なく外国人が土地を売買できる国は、世界のどこを見ても日本以外にありません。
諸外国の多くは、安全保障や食料自給の観点から、外国資本による土地取得に厳しい制限を設けています。しかし、日本では、一部の例外を除き、外国人も日本人と全く同じ手続きで土地や建物を購入できます。この「開かれた市場」が、現在の中国資本による土地買収問題の温床となっているのです。
経済再生を優先した「政策選択」の帰結
日本の土地規制が緩やかになった背景には、歴史的な経緯があります。戦前には「外国人土地法」という法律が存在し、国防上の観点から外国人の土地取得を制限する仕組みがありました。しかし、戦後はこの法律が実質的に機能しない状態が続きます。
第4条では、国防上必要な地区においては、政令によって外国人・外国法人の土地に関する権利の取得を禁止、または条件もしくは制限をつけることができると定めている。
決定的な転換点となったのは、バブル経済が崩壊し、日本経済が長期停滞に陥った1990年代以降です。当時の日本政府は、経済を再生させるために、海外からの投資、つまり「外資」を積極的に呼び込む政策にかじを切りました。
その象徴的な出来事が、1995年の世界貿易機関(WTO)加盟時に結ばれた「サービスの貿易に関する一般協定(GATS)」です。この協定には、自国民と外国人を差別しない「内外無差別」の原則があります。多くの国は、自国の安全保障などを理由に、特定の分野でこの原則の例外(留保条項)を設けました。しかし、日本は、外国人による土地取得を規制する留保条項を盛り込まなかったのです。
日本は1995年の加盟時に、米国など諸外国と異なり外国人による土地取得を規制する留保条項を同協定に盛り込まなかった。当時は外資の呼び込みを優先したためだ。
この判断は、その後の日本の方向性を決定づけました。古舘氏が言及する小泉政権下の「規制緩和」路線も、この大きな流れの中で加速していきます。経済合理性を最優先し、海外からのお金を呼び込むことで日本経済を立て直す。その「政策選択」が、結果として安全保障上の扉を大きく開け放ってしまったのです。今の状況は、誰かの陰謀ではなく、過去の日本自身が下した判断の帰結と言えるでしょう。
第3章:単純な悪ではない?土地買収の『光と影』
外国資本による土地買収を、単純に「悪」や「脅威」と断じるのは早計かもしれません。物事には必ず光と影があります。この問題を冷静に考えるためには、経済的なメリットと安全保障上のデメリットを天秤にかける視点が不可欠です。
光:経済活性化と過疎地の再生
外国資本が日本の不動産に投資することには、明確な経済的メリットも存在します。
- 経済の活性化: 特に都市部のタワーマンションやリゾート地の別荘など、高額な物件が海外の富裕層によって購入されることで、不動産市場が活性化し、関連産業にお金が回ります。
- 過疎地域の救済: 日本では人口減少や高齢化により、買い手のつかない土地や放置された山林(所有者不明地)が全国で増加しています。こうした土地に海外から買い手がつくことは、固定資産税収の確保や地域の経済循環につながるという側面もあります。
- インバウンド需要の創出: ニセコのように、海外資本によって国際的なリゾート地として開発が進むことで、多くの外国人観光客を呼び込み、地域経済全体が潤うケースもあります。
バブル崩壊後の長いデフレに苦しんできた日本にとって、海外からの投資は、経済を浮上させるための「処方箋」の一つとして期待されてきたのです。
影:安全保障と国土保全のリスク
一方で、その影は深く、暗いものです。特に規制が緩い日本では、そのリスクがより顕在化しやすくなっています。
外国人による日本の土地売買で指摘されている問題点
問題点①:取得した土地の使途が自由すぎる
問題点②:トラブル時に日本の法律を適用できない可能性がある
問題点③:国土の大部分が外国人所有になるリスクがある
問題点④:「外国人自治区」を作られる可能性がある
これらの問題点の中でも、特に深刻なのは以下の2点です。
- 安全保障上のリスク: 第1章で見たように、自衛隊基地やインフラ施設の周辺土地が買収されれば、通信の傍受や監視活動の拠点として利用される恐れがあります。これは国の防衛能力を直接的に脅かす行為につながります。
- 水資源や食料安全保障の問題: 北海道の水源林などが買収されることは、日本の貴重な水資源のコントロールを外国資本に明け渡すことになりかねません。同様に、広大な農地が買われれば、将来の食料安全保障にも影響を及ぼす可能性があります。
経済の活性化という短期的な「光」を追い求めるあまり、国の根幹である安全保障や資源という長期的な「影」の部分を見過ごしてはいないか。この中国 土地買収 問題は、私たちにその根本的な問いを突きつけているのです。
第4章:政府の対策はザルなのか?『重要土地利用規制法』の限界と課題
高まる国民の不安や安全保障上の懸念を受け、日本政府も手をこまねいていたわけではありません。2022年9月に全面施行されたのが「重要土地等調査法(通称:土地利用規制法)」です。
しかし、この法律は本当に有効な対策となっているのでしょうか。その中身と限界を見ていきましょう。
「売買」ではなく「利用」を規制する法律
まず、この法律の目的を正確に理解する必要があります。
本法は、日本の安全保障環境の変化を踏まえ、重要施設の周辺、国境離島等の周辺における土地等の利用状況の調査、利用の規制等を行う法律です。
この法律は、自衛隊の基地や原子力発電所といった「重要施設」の周辺や国境離島などを「注視区域」や「特別注視区域」に指定します。そして、それらの区域内で、施設の機能を妨害するような行為(例えば、電波妨害やドローンによる妨害飛行など)が行われていないかを調査し、問題があれば中止を勧告・命令できるというものです。
この法律ができたことで、これまで手つかずだった安全保障の観点からの土地利用調査が可能になったことは、間違いなく一歩前進です。しかし、そこには決定的な限界が存在します。
抜け穴だらけ?根本問題に踏み込めない実態
この法律の最大の課題は、あくまで土地の「利用」を規制するものであり、土地の「売買」そのものを規制するものではないという点です。
法整備の際、野党だけでなく、自民の一部や公明党から私権制限や経済活動の鈍化を招きかねないとの声が上がり、規制する行為が「売買」ではなく「利用」に限定されたためだ。
つまり、外国資本が防衛施設の隣の土地を買うこと自体は、この法律では止められません。購入後に問題のある「利用」が確認されて初めて、行政が介入できる仕組みなのです。これでは、問題が起きてから対応する「後手」の対策と言わざるを得ず、抑止力としては不十分です。
また、この法律は「外国人」だけを対象にしたものではなく、日本人にも適用されます。これは、憲法で保障されている財産権(私権)の制限につながりかねないという慎重な議論の結果ですが、それゆえに外国資本の流入を直接食い止めるような強力な規制にはなり得ていません。
結果として、「対策は講じられた」というアリバイにはなっても、中国資本による土地買収問題の根本的な蛇口を締めるには至っていない、というのが厳しい現実なのです。
結論:私たちは未来の子供たちに何を残すのか?
古舘伊知郎氏の「最近のことのように言うなよ」という叫びは、この問題の根源が、日本の戦後から続く経済政策と安全保障に対する姿勢そのものにあることを示唆しています。
バブル崩壊後、日本は経済再生という至上命題のために、外資を呼び込むことを優先しました。規制緩和を進め、グローバル経済の波に乗ることで、短期的な利益を追求してきたのです。その結果、世界でも類を見ないほど「土地が買いやすい国」となり、安全保障や資源確保といった、目先の利益には直結しない長期的な国益がないがしろにされてきた側面は否定できません。
この問題は、単純な「中国脅威論」で片付けられるものではありません。むしろ、経済合理性と安全保障という二律背反のテーマを前に、日本社会全体がどのような選択をしてきたのか、そしてこれからどのような選択をしていくのかを問う、極めて国内的な構造問題です。
「重要土地利用規制法」という対策は打たれましたが、それはあくまで対症療法に過ぎません。土地の「売買」そのものにどう向き合うのか、私権の制限と国益のバランスをどう取るのか、といった根本的な議論を避けていては、静かなる国土の買収は止まらないでしょう。
今、私たち一人ひとりに求められているのは、この問題を一過性のニュースとして消費するのではなく、継続的に監視し、学び、声を上げることです。短期的な経済の甘い果実と、長期的な国家の安全。そのどちらを優先するのか。その判断は、最終的にこの国に住む私たち自身に委ねられています。未来の子供たちに、安全で豊かな日本を残すために、今こそ真剣な国民的議論を始める時です。

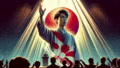

コメント