この記事のポイント
- ロバーツ監督が佐々木朗希を「クローザー」と呼ばない。それは不信感どころか、現代MLBの最先端戦術「ハイ-レバレッジ・リリーバー」として起用するという、最大の信頼の証だ。
- 監督は過去にもクローザーを固定しない哲学を貫いてきた。これは、チームの勝利を最大化するための、一貫した戦略なのである。
- チーム内の人間関係や、メジャー1年目の佐々木にかかる過度なプレッシャーを回避する、巧みなマネジメント術も見て取れる。
- 結論、「クローザーと呼ばない」という言葉は、佐々木を「9回限定の投手」ではなく、「試合で最もヤバい場面を任せる究極の切り札」と認める、最高の賛辞なのだ。
導入:なぜだ? あの完璧な投球を見せた佐々木朗希を、指揮官は「クローザー」と呼ばないのか
「この男がいれば、世界一も夢じゃない」――ポストシーズンの熱狂に沸くドジャー・スタジアムで、多くのファンがそう確信したはずだ。その中心にいたのは、一人の日本人投手。佐々木朗希、23歳。フィリーズとの激闘、わずか2点リードという息詰まる場面でマウンドに上がると、彼の右腕から放たれる162.5キロの火の玉が、強打者たちのバットを次々と空に斬らせていく。
怪我の悪夢から蘇り、ブルペンの絶対的救世主となったその姿は、我々の目に新しい「守護神」の誕生を焼き付けた。しかし、だ。試合後の会見で、名将デーブ・ロバーツ監督の口から飛び出したのは、我々の期待を裏切る、あまりにも不可解な言葉だった。
「ロウキをクローザーと呼んでいいか?」という記者の問いに、彼はこう答えたのだ。「彼は間違いなく最も信頼できるリリーフの一人だ。しかし9回固定では決めたくない」。この「クローザーと呼ばない」宣言は、USAトゥデイ紙の名物記者ボブ・ナイチンゲールが即座にXで報じるなど、全米を駆け巡る大きな波紋を呼んだ。
なぜ、これほど圧倒的な結果を見せつけた若き才能を、ロバーツは「クローザー」と認めないのか? 不信感か? それとも何か裏があるのか? いや、違う。その言葉の裏には、現代メジャーリーグの深遠なる戦略と、知られざるチーム事情が複雑に絡み合っていたのだ。さあ、あなたも一緒に、この謎めいた発言の深層を解き明かす旅に出ようではないか。
【考察1】「大人の事情」か? チーム内に渦巻くベテランへの忖度とプライド
まず我々が足を踏み入れねばならないのは、グラウンドの外、もっと生々しい「人間関係」の世界だ。あなたがもし、これまでチームを支えてきたベテランリリーフ投手だったとしたら、どう感じるだろうか?
ドジャースのブルペンには、2023年に24セーブを挙げたエバン・フィリップスという不動の中心人物がいる。彼の存在なくして、今のドジャースはなかったかもしれない。そんな彼の、そして他の功労者たちのプライドを飛び越えて、シーズン終盤に彗星の如く現れたルーキーを、たった数試合の結果で「新しい守護神だ」と公式に戴冠させてしまう。それは、チーム内に不必要な亀裂を生みかねない、危険な賭けだ。
選手心理の掌握に長けたロバーツ監督が、そのリスクを知らないはずがない。「クローザーは一人じゃない。誰もが最も重要な場面でヒーローになる可能性があるんだ」――。特定の称号を与えないことで、彼はブルペン全体の競争心を煽り、一体感を維持しようとしている。これは、もはや野球の采配ではない。
そう、これは巨大組織を率いるトップマネージャーが下す、極めて高度な組織マネジメント術なのだ。個々の感情にまで配慮し、チームという生き物を最高の状態で動かす。彼の言葉の裏には、そんな計算が働いていると見るのが自然だろう。
【考察2】なぜ最強の切り札を9回に温存するのか? 「ハイ-レバレッジ」という不都合な真実
だが、「大人の事情」だけが理由ではない。私が最も本質的だと考える理由は、もっと戦術的で、もっとドライな世界にある。現代MLBの最先端トレンド、「ハイ-レバレッジ・リリーバー」という考え方。これこそが、今回の謎を解く最大のカギだ。
知っていますか? 試合の本当の“勝負所”は9回ではない
「ハイ-レバレッジ」なんて言葉を聞くと、難しく感じるかもしれない。だが、話は至ってシンプルだ。「レバレッジ」とは「てこ」のこと。野球で言えば、「試合の勝敗を最も大きく左右する局面」を指す。そして、ここが重要なのだが、試合の本当の“勝負所”は、必ずしも最終回にやってくるとは限らないのだ。
想像してみてほしい。2点リードの7回裏、一死満塁で相手はクリーンナップ。ここで1本出れば逆転、抑えれば勝利は目前。この場面こそ、その試合で最も“レバレッジが高い”瞬間ではないだろうか?
ロバーツ監督の頭の中は、まさにこれでいっぱいなのだ。彼の言葉を直接聞いてみよう。
彼は間違いなく最も信頼できるリリーフの一人だ。しかし9回固定では決めたくない。打線の並びによっては、8回が重要になる場合もある。彼は勝敗に直結する大事な場面で投げられる投手と考えている。
お分かりだろうか? 佐々木朗希という160キロ超の剛速球と悪魔的なスプリットを操る「最強のカード」を、「9回専門」という古い常識の檻に閉じ込めることこそ、最大の損失なのだ。監督は、佐々木を試合の趨勢を決める真のクライマックスで使う「ジョーカー」として、手元に置いておきたいのだ。8回だろうが7回だろうが、チームが最も彼を必要とする場面に投入する。そのための「クローザーと呼ばない」宣言なのだ。
「最終的には、その一つの場面で最も信頼できると感じる投手と共に行くしかない」。Dodgers Nationの取材にそう語る監督の哲学は揺るぎない。(Dave Roberts Weighs in on Whether Roki Sasaki is the Dodgers … – Dodgers Nation)
これは佐々木への不信ではない。むしろ、「君は9回だけじゃない。試合のどの局面でもゲームを支配できる、我々の“究極兵器”なのだ」という、これ以上ない信頼のメッセージなのである。
【考察3】日本人は誤解している? “守護神”という言葉がメジャーで持つ本当の意味
それでも、なぜ我々日本のファンは、このロバーツ監督の発言にモヤモヤしてしまうのだろうか? その答えは、あなたや私の中に、知らず知らずのうちに深く根付いている“野球観”そのものにある。
日本では、「クローザー」は「守護神」や「大魔神」と呼ばれ、チームの絶対的な砦として神格化される。9回、お決まりの登場曲がスタジアムに鳴り響き、マウンドに向かうその姿は、もはや一種の“儀式”だ。「9回を任されること=チーム最高の投手」。そこに、疑いの余地はない。
一方、データが支配する近年のMLBでは、その考え方は古臭いものになりつつある。役割を固定することの非効率性を嫌い、常に状況に応じた最適解を探す。リリーフ投手の役割は、水のように流動的(Fluid)に捉えるのが主流なのだ。
事実、ロバーツ監督のこの哲学は、今に始まったことではない。絶対的クローザーだったケンリー・ジャンセンがチームを去って以来、彼は意図的に特定の誰かを「クローザー」と呼ぶことを避けてきた。RONSPOの記事が、その一貫性を鋭く指摘している。
2023年にエバン・フィリップスが24セーブを挙げた時でさえ、「クローザー」とは呼ばなかった。「フィリップスの役割を流動的にする柔軟性を重視したため」だという。
つまり、佐々木朗希への対応は、彼個人に向けられた特別なものではなく、ロバーツ監督が長年貫いてきた揺るぎないブルペン哲学の表れなのだ。この日米の文化や監督個人の哲学という「背景」を理解して初めて、我々はこの発言の真意にたどり着くことができる。これは野球のようで、実は「異文化コミュニケーション」の問題なのである。
【考察4】これは“親心”か、それとも――。 23歳の若武者を潰さないための深謀遠慮
そして最後に、忘れてはならない視点がある。それは、戦術や哲学を超えた、ロバーツ監督という一人の“人間”としての、佐々木朗希という若者への温かい眼差しだ。
彼が今季、どれほどの逆境と戦ってきたか、あなたは想像できるだろうか。Sports Illustratedの記事も伝えるように、メジャーという新しい環境、ケガとの戦い、そして自信の喪失…。5月から長い離脱を経験した彼が、ようやく掴んだポストシーズンの大舞台。そのプレッシャーは、我々の想像を絶する。
そんな彼に、もし監督が「彼が我々の新しいクローザーだ」と宣言してしまったら? 佐々木の肩には、ワールドシリーズ制覇という、あまりにも重い十字架がのしかかる。たった一度の失敗が、「クローザー失格」の烙印となり、メディアとファンからの容赦ない批判に晒されるかもしれない。
だからこそ、監督はあえて「信頼できるリリーバーの一人」という表現に留めたのではないか。それは、「一人ですべてを背負い込むな。君はチームの一員だ。ただ、自分の力を出すことだけに集中してくれ」という、静かで、しかし力強いメッセージ。若き才能を潰さず、未来を見据えて育てる。私にはそれが、まるで“親心”のようにも思えてならない。
「長いシーズンを通して毎試合リリーフ登板する形で準備を続けるのは現実的ではない」。佐々木本人も、あくまで短期決戦での役割だと冷静に自分を見つめている。監督の発言は、彼のそうした状況も踏まえた、極めて現実的な判断でもあるのだ。
結論:『君はクローザーではない』――それは、佐々木朗希への“最大級の賛辞”だった
ここまで見てきたように、ロバーツ監督が佐々木朗希を「クローザー」と呼ばない理由は、断じて彼の力を疑っているからではない。我々は、その真逆の結論にたどり着く。
- チームの和を乱さないための、巧みな「組織マネジメント」(考察1)
- 彼の能力を120%引き出すための、「最先端のMLB戦術」(考察2)
- 監督自身が貫いてきた、揺るぎない「一貫した哲学」(考察3)
- 若き才能を重圧から守るための、「親心にも似た配慮」(考察4)
これらのすべてが絡み合い、あの「クローザーと呼ばない」という一言に集約されているのだ。
「クローザー」という、たった一つの役割に押し込めるには、佐々木朗希という才能はあまりにも規格外すぎる。彼こそが、試合の流れを根底からひっくり返す力を持つ“究極兵器(アルティメット・ウェポン)”であり、だからこそ、最も効果的な一点で投下されねばならない。
そう、あの言葉は、9回というイニングの呪縛から彼を解き放ち、「ドジャースの勝敗を左右する、あらゆる危機的状況を支配する救世主」として認める、最大級の賛辞だったのである。
これから続く死闘の中、佐々木朗希は一体いつ、どんな場面でマウンドへ向かうのか。9回二死満塁か、はたまた試合が最も動く7回のピンチか。ロバーツ監督が、その“最高の瞬間”に背番号17を告げるその時を、我々は固唾をのんで見守るしかない。その起用法こそが、言葉以上に雄弁な、監督から佐々木への信頼のメッセージとなるはずだからだ。
📚 参考情報・出典
- なぜだ?「バカバカしい。ロウキが守護神だ」ロバーツ監督が佐々木朗希を「クローザー…
- Is Roki Sasaki the Dodgers’ Closer? Dave…
- Roki Sasaki appears to be new Dodgers cl…
- Dave Roberts when asked if Roki Sasaki i…
- Dave Roberts Weighs in on Whether Roki S…
- Dave Roberts Still Declines to Name Roki…
- Evan Phillips Stats, Height, Weight, Pos…
- Evan Phillips – Stats – Pitching | FanGr…

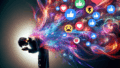
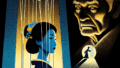
コメント