この記事のポイント
- ドジャースは勝利したものの、9回に佐々木朗希を頭から起用しなかったデーブ・ロバーツ監督の継投策に「迷走采配」と批判が殺到。
- 監督は佐々木の連投を考慮したと説明するも、前日の発言との矛盾が露呈し、采配への疑問が深まっている。
- フィリーズOBからは「メジャー史上最も馬鹿な采配」と酷評され、専門メディアも「クローザーは佐々木しかいない」と断言。
- 結果的に佐々木が窮地を救ったが、この一件はポストシーズンにおける監督の決断力と、佐々木の起用法が今後の鍵を握ることを浮き彫りにした。
「なぜ、彼を最初から出さないんだ?」――勝利の裏で燃え上がった、世紀の“迷采配”騒動
ポストシーズンの熱狂。勝利こそが、すべてを癒し、正当化するはずだった。ロサンゼルス・ドジャースは敵地でフィラデルフィア・フィリーズを打ち破り、ディビジョンシリーズ突破に王手をかけた。しかし、勝利の美酒に酔うはずだったその夜は、一人の男の“不可解な決断”によって、苦々しい疑念と怒号に満ちた一夜に変わってしまった。
3点リードで迎えた最終9回。誰もが確信していたはずだ。マウンドに上がるのは、若き絶対的守護神、佐々木朗希(23)だと。だが、デーブ・ロバーツ監督がコールしたのは、ベテランのブレイク・トライネン(37)。この瞬間、勝利への確実なレールは、崩壊への断崖絶壁へと姿を変える。
トライネンはアウトを一つも奪えずに降板。後を受けたアレックス・ベシア(29)も火のついた相手打線を止められない。あれよあれよという間に、一打サヨナラの危機。万事休すかと思われた二死一、三塁、絶体絶命の土壇場で、ようやく「真打ち」佐々木がコールされた。対するは今季の首位打者トレー・ターナー。しかし、この国の至宝は、わずか2球でこの窮地をねじ伏せ、セカンドゴロに打ち取ってみせた。
記録の上では、ドジャースの勝利、そして佐々木のポストシーズン2セーブ目という輝かしい文字が刻まれた。だが、ファンやメディアの胸に渦巻いたのは安堵ではない。「なぜ、こんな心臓に悪い“劇場”に付き合わされなければならなかったんだ?」という、煮えたぎるような憤りと疑問だった。
なぜ佐々木はベンチだったのか?ロバーツ監督、矛盾だらけの言い訳を徹底解剖
なぜ、ロバーツ監督は9回の頭から、チームが絶対的な信頼を寄せる佐々木をマウンドに送らなかったのか?今回の騒動の核心は、すべてこの一点に集約される。試合後、監督の口から語られたその理由は、しかし、火に油を注ぐだけの結果に終わった。
一夜にして覆された「信頼の言葉」。その舌の根も乾かぬうちに…
記者団の「9回の頭から佐々木の起用は考えなかったのか?」という当然の問いに、監督は苦しい表情でこう弁明する。
「考えはした。ただロウキには3試合中2試合のような登板リズムを試していたが、それを複数やっているわけではなかった。だから今日は無理に続けて投げさせたくなかった」
なるほど、聞こえはいい。若き至宝のコンディションを気遣った、親心のような采配だったと。だが、思い出してほしい。つい前日、彼は一体何と言っていただろうか。佐々木がシーズン終盤に意図的に試した中1日での登板に触れ、「(試合間隔の狭い登板に)心配はない」と、自信たっぷりに断言していたではなかったか。この言葉があったからこそ、私たちは皆、佐々木の連投を信じて疑わなかったのだ。
このあまりにも鮮やかな手のひら返し。一貫性を欠いたその場しのぎの説明は、「この監督、本当に行き当たりばったりで采配しているんじゃないか?」という、拭いきれない不信感を植え付けるのに十分すぎるものだった。
「過去の栄光」にすがるのか?ファンが突きつけた痛烈な”NO”
では、佐々木ではなくトライネンだった理由は?監督は「ブレイク(トライネン)は、ポストシーズンで何度も重要なアウトを取ってくれた。彼を信頼した」とも語る。つまり、37歳のベテランが過去に積み上げた「実績」という名の神話に賭けたわけだ。
しかし、そんな理屈が今のファンに通じるだろうか。スポーツメディア『Dodgers Nation』に寄せられた「去年彼は信頼に値したが、今年は違う。今年のパフォーマンスで采配してくれ!」という悲痛な叫び。これこそが、ファンの総意ではないだろうか。過去の栄光ではなく、今、この瞬間、誰が最も頼りになるのか。その答えは、誰の目にも明らかだったはずだ。
当の佐々木は、チームの苦境を見て自らリリーフ転向を志願したとまで言われている。米ESPNによれば、ロバーツ監督はそんな彼の姿を「彼はキラーの顔つきになった」と絶賛したという。そこまで惚れ込みながら、なぜ最大の“狩り場”で、その“キラー”を檻に閉じ込めたままだったのか。監督の言葉と行動は、あまりにも矛盾に満ちている。
「メジャー史上最も馬鹿な采配」――内外から浴びせられる容赦なき罵声
あなたが感じたその怒りや疑問は、決して一人だけのものではない。ロバーツ監督の常軌を逸した采配には、専門家やOBたちからも、もはや批判という生易しいレベルを超えた、容赦ない罵声が浴びせられている。
「佐々木がいなければ、ただのゴミ箱だ」元守護神が吐き捨てた痛烈な一言
最も痛烈だったのは、対戦相手フィリーズのOBであり、百戦錬磨のクローザーだったリッキー・ボタリコ氏だ。RONSPOの記事によると、彼に言わせれば、今回の継投はまさに「メジャー史上最も馬鹿な采配のひとつ」。さらに「佐々木がいなければゴミ箱みたいなブルペン」とまで吐き捨て、監督の決断を木っ端微塵にこき下ろした。
敵将からの言葉とはいえ、これはただのリップサービスではない。百戦錬磨のプロの目から見ても、今回の采配がいかに理解不能で、危険なギャンブルだったかを物語っている。彼のYouTubeチャンネルでは「佐々木いなけりゃブルペンはゴミ」という、もはや悪口に近いタイトルが躍る始末だ。
「もはや彼しかいない」専門メディアが下した最終通告
メディアも黙ってはいない。ドジャースの専門メディア『Dodgers Nation』のノア・カムラス記者は、試合終了の直後、自身のX(旧ツイッター)にこう叩きつけた。
「ロキ・ササキはドジャースのクローザーだ。他の選択肢はない。ササキはドジャースを救った。1点差の9回、NL首位打者トレア・ターナーを退治した。23歳で、彼は最大の力を発揮した」
「他の選択肢はない」。この力強い断言が、あなたの胸をえぐるように響かないだろうか。これはもはや単なる称賛ではない。なぜ「他の選択肢(トライネン)」を選んだのかという、指揮官への痛烈な皮肉であり、「いい加減、目を覚ませ」という最後通告に他ならない。皮肉にも、監督の迷采配こそが、佐々木こそが真のクローザーであることを、全世界に証明してしまったのだ。
本当にただの“迷采配”なのか?ロバーツ采配をあえて擁護してみる、たった一つの可能性
ここまで、我々はロバーツ監督を徹底的に批判してきた。だが、少しだけ視点を変えてみよう。あるいは彼の頭の中には、我々には理解できない、メジャーリーグ特有のロジックが存在したのかもしれない。もちろん、これは結果を正当化するものでは決してないが。
知られざるメジャー流「勝利の方程式」のリアル
日本のプロ野球では、「7回はA投手、8回はB投手、9回はクローザー」という固定化された『勝利の方程式』がお馴染みだ。あなたも、それを信じて疑わないだろう。しかし、近年のメジャーリーグでは、より柔軟で、データに基づいたブルペン運用が主流になりつつある。
その哲学とは、「9回だからクローザー、ではない。試合で最もヤバい場面(ハイレバレッジ・シチュエーション)に、最も信頼できる投手をぶつける」というものだ。たとえそれが7回であっても、一死満塁のピンチを迎えれば、迷わずクローザーを投入する。それがメジャーの合理主義なのだ。
この理屈に立てば、こう解釈できなくもない。ロバーツ監督は「9回頭の3点差」より、「1点差の二死一、三塁で首位打者を迎えた場面」こそが真のクライマックスだと判断し、そこに“最高のカード”である佐々木を切ったのだ、と。だが、この擁護論には致命的な欠陥がある。
だが、その理屈は通用しない。「結果オーライ」で失った、あまりに大きな代償
考えてみてほしい。そもそも、その最大のピンチを“作り出した”のは、一体誰だったのか?最高の投手を使わずに、自らチームを崖っぷちに追いやっておいて、「ここが勝負どころだ!」と最高のカードを切る。それは果たして名采配と呼べるのだろうか。
「結果オーライ」の一言で片付けるには、この采配が残した爪痕はあまりに大きい。
- ブルペンの無駄な消耗:本来なら佐々木一人で済んだはずが、3人もの投手を注ぎ込む羽目になった。
- ファンとチームへの不安:楽勝ムードを一変させ、心臓が止まるようなストレスを全員に強いた。
- 監督への信頼の揺らぎ:その場しのぎの説明と謎の采配は、選手からの信頼をも失いかねない。
これは佐々木への「信頼の証」だったのか。それとも、自らの失敗を糊塗するための、都合のいい「消火器」だったのか。この起用法は、佐々木のチーム内での価値を決定づけた一方で、彼をあまりに危険な形で酷使する未来を予感させるものだった。
結論:この“悪夢”は、偉大な伝説の序章となるか?すべては佐々木朗希の右腕に託された
デーブ・ロバーツ監督の采配は、勝利という最高の結果と引き換えに、痛烈な批判を浴びた。この一件は、短期決戦において指揮官の決断一つが、いかにチームを天国と地獄に振り分けるかを、我々にまざまざと見せつけた。
しかし、信じられないことに、この悪夢のような継投劇は、一つの“伝説”を生み出したのかもしれない。この絶体絶命のピンチを、まるで漫画の主人公のようにねじ伏せたことで、佐々木朗希は単なる一流投手から、チームを勝利に導く絶対的な“救世主”へと、その存在を昇華させたのだ。「彼がマウンドに上がれば、もう大丈夫だ」。その絶対的な安心感を、彼はたった2球でチームとファンに刻み込んだ。
問題は、指揮官がこの“失態”から何を学ぶかだ。これからも過去のデータや感性に固執し、我々ファンが胃をキリキリさせながら見守るような采配を続けるのか。それとも、今、最も信頼できる「キラーの顔つき」になった若き守護神に、すべてをシンプルに託すことができるのか。
ワールドシリーズ制覇への道は、まだ始まったばかりだ。ドジャースがその頂に立つとき、我々はその中心に佐々木朗希の雄姿を見ることになるだろう。そして、その才能を最大限に引き出すも殺すも、すべてはベンチに座る一人の男、デーブ・ロバーツの決断にかかっている。彼の右腕の使い方が、ドジャースの、いや、ベースボールの歴史そのものを左右すると言っても、決して大げさではないだろう。

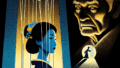
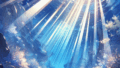
コメント