この記事でわかること
- 「二人で児童養護施設に行けばよかった…」安倍元総理銃撃事件の法廷で、山上被告の妹が涙ながらに語った壮絶な生い立ちと悲痛な後悔。
- 家庭を地獄に変えた母親の狂信。ろうそくの灯りで行われる不気味な祈り、子供への無関心、そして消えた1億円――兄妹を追い詰めた異常な日常とは。
- これは他人事ではない。経済的搾取と精神的虐待に苦しむ「宗教二世」問題こそが、この未曾有の事件の根底に潜む、日本の“病巣”である。
- 妹の勇気ある告発は、社会から見捨てられた子供たちの声なきSOS。同じ悲劇を繰り返さないために、私たちに何ができるのかを問う。
「もし、あのとき施設に行っていたら…」妹の後悔が暴き出す、事件の“もう一つの動機”
「もし、あのとき別の道を選んでいたら…」
あなたも人生で一度は、そんな後悔の念に駆られたことがあるかもしれません。しかし、このありふれた後悔の言葉が、これ以上なく重い意味を持って法廷に響き渡りました。
「私と徹也の2人だけでも、あのとき児童養護施設にでも行けばよかったと後悔している」
2022年に日本中を震撼させた安倍元総理銃撃事件。殺人罪などに問われる山上徹也被告(45)の裁判で、彼の妹が絞り出したのは、あまりにも悲痛な魂の叫びでした。関西テレビの報道によれば、彼女は震える声でこう語り始めます。「今まで生い立ちをほとんど話したことはありません。つらい思いをなるべく忘れようと生きてきました」。この山上被告の妹の証言は、事件の背景に私たちが想像する以上に壮絶な家庭環境があったことを、改めて白日の下に晒したのです。
この記事では、複数の報道から明らかになった妹の証言という名の“パズルのピース”を一つ一つ拾い集め、犯行の真の根源――「家庭の崩壊」と「宗教二世の悲劇」という、この社会が長年見て見ぬふりをしてきた深刻な問題に、真っ向から切り込んでいきます。彼女の涙が私たちに何を問いかけているのか、その深層へ潜ってみましょう。
家庭という名の地獄。証言で蘇る「ろうそくの灯り」と「消えた1億円」
山上被告の妹の証言が描き出したのは、もはや“家庭”とは呼べない、あまりにも不気味な日常でした。母親が旧統一教会(現・世界平和統一家庭連合)の信仰にのめり込むことで、家庭という名の船は安らぎの港ではなく、恐怖と無関心、そして搾取が渦巻く地獄へと突き進んでいったのです。
暗闇に響く母の祈り。「気持ち悪い」と感じた不気味な儀式
妹が「気持ち悪い」と生理的な嫌悪感さえ滲ませたのは、母親の異様な祈りの姿でした。彼女の言葉は、その光景をまるで目の前で起きているかのように映し出します。
母は毎朝、毎晩お祈りをしていた。夜中に縦長の半紙に作った見本みたいなのを見ながら、『日本が韓国に戦争で申し訳ないことをしてすみません』と何度も書いていた。(中略)部屋は電気を消していて、ろうそくの明かりだけ。とても不気味だと思った。
あなたがもし幼い子供だったら、どう感じるでしょうか?暗闇の中、ろうそくの炎に揺れる母親の影と、一心不乱に繰り返される祈りの言葉。それは、どれほど恐ろしい光景だったことでしょう。「なぜ先祖ばかり大切にするのか、生きている人を大事にしてほしい」。そんな妹の必死の訴えも、母親の耳には届きません。彼女にとって大切なのは、目の前で震える我が子ではなく、教団の教えと見えない先祖だったのですから。
「パフェ食べに行こ」甘い罠で連れ去られた先は…
母親の異常さは、子供の純粋な心さえも利用する形で牙を剥きます。妹が忘れられないと語る、ある日の記憶。「パフェを食べに行こう」。普段はありえない母親からの誘いに「うれしくていったら統一教会でした」。「だまされて連れて行かれました」と、裏切られた心の叫びを法廷で吐露したのです。
毎日新聞によれば、そこは教団の偉い人が話し、信者が互いの体を叩き合う異様な空間。「会場に入りたくなかったので、ロビーで待っていました」。子供にとって幸せの象徴であるはずの「パフェ」が、信仰の沼に引きずり込むための偽りの餌だった――。このエピソードは、母親が我が子を、心を持った一人の人間ではなく、信仰活動のための“道具”としか見ていなかったことを残酷なまでに物語っています。
40度の熱より教団が大事?母性と共に消えた1億円
母親の関心は、完全に家庭の外――旧統一教会にありました。「母は世界平和統一家庭連合(旧統一教会)と長兄のことで頭がいっぱいで、私には無関心でした」。その言葉を裏付けるように、彼女は40度の高熱で苦しむ我が子を家に残し、平然と教団の活動に出かけてしまったと証言しています。
その一方で、家庭の資産はブラックホールに吸い込まれるように教団へと消えていきました。伯父の証言などから明らかになった献金の総額は、なんと約1億円。その原資は、自ら命を絶った父親の生命保険金約6000万円と、祖父から相続した不動産の売却益4000万円でした(NNNの報道より)。
産経新聞の報道では、祖父の死後、母親が「天国に行けるように(遺産を)献金をしないとダメだ」と主張した際、妹は「何を言っているんだ、この人は」と、母親に向けた最後の信頼が崩れ落ちる音を聞いたといいます(産経新聞 2025/11/18 18:28)。子供の未来、夫の命、父の遺産。そのすべてが、“信仰”の名の下に無残に食い潰されていったのです。
なぜ誰も助けなかったのか?社会の“網”からこぼれ落ちた兄妹のSOS
「二人だけでも施設へ行けばよかった」。この言葉、あなたはどう聞きますか?これは単なる後悔ではありません。社会のどこにも、彼らのための居場所がなかったという、痛切な告発なのです。なぜ、これほどまでに追い詰められた兄妹は、誰にも助けを求められなかったのでしょうか?
最後の砦だった祖父の家。たった一言で路上に放り出された日
家庭内で唯一の防波堤となり得た祖父もまた、娘(山上被告の母親)の狂信に心底疲れ果てていました。「毎日家が荒れ、不安の中で生きていた」という妹の言葉通り、信仰を巡る母と祖父の衝突は日常茶飯事。そしてある日、ついにその均衡が崩れます。
(祖父から)『出ていけ』と追い出され、家の隣の駐車場に立っていたことがあった。部活帰りの徹也が帰ってきて家に入ろうとしたとき、おじいさんは『出ていけ』と徹也にも言い、徹也は出ていってしまった。
たった一言で、最後の砦だったはずの家から追い出される。このエピソードは、兄妹にとって家庭がもはや安全な場所ではなかった事実を突きつけます。母親の信仰が引き起こした亀裂は、家族を完全に分断し、彼らを文字通り路頭に迷わせたのです。
もしも彼らが“普通の子ども”だったら…機能しなかったセーフティネットの残酷な現実
ここで、私たちは妹の後悔の言葉に基づき、一つの「IF」を考えずにはいられません。もし、あの時、兄妹が本当に児童養護施設に行っていたら、この悲劇は起きなかったのではないか? 想像してみてください。もし、彼らが手を伸ばした先に、温かい手を差し伸べてくれる大人が一人でもいたら…?
この問いは、日本の社会的養護システムが抱える残酷な現実を鋭く突いています。セーフティネットは、確かに存在する。しかし、親による宗教的虐待やネグレクトという“密室の犯罪”に苦しむ子供が、自力でその網にたどり着くのは絶望的に困難なのです。
- 情報へのアクセス不足:助けてくれる場所があることすら、子供たちは知らない。
- 心理的ハードル:親を「売る」ことへの罪悪感。世間体。「施設の子」と呼ばれることへの恐怖が、SOSの声を喉の奥に押し込める。
- 外部からの不可視性:「信教の自由」「家庭の問題」という便利な言葉が、外部の介入を阻む高い壁となる。
山上兄妹が置かれていた状況は、まさにこの典型例でした。助けを求める術を知らず、周囲の大人もその密室で起きている惨劇に気づけない。彼らは社会のど真ん中で、誰にも見つけてもらえないまま、静かに孤立していったのです。
第3章:これは他人事ではない。あなたのご近所でも起こりうる「宗教虐待」という名の犯罪
ここでハッキリさせておきましょう。これは、山上家という“特殊な家族”に起きた悲劇ではありません。この事件は、特定の宗教団体を親に持つことで苦しむ「宗教二世」が、日本社会の至る所で直面している構造的な虐待の問題なのです。
「死にたかった」――山上兄妹だけじゃない、声なき宗教二世たちの絶叫
読売テレビの報道によれば、妹は法廷でこうも叫びました。「つらかった、死にたかった」(読売テレビ)。この短い言葉に凝縮された絶望は、決して彼女一人のものではありません。それは、今この瞬間も声を出せずにいる、無数の宗教二世たちの心の叫びそのものなのです。
彼らが直面する苦しみは、あなたの想像を絶するかもしれません。
- 経済的搾取:親の献金のために家は常に火の車。学びたいことも、叶えたい夢も、すべて諦めさせられる。
- 精神的虐待・ネグレクト:「教え」が絶対。自分の感情や意思はすべて否定され、親の愛は教団にだけ向けられる。
- 社会的孤立:「信者以外はサタン」。外部との交流を禁じられ、世の中から切り離されていく。
- 選択の自由の剥奪:誰を愛し、誰と結婚し、どんな仕事に就くか。人生のすべてを教団に支配される。
朝日新聞が報じた元信者は、「『このままでは子供や孫に厄災が降りかかる』と刷り込まれ」、借金までして数千万円を献金したといいます(朝日新聞 2022年8月13日)。山上家で起きたことは、氷山の一角。あなたのすぐ隣で、子供たちが同じような苦しみに喘いでいるかもしれないのです。
「信教の自由」は免罪符か?見過ごされてきた“聖域”の闇
なぜ、こんな悲劇が長年見過ごされてきたのでしょうか。その背景には、「信教の自由」という、あまりにも高く、厚い壁がありました。親が何を信じようと自由だ。家庭内のことに口を出すな、と。
しかし、問いたい。その「信仰」が子供の人権を著しく踏みにじり、心と体を蝕んでいるとしたら?それは本当に、守られるべき「自由」なのでしょうか。いや、それは紛れもなく「虐待」という名の犯罪です。
山上被告の妹の証言は、この「信仰」と「虐待」の曖昧な境界線を社会に改めて問い直す、極めて重要な意味を持っています。親の信仰のために、子供が未来を奪われる。これを「信教の自由」という言葉で見過ごすことは、私たち社会全体の怠慢であり、共犯行為に他なりません。
結論:妹の涙を無駄にしないために。今、私たちに突きつけられた重い宿題
彼女の証言は、単に兄の罪を軽くしてほしいという願いだけだったのでしょうか?私は、そうは思いません。それは、崩壊した家族の中で兄を救えなかった妹自身の癒えない痛みであり、そして、同じ苦しみの中にいるすべての子供たちから社会へ向けた、必死のSOSだったのです。
「私が兄を救えたはずなのに…」サバイバーを苛む終わらない罪悪感
妹の言葉の端々から滲み出るのは、兄を止められなかった、あるいは同じ地獄を最後まで共にできなかったという、深い後悔と罪悪感――心理学でいう「サバイバーズ・ギルト(生存者の罪悪感)」です。忘れてはなりません。彼女自身もまた、この事件によって心に深い傷を負った、一人の被害者であり、サバイバーなのです。
関西テレビの別の報道は、妹が涙で言葉を詰まらせる間、山上被告は「時折、目元を抑えるしぐさもみられました」と伝えています(関西テレビ 11月18日)。言葉を交わさずとも、法廷という場で初めて共有された壮絶な過去。それは、いまだ断ち切ることのできない兄妹の絆と、互いへの複雑な感情を静かに物語っていました。
“異常な個人の犯罪”で終わらせるな。この証言から社会が学ぶべきこと
山上被告の妹が、自らの身を引き裂くような過去を公の場で語るには、どれほどの勇気が必要だったことでしょう。私たちは、この勇気を、この涙を決して無駄にしてはなりません。彼女の証言は、私たち一人ひとりに重い問いを突きつけています。
- 私たちは、「信教の自由」という名の聖域で行われる児童虐待を、これからも見過ごし続けるのか?
- 社会の片隅で声を殺している子供たちに、手を差し伸べる具体的な方法を、本気で考えられているか?
- 「自己責任」という冷たい言葉で、セーフティネットからこぼれ落ちる人々を、再び突き放すのか?
この事件を「特異な思想を持つ個人の凶行」として片付け、忘れてしまうのは簡単です。しかし、それでは何も解決しません。山上被告の妹の証言を、私たち社会全体の“宿題”として受け止める。第二、第三の悲劇を防ぐために何ができるのかを、自分のこととして考える。この問いにどう答えるか、その責任は、今この記事を読んでいるあなた自身にもあるのです。


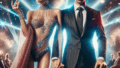
コメント