この記事のポイント
- なぜ高市早苗は大逆転できたのか?その裏には、キングメーカー・麻生太郎の土壇場での「翻意」があった。
- 麻生氏が小泉進次郎を見限った最大の理由は、政策ではなく、平将明氏や木原誠二氏といった小泉氏側近への強烈な“嫌悪感”だった。
- 「麻生の影響力は低下した」という平氏の一言が麻生の逆鱗に触れ、「人事は麻生さんにお任せします」という高市陣営の囁きが勝敗を決定づけた。
- この一件は、日本のトップが政策そっちのけの人間関係、そして“貸し借り”と“仁義”の世界で決まるという、不都合な真実を暴き出した。
「また麻生か…」高市新総裁、奇跡の大逆転劇。その裏で囁かれる“キングメーカー”の冷徹な計算とは?
なぜ、大本命のはずだった小泉進次郎は敗れたのか? なぜ、下馬評を覆し、高市早苗は総理の座を手にしたのか?――この問いに、多くの人が首を傾げたはずです。党員・党友票での予想外の健闘もさることながら、決選投票で議員票が雪崩を打って高市氏に流れた光景は、まさに「奇跡」以外の何物でもありませんでした。
しかし、永田町に奇跡などありません。そこにあるのは、常に冷徹な計算と、生々しい人間関係だけ。そして今回の逆転劇、そのすべての答えは、自民党に君臨する一人の“キングメーカー”の胸の内にありました。そう、自民党最高顧問・麻生太郎、その人です。
国家の未来を左右する高尚な政策論争? いいえ、違います。麻生が最後に天秤を動かしたその理由は、もっとドロドロとした、人間の“好き嫌い”と“プライド”の世界だったのです。この記事で、日本の政治を今なお支配する「昭和の妖怪」たちの恐るべき正体が見えてくるはずです。
引き金は「あの男」の一言。麻生太郎を激怒させた“気に食わない”奴らのリスト
この不可解な政局の裏側を、元日本テレビ政治部でジャーナリストの青山和弘氏が、あるテレビ番組で生々しく暴露しています。驚くべきことに、麻生氏は当初「小泉さんでもいいんじゃないか」と、容認する姿勢だったというのです。では、何が彼をそこまで変心させたのか?
一番麻生さんが心変わりした理由は、小泉さんの周辺にいる人たちがどうも気にいらない(ということ)。平(将明)デジタル大臣が『麻生さんの影響力が下がった』って、はっきり言って。これ、犬猿の仲。木原誠二さんとか、あと麻生派を出ていった人が小泉さんんの周りをがっちり固めている。
どういうことか? つまり、麻生太郎が最後に下した決断は、小泉進次郎という政治家そのものの評価ではなく、彼の周りをうろつく「気に食わない連中」への強烈な拒否反応だったのです。具体的に、彼の怒りのスイッチを押してしまった人物たちを見ていきましょう。
【地雷その1】「麻生さんの影響力は下がった」――キングメーカーのプライドを粉砕した禁断の言葉
決定的な引き金を引いたのは、小泉陣営で選対本部長を務めていた平将明デジタル大臣でした。彼はこともあろうに記者会見の場で、麻生氏を指して「以前ほど影響力があるように思えない」と公言してしまったのです。
想像してみてください。長年、日本の政界を裏で操り、総理大臣を何人も生み出してきたと自負する男が、公の場で「お前の時代は終わった」と宣告されたも同然の状況を。これは単なる失言ではありません。キングメーカー・麻生太郎の存在価値そのものへの、正面からの挑戦状でした。この一言が、麻生氏の中で「小泉だけは、絶対に勝たせるわけにはいかない」という暗い炎を燃え上がらせたのです。
【地雷その2】派閥を捨てた「裏切り者」たちへの“怨念”
もう一つの地雷は、小泉氏のブレーンである木原誠二元官房副長官らの存在でした。青山氏の指摘通り、彼の周りには、かつて麻生派に所属しながらも、麻生氏の元を去っていった人物たちが集まっていました。
派閥の論理が絶対である自民党の古い体質において、これは「仁義に反する」最大のタブー。麻生氏からすれば、彼らは自分を裏切った人間であり、そんな連中が権力の中枢に座ることなど、到底許せるはずがありません。小泉政権の誕生は、すなわち「裏切り者」たちの復権を意味する。そのシナリオだけは、何としてでも阻止しなければならなかったのです。
これは単なる“好き嫌い”ではない。麻生太郎を動かす「権力」と「仁義」の絶対法則
「なんだ、結局はただの好き嫌いか」――そう結論づけるのは早計です。彼の行動の裏には、自らの影響力を死守するための老獪な権力維持術と、自民党という組織に深く根付いた「昭和の掟」とも言うべき、2つの絶対法則が存在するのです。
法則①:「俺をナメるな」――存在価値を賭けたキングメーカーの“粛清”
麻生氏の今回の動きは、自身の党内でのポジション、つまり「キングメーカー」としての絶対的な権威を守るための、極めて合理的な“粛清”でした。平氏の「影響力低下」発言は、その権威への挑戦です。これを黙って見過ごせば、足元を見られ、自身の求心力は確実に失墜する。だからこそ、挑戦者は徹底的に叩き潰す必要があったのです。
彼の執念深さは、石破茂氏との長年の確執からも見て取れます。過去の報道が示すように、一度「敵」と認定した相手への攻撃は苛烈を極めます。今回の小泉陣営への仕打ちは、まさに麻生氏ならではの行動原理が発動した結果と言えるでしょう。
「麻生太郎が高市早苗を支持した理由」。その本質は、自らの権威を脅かす者を排除し、意のままになる人間をトップに据えることで、キングメーカーとしての君臨を世に知らしめる――そんな冷酷な権力闘争の論理に他なりません。
法則②:「裏切り者は許さない」――“言うことを聞く人間”だけが生き残る世界
麻生派は今や党内唯一の派閥であり、その結束力こそが麻生氏の影響力の源泉です。しかし思い出してください。かつて彼は、自派閥のホープだった河野太郎氏ですら、総裁選で全力で推すことはしませんでした(SmartFLASHの報道)。これは、たとえ身内であっても、自分のコントロールから外れる可能性のある人間は決してトップにしない、という彼の鉄の掟を示しています。
平氏や木原氏といった面々は、麻生氏の目には「コントロール不能で、言うことを聞かない連中」と映ったはずです。彼らが主導する政権が生まれれば、自分の影響力が削がれるのは火を見るより明らか。ならば、恩を売ることで完全にコントロール下に置ける高市氏を担ぐ方が、よほど合理的。それが彼の出した結論でした。
勝敗を決した“悪魔の囁き”――高市陣営が差し出した「人事権」という切り札
小泉陣営が、知ってか知らずか、キングメーカーへの“仁義”を欠き、慢心していたその裏で、高市陣営は実に狡猾な一手を用意していました。
その決定打こそ、ジャーナリスト青山氏が明かした「『人事は麻生さんにお任せしますから』というメッセージ」です。これは、総理大臣が持つ最大の権力「人事権」を、事実上、麻生氏に譲渡するという驚くべき提案でした。権力と実利を何よりも重んじる老獪な政治家にとって、これほど甘美な響きを持つ言葉があったでしょうか。
この一言で、麻生氏は「高市を担ぐメリット」を完全に理解しました。それは、高市政権を誕生させ、その後の組閣や党役員人事をも自分の一存で動かせるという、絶対的な影響力の確約だったのです。
悪魔の囁きを受け取った麻生氏の動きは、電光石火でした。報道によれば、彼は決選投票直前、派閥議員に直接電話をかけ、こう告げたといいます。「党員(票)に合わせろよ。高市で行くから、言うなよ」。この鶴の一声で、麻生派の票は一気に高市氏へと流れ込み、歴史的な大逆転劇が完成したのです。周辺が「ばくちに勝ったな」とほくそ笑んだというのも、頷ける話です。
結局、政治は「感情」で動くのか? この政局から私たちが学ぶべきこと
今回の総裁選は、政策論争という建前とは裏腹に、一人のキングメーカーの“感情”と“計算”が、いとも簡単に日本のリーダーを決めてしまうという現実を、私たちに見せつけました。この茶番劇とも言える結果は、今後の日本に何をもたらすのでしょうか。
高市政権は「麻生の操り人形」で終わるのか?
高市新総裁が誕生したのは、麻生氏の絶大な支援があったからに他なりません。当然、今後の政権運営には「麻生の意向」が影を落とすことになり、一部ではすでに「麻生傀儡政権」だと揶揄する声も聞こえてきます(Newtalk新聞の視点)。彼女がキングメーカーの呪縛を断ち切り、真のリーダーシップを発揮できるのか。その手腕と自立性が、いきなり問われています。
証明された“キングメーカー”の健在。麻生支配はまだ続く
皮肉なことに、「影響力が下がった」という一言が、麻生太郎の影響力が全く衰えていないことを、これ以上ない形で証明してしまいました。彼に逆らう者がどうなるか、党内の誰もがその恐ろしさを再認識したはずです。今後も自民党のパワーバランスは、この老獪なキングメーカーの掌の上で動き続けることになるでしょう。
敗れ去った小泉進次郎に未来はあるか? 問われる“中身のなさ”
一方、大本命から一転、惨めな敗北を喫した小泉進次郎氏の未来は、決して明るくありません。メディアからは、決選投票前の演説が「感謝と思い出話」に終始したと酷評され、その致命的な「中身のなさ」が露呈しました。人気やイメージというメッキが剥がれた今、彼が真の政治家として再起できるかどうかは、国家のビジョンを自らの言葉で語れるかにかかっています。
結局のところ、麻生太郎が高市早苗を支持した理由を突き詰めていくと、日本の政治がいかにウェットで、非論理的な世界であるかという現実にぶつかります。政策や理念よりも、個人のプライドや派閥の論理、人間関係の貸し借りが優先される世界。私たちが次にニュースを見るとき、その裏側でどのような人間ドラマが繰り広げられているのか、少し想像してみてください。きっと、退屈な政治ニュースが、途端に生々しく、面白い物語に見えてくるはずです。

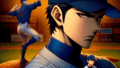
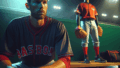
コメント