これは他人事ではない。広島で起きた悲劇と『ブラック部活』の現実
「生理が止まれば、それで正解」。
広島県のスポーツ強豪校で、顧問の男性教員が女子部員にこう言い放ちました。この言葉を信じた18歳の女性は、過酷な減量を強いられ、体重32kg、体脂肪率は測定不能に。摂食障害と無月経に陥り、競技人生を断たれました。彼女は当時を振り返り、「洗脳状態だった」と語ります。
1日の摂取カロリーは500kcal。これは10代女性の必要量の4分の1以下です。恋愛は「幸せホルモンが出て太るから」と禁止され、部室では毎日体重測定。少しでも増えれば、顧問から「やる気あるんか」と罵声を浴びせられました。
これは、遠いどこかの特別な話ではありません。勝利という名の麻薬に蝕まれ、子どもの心と体を犠牲にする「ブラック部活」は、日本の至る所に潜んでいます。あなたの、そしてあなたの大切な子どもの周りは、本当に大丈夫でしょうか? この記事は、悲劇を繰り返さないために、すべての中高生、保護者、そして指導者に読んでほしいと願っています。
なぜ逃げられない?指導者が生徒を支配する『洗脳』の心理メカニズム
「先生が言うことは絶対」「先生に認められたかった」。被害者の女性がそう思い込んでしまったのは、なぜでしょうか。それは、決して彼女が弱かったからではありません。ブラック部活の現場には、生徒を心理的に支配し、正常な判断力を奪う巧妙な「罠」が仕掛けられています。
第一に、「権威への服従心理」です。「実績のある指導者」という肩書きは、生徒や保護者にとって絶対的なものに映ります。特に思春期の生徒にとって、尊敬する大人からの承認欲求は非常に強いものです。指導者はその心理を巧みに利用し、「お前のためを思って言っているんだ」という言葉で、非科学的で危険な指導を正当化します。生徒は「指導を疑う自分がおかしいのかもしれない」と、自分自身を責め始めるのです。
第二に、「閉鎖的な環境」が生む異常な常識です。部活動は、学校や家庭とは切り離された特殊な空間になりがちです。その中で、「生理が止まるのは頑張っている証拠」「水を飲むな」「先輩の言うことは絶対」といった独自のルールが「常識」としてまかり通ります。外部からの情報が遮断されるため、部員たちは自分たちの置かれた状況が異常であることに気づきにくくなります。元記事で「女子部員のほとんどが無月経だった」という事実は、まさにこの異常な常識が部全体に蔓延していたことを示しています。
第三に、「同調圧力」という見えない鎖です。「みんな我慢しているんだから、自分も頑張らなきゃ」。仲間からの冷たい視線や、「和を乱すな」という無言の圧力は、生徒が「NO」と言う勇気を奪います。特に、体重測定の結果が公開されるような環境では、仲間は連帯する対象ではなく、互いを監視し、追い詰める存在へと変貌してしまうのです。この巧妙な支配の構造は、近年問題視されている「グルーミング(手なずけ)」とも共通する危険性をはらんでいます。
これらの心理的な罠が幾重にも張り巡らされることで、生徒は心身ともに追い詰められ、まるでカルト集団のような「洗脳状態」に陥ってしまうのです。
『無月経は正解』が奪う未来 ― 10代アスリートの身体を蝕む深刻なリスク
「生理が止まる=頑張っている証拠」。これは、指導者が使う最も危険で、無知な言葉の一つです。この言葉の裏には、若いアスリートの未来を根こそぎ奪いかねない、深刻な医学的リスクが隠されています。
専門家の間では「女性アスリートの三主徴(Female Athlete Triad)」という言葉が警鐘を鳴らされています。これは、以下の3つの症状が互いに関連し合って発生する健康問題です。
- 利用可能エネルギー不足:食事からの摂取エネルギーが、運動による消費エネルギーに追いつかない状態。過度な減量や食事制限が主な原因です。
- 視床下部性無月経:エネルギー不足により、脳からの女性ホルモンの分泌が止まり、月経が停止する状態。
- 骨粗鬆症:女性ホルモン(エストロゲン)の欠乏により、骨がもろくなる状態。
順天堂大学の研究によれば、激しいトレーニングを行う女性アスリートは、これらのリスクに晒されやすいことが指摘されています。
激しいトレーニンクゃを継続的に行う女性アスリートは、i(摂食障害の有無に関わらない) 利用できるエネルギー不足」、またそれに伴う「視床下部性無月経」、「骨粗懸症」のリスクがあり…
「生理が止まる」ということは、単に月経が来ないというだけではありません。それは、体が「生命維持を優先するため、生殖機能を停止します」という悲鳴を上げているサインなのです。この状態が続くと、何が起きるのでしょうか。
まず、骨がスカスカになります。女性ホルモンは骨の健康を維持するために不可欠です。無月経によるホルモン欠乏は、骨密度を急激に低下させます。通常、女性の骨量は20歳頃にピークを迎えますが、10代で無月経を放置すると、ピークに達する前に骨量が減少し、若くして高齢者のような骨粗鬆症になる危険性があります。その結果、競技中のわずかな衝撃で疲労骨折を起こしやすくなり、選手生命を縮めることになります。
無月経による低エストロゲン状態が続くことで,骨密度が減少して骨粗鬆症や疲労骨折のリスクとなります。通常、女性は20歳頃に最大骨量を獲得し,その後の…
さらに深刻なのは、将来の健康への影響です。10代で受けた骨へのダメージは、一生涯ついて回ります。そして、長期間の無月経は、将来の不妊の原因となる可能性も指摘されています。目先の勝利のために、指導者は生徒から「健康に競技を続ける権利」と「将来母親になる可能性」という、何物にも代えがたい未来を奪っているのです。「無月経は正解」などでは断じてなく、選手の未来を破壊する「不正解」以外の何物でもありません。
見て見ぬふりをする大人たち ― ブラック部活がなくならない構造的問題
元記事の女性は、「校長や保護者、教育委員会も意見できない空気だった」と証言しています。なぜ、これほど異常な指導がまかり通り、周りの大人たちは止められなかったのでしょうか。そこには、個人の資質の問題だけでなく、日本のスポーツ界や教育現場に根深く存在する構造的な問題があります。
第一に、絶対的な「勝利至上主義」の存在です。大会で結果を出すことが、指導者の評価、学校の名声、さらには地域の期待に直結します。この「勝利」という絶対的な目標の前では、生徒の心身の健康は二の次にされがちです。「あの先生は厳しいが、勝たせてくれる」という評価が、体罰やハラスメントを容認する土壌を生み出しているのです。
第二に、部活動が「聖域化」し、指導者の権力が絶対化している問題です。特に、外部から招聘された指導者や、長年の実績を持つ顧問の場合、その指導法はブラックボックス化し、学校側も口出しできないケースが少なくありません。保護者も「素人が口を出すべきではない」「子どもが目をつけられたら困る」と萎縮してしまい、結果的に指導者の独裁を許してしまいます。
第三に、OB・OGや地域社会からの同調圧力です。「自分たちの時代はもっと厳しかった」「厳しくなければ強くならない」といった精神論が、いまだに根強く残っています。こうした声が、指導方法の改善を試みようとする学校や新しい指導者の動きを妨げる障壁となることもあります。
これらの問題が複雑に絡み合い、「おかしい」と感じながらも誰も声を上げられない、あるいは声を上げてもかき消されてしまうという構造が生まれます。生徒一人がこの巨大な構造に立ち向かうのは、あまりにも困難です。問題の根絶には、指導者個人の責任を問うだけでなく、この歪んだ構造そのものにメスを入れる必要があります。
今すぐできること ― 我が子と自分を『ブラック部活』から守るための具体的なアクション
もし、あなたやあなたの子どもが「この部活、何かおかしいかも」と感じたら、決して一人で抱え込まないでください。状況を客観的に判断し、自分を守るために、今すぐできる具体的なアクションがあります。
「熱心な指導」と「違法なハラスメント」の境界線チェックリスト
「厳しいけれど、愛のムチだ」という言葉に騙されてはいけません。指導とハラスメントには明確な境界線があります。以下のリストに当てはまるものがないか、冷静にチェックしてみてください。
- 人格否定:「お前は才能がない」「いてもいなくても同じ」など、存在を否定する言葉を言われる。
- 身体的暴力:殴る、蹴る、物を投げつけるなどの直接的な暴力。
- 過度な練習:スポーツ庁の指針(週2日以上の休養日)を無視した、長時間の拘束や練習。
- 非科学的な指導:水分補給の禁止、うさぎ跳びの強制、非科学的な減量指導など。
- プライベートへの過剰な干渉:恋愛の禁止、スマートフォンの使用制限、交友関係への口出しなど。
- 集団での無視や仲間外れ:指導者が特定の生徒を無視したり、他の部員に同調するよう仕向けたりする。
- 相対的な評価:「〇〇はできているのに、なぜお前はできないんだ」と、他者と比較して貶める。
一つでも当てはまれば、それは「熱心な指導」ではなく、心身を傷つける「ハラスメント」の可能性が非常に高いです。それは教育ではなく、単なる暴力です。
自分を守るための3つのステップ
「おかしい」と感じたら、次の3つのステップで行動しましょう。
- STEP1: 証拠を集める
「言った」「言わない」の水掛け論を避けるため、客観的な証拠が重要です。- 日記やメモ:いつ、どこで、誰に、何を言われたか、何をされたか、その時の気持ちを具体的に記録します。日付を入れることが重要です。
- 録音・録画:指導者との会話を、スマートフォンのボイスレコーダー機能などで録音することも有効な手段です。(ただし、使用方法には注意が必要です)
- 写真:怪我をした場合は、日付がわかるように写真を撮っておきましょう。
- メールやSNSの保存:指導者からのメッセージはスクリーンショットなどで保存しておきます。
- STEP2: 信頼できる大人に相談する
一人で戦おうとしないでください。必ず味方になってくれる大人がいます。- 保護者:まずは一番身近な保護者に相談しましょう。現状を正直に話すことが第一歩です。
- 学校内の相談相手:顧問以外の、信頼できる先生に相談しましょう。養護教諭(保健室の先生)やスクールカウンセラーは、守秘義務があり、専門的な視点からアドバイスをくれます。
- 学校の管理職:教頭や校長に相談することも一つの手です。ただし、学校側が問題を隠そうとする可能性も念頭に置きましょう。
- STEP3: 外部の専門窓口に助けを求める
学校内で解決が難しい場合は、ためらわずに外部の窓口に相談してください。匿名で相談できる場所もあります。- 日本スポーツ振興センター(JSC) スポーツにおける暴力・ハラスメント等相談窓口
アスリートや指導者、保護者からの相談を受け付けています。JSPOでは、スポーツ現場における暴力行為等に関する相談に対応するため、スポーツにおける暴力行為等相談窓口を設置しています。
- 24時間子供SOSダイヤル(文部科学省)
いじめやその他の悩みについて、24時間いつでも相談できます。電話番号:0120-0-78310いじめやそのほかのSOSを、24時間相談できます。 電話番号:0120-0-78310(なやみ言おう)
困ったときは相談しようより引用
- その他、各自治体の教育委員会や人権相談窓口
お住まいの地域の相談窓口も必ずあります。以下の資料も参考にしてください。スポーツにおける暴力・ハラスメント等相談窓口一覧のご案内
- 日本スポーツ振興センター(JSC) スポーツにおける暴力・ハラスメント等相談窓口
一番大切なのは、「逃げることは、負けではない」と知ることです。心と体を壊してまで、続けるべき部活動など一つもありません。あなたの未来を守ること以上に優先されるべきものはないのです。
結論:スポーツの本当の価値とは何か。勝利よりも大切なものを守るために
スポーツを通して、何を学ぶべきなのでしょうか。それは、勝利という結果だけではありません。フェアプレーの精神、仲間と協力する喜び、目標に向かって努力する尊さ、そして何より、心と体の健全な成長です。
海外、特に欧米のユーススポーツの現場では、「勝利至上主義」ではなく、「楽しむこと(FUN)」や「選手の長期的な育成(Long-Term Athlete Development)」が重視されています。子どもたちがスポーツを生涯愛し続けられるように、目先の勝利のために燃え尽きさせたり、心身を傷つけたりする指導は厳しく戒められています。
日本の部活動も、変わらなければなりません。指導者は、勝利への最短距離を求めるのではなく、一人ひとりの生徒が人として成長するための伴走者であるべきです。学校や教育委員会は、指導者にすべてを丸投げするのではなく、その指導が適切かどうかをチェックし、サポートする体制を築く責任があります。
そして、私たち一人ひとりが、この問題に関心を持つことが何よりも重要です。この記事を読んで、「ひどい話だ」で終わらせるのではなく、自分の周りを見渡し、おかしなことには「おかしい」と声を上げる。その小さな勇気の連鎖が、未来のアスリートたちを救う大きな力になります。勝利よりも大切なものを守るために、今、私たちに何ができるのか。その問いから、変化は始まります。

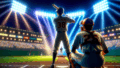

コメント