「故人に対する誹謗中傷は今も止みません」――。
もし、亡くなったあなたの大切な人が、事実無根の中傷に晒され続けたらどうしますか?その声なき声に代わり、あなたは真実を叫ぶことができるでしょうか。
2025年8月8日、一つの悲痛な決断が世に示されました。兵庫県の元県議会議員、故・竹内英明氏の妻が、NHK党の立花孝志党首を名誉毀損の疑いで刑事告訴したのです。これは、ただの政治的な対立ではありません。「夫の尊厳を守りたい」――その一心で、深い悲しみと恐怖を乗り越えて表舞台に立った一人の女性の、魂の叫びから始まる物語です。この記事では、一個人の悲しみを通して、私たちの社会が抱える言葉の暴力という大きな問題を考えます。
【事件の全貌】「夫の尊厳を守りたい」- 妻が立花孝志氏を刑事告訴した経緯
この物語の中心にいるのは、竹内英明・元兵庫県議。同僚議員から「正義感が強く調査能力が高い」「県政の財政問題に鋭く切り込んだ」と評され、多くの人々の悩みや相談に親身に応じていた人物でした。5期にわたり県政に尽力した彼は、まさに「24時間、仕事をやっていたような夫でした」と妻が語る通りの人物だったのです。(出典: 毎日新聞)
しかし、彼の人生は昨年、突然の転換点を迎えます。2024年11月の知事選投開票日の翌日、「一身上の都合」を理由に議員を辞職。そして2025年1月、彼は自ら命を絶ったとみられています。
残された家族の悲しみが癒える間もない中、追い打ちをかけるように浴びせられたのが、立花孝志氏による言葉の刃でした。そして2025年8月8日、沈黙を破り、妻は記者会見の席に立ちました。
「表に出ることで再び批判にさらされる、攻撃されることを恐れる気持ちが今も私の頭を支配しているが、私は夫の尊厳を守りたい。夫は『黒幕』ではありませんし、誰かを貶めるようなことはしていません。夫の代わりに声をあげられるのは私しかいない」
恐怖を乗り越えての刑事告訴。それは、亡き夫への最後の愛であり、守るべき尊厳のための、あまりにも切実な戦いの始まりでした。(出典: 毎日新聞)
一体何が語られたのか?問題となった立花氏の「ウソの発言」とされる内容
一体、どのような言葉が、遺族をここまで追い詰めたのでしょうか。告訴状に記された立花氏の発言は、あまりに衝撃的です。
1.街頭演説での発言(2024年12月)
立花氏は、自身が立候補していた泉大津市長選挙の街頭演説で、聴衆に対し、当時まだ存命だった竹内元県議についてこう断言しました。
「(竹内元県議が)警察の取り調べを受けているのは間違いない」
2.ライブ配信での発言(2025年1月、竹内氏死亡直後)
さらに、竹内氏の訃報が報じられた直後、立花氏は自身の動画投稿サイトでのライブ配信で、視聴者に向けてこう語りました。
「竹内元県会議員、どうも明日逮捕される予定だったそうです」「本人は逮捕される前にも自ら命を絶ったのではないかと。お亡くなりになったといっても自業自得であったとしか言いようがない」
これらの発言は、あたかも警察の内部情報を得たかのような口ぶりで語られ、ネット上で瞬く間に拡散されました。しかし、この発言には公的な機関が明確に「NO」を突きつけています。
2025年1月、兵庫県議会の委員会で、当時の村井紀之・兵庫県警本部長は「元議員について容疑者として任意の調べをしたことはなく、ましてや逮捕するといったような話は全くない。全くの事実無根だ」と、極めて異例の形で、発言内容を完全に否定したのです。(出典: NHK NEWS WEB)
警察トップが「事実無根」と断じた言葉が、なぜ公の場で語られ、一人の人間の名誉を死してなお傷つけなければならなかったのか。この問いは、次の法的、そして社会的な問題へと繋がっていきます。
故人への名誉棄損は罪になる?刑事告訴の行方と「死者の名誉毀損」の法的ハードル
「亡くなった人への名誉毀損は、罪に問えるのか?」これは多くの人が抱く疑問でしょう。答えは「YES」ですが、そこには高いハードルが存在します。
日本の刑法第230条は名誉毀損罪を定めており、これは死者に対しても適用され得ます。しかし、生きている人への名誉毀損が「事実の有無にかかわらず」成立するのに対し、死者の名誉毀損罪が成立するのは「虚偽の事実を摘示した場合」に限定されます。(出典: 産経新聞)
今回のケースをこの法律に照らし合わせてみましょう。
- 「虚偽の事実」にあたるか?
立花氏の「警察の調べを受けている」「逮捕予定だった」という発言に対し、兵庫県警トップが「全くの事実無根」と公式に否定しています。この事実は、立花氏の発言が「虚偽」であったと認定される上で、極めて強力な証拠となる可能性があります。 - 立証のハードル
検察が起訴に踏み切るためには、立花氏が「虚偽であると認識しながら、あえて発言した」という故意を立証する必要があります。捜査の焦点は、立花氏がどのような情報源を基に発言したのか、そしてその情報源の信憑性をどう評価していたのか、という点に集まるでしょう。
今回の刑事告訴は、この高い法的ハードルに挑むものです。その行方は、単に一個人の名誉回復にとどまらず、死者の尊厳を法がどこまで守れるのかという、社会に対する重要な問いかけでもあるのです。
なぜ繰り返されるのか?政治とネット誹謗中傷が交差する社会の闇
この事件を、一政治家の特異な言動として片付けることはできません。これは、現代社会が抱える根深い「闇」が、政治という領域で噴出したものと捉えるべきです。
1.注目が利益を生む「アテンション・エコノミー」の罠
現代は、人々の「注目(アテンション)」が経済的な価値を持つ時代です。SNSの「いいね」や動画の再生数は、直接的な収益や影響力に繋がります。この環境下では、正確さや倫理観よりも、いかに人々の耳目を集めるかが優先されがちです。過激で、断定的で、扇情的な言葉ほど、拡散されやすい。政治家がこのメカニズムを利用し、注目を集めるために過激な発言を繰り返す構図は、ネット社会の深刻な副作用と言えるでしょう。(参考: NHK「フィルターバブル」と「アテンションエコノミー」に注意)
2.信じたいものだけを信じる「フィルターバブル」現象
インターネットは、私たちを心地よい情報の泡(フィルターバブル)の中に閉じ込めることがあります。自分の思想や信条に合った情報ばかりが目に入るため、異なる意見や客観的な事実に触れる機会が減っていきます。立花氏の発言も、特定の支持者層にとっては、既存の不信感や陰謀論を補強する「心地よい真実」として受け入れられ、拡散と再生産が繰り返されてしまうのです。
3.「言葉の暴力」に対する社会の麻痺
ネット上では日々、誹謗中傷が溢れています。その奔流の中で、私たちは少しずつ、言葉の暴力に対して麻痺してはいないでしょうか。「どうせまたいつものことだ」と見過ごし、あるいはエンターテイメントとして消費してしまう。その無関心が、言葉のナイフを研ぎ澄ませ、誰かの心や尊厳を深く傷つける結果を招いているのかもしれません。
私たちにできること、そして社会が向かうべき場所
「夫の尊厳を守りたい」――。竹内氏の妻の言葉は、私たち一人ひとりの胸に突き刺さります。これは遠い世界の出来事ではありません。言葉が凶器となりうる社会で、私たちはどうすれば大切な人を、そして自分自身を守れるのでしょうか。
まず、情報の受け手として、一度立ち止まる勇気を持つこと。センセーショナルな見出しや断定的な物言いにすぐ飛びつくのではなく、「その根拠は何か?」「反対の意見はないか?」と自問する姿勢が求められます。
そして、社会全体として、政治家をはじめとする公人・インフルエンサーの発言責任を、より厳しく問うていく必要があります。表現の自由は尊重されるべきですが、それは他者の人権や尊厳を蹂躙する「無責任の自由」ではありません。今回の刑事告訴が司法の場でどう判断されるかを見守ることは、その第一歩です。
故・竹内英明氏がどのような思いで県政を見つめていたのか、今となっては確かめる術はありません。しかし、彼が人生をかけて守ろうとしたものがあったはずです。そして今、彼の妻が、自らの全てをかけて守ろうとしているのが「夫の尊厳」です。
この悲痛な訴えが、無責任な言論がまかり通る社会に一石を投じ、言葉の重みを誰もが再認識するきっかけとなることを、切に願います。

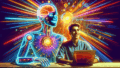
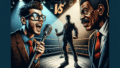
コメント