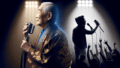「醜く奇妙な生き物」――北村晴男氏の発言が映す保守の現在地

日本保守党の北村晴男参院議員が、石破茂首相を「醜く奇妙な生き物」とX(旧ツイッター)に投稿した(時事通信 2024年10月25日配信 https://news.yahoo.co.jp/articles/91d23dffc89b39d8cfc6f6e85c242b2d7756e5a4)。多くのメディアが「暴言」と報じ、SNSでは非難が相次いだが、北村氏は「率直な感想」として撤回しない意向を示している。この一連の騒動を、単に政治家の品性の問題として片付ければ、その本質を見誤る。この言葉は感情の産物ではなく、計算された政治的メッセージだ。それは石破個人に向けられると同時に、現代日本の「保守」が直面する構造的な対立と、その中で選択される戦略を浮き彫りにしている。
「非人間化」による対話の拒絶
弁護士として言葉の力を熟知するはずの北村氏が、首相を人間ではない「生き物」と表現したことには、明確な政治的意図が読み取れる。これは、相手を対等な議論の対象から外し、理解不能で排除すべき「異物」として位置づける「非人間化」の手法である。
人間を動物や害虫に喩えるレトリックは、歴史を通じて特定の集団への憎悪を煽り、対話の可能性を根絶するために用いられてきた。過去のヘイトスピーチ問題が示すように、こうした言葉は社会の分断を深刻化させる。北村氏の発言は、石破首相の政策や理念を批判するのではなく、その存在自体を否定し、支持者に対して「あれは我々と同じ人間ではない」という強烈なシグナルを送るものだ。
北村氏は、選挙で敗北しても続投する姿勢を「首相の座にしがみついている」と断じ、それが「人柄」への評価、すなわち「生き物」という表現に繋がったと説明する。しかし、これは論点のすり替えに他ならない。政治姿勢への批判は、政策論争や政治倫理の文脈で展開されるべきであり、相手を人ならざるものとして貶める言葉を選ぶことは、健全な言論の放棄を意味する。
この問題を「国会の品位」という枠組みだけで捉えることにも限界がある。過去の判例では、議員の発言が懲罰対象となる「無礼の言葉」にあたるかは、発言の趣旨や目的を全体的に見て、批判に必要な限度を超えているかが問われる。北村氏の発言がその一線を越えていることは明らかだが、重要なのは「品位がない」と嘆くことではない。なぜ、このような非人間化の言葉が、一つの政治戦略として公然と採用されるに至ったのか、その力学をこそ問う必要がある。
日本保守党の生存戦略と「敵」の必要性
北村氏の過激な発言は、彼個人の資質の問題以上に、日本保守党という新興政党の生存戦略と深く結びついている。同党は、LGBT理解増進法への自民党の対応に不満を持つ層を主な支持基盤として結党された。彼らは既存の自民党を「リベラルに汚染され、本来の保守の姿を失った存在」とみなし、自らこそが「真の保守」であると規定している。
この純粋性を求めるアイデンティティを維持し、支持者を結束させるためには、常に「敵」と「裏切り者」を明確に設定し、攻撃し続けることが不可欠となる。その最大の標的こそ、石破茂という存在である。
作家の古谷経衡氏が指摘するように、石破氏は「岩盤保守」と呼ばれる層から長年にわたり強い反発を受けてきた。過去の歴史認識に関する発言や、安全保障政策に対する慎重な姿勢などがその理由とされる。特に、保守論壇で強い影響力を持っていた故・渡部昇一氏が、かつて石破氏を「国賊」とまで批判したことは、保守層内部に存在する石破氏への根深い不信感を象徴している。
日本保守党にとって、石破首相はまさに「偽物の保守」「自民党の堕落を象徴する存在」である。彼を「醜く奇妙な生き物」と罵倒することは、自民党との差異化を最も鋭く描き出し、支持者に対して「我々は、あのような『生き物』とは違う純粋な存在だ」と宣言する、効果的なパフォーマンスとなる。これは単なる政策批判ではなく、党のアイデンティティを確認し、支持層への忠誠を示す儀式なのだ。
古谷氏の分析によれば、日本保守党の誕生は「岩盤保守」の結束ではなく、むしろその内部での分裂と純化の動きの表れだという。安倍晋三元首相の死後、一枚岩と見られた保守層は、誰が「本流」かをめぐって分裂を始めた。日本保守党は、その中で最も純粋で、最も過激な層を掬い上げようとしている。そのためには、穏健な言葉や理性的な議論は足かせとなる。必要なのは、敵を名指しし、支持者の感情を昂らせる、シンプルで暴力的な言葉だ。「醜く奇妙な生き物」という言葉は、そのための最適な道具として選ばれたのである。
分断を映し出す鏡
この発言によって、日本の政治における一つの亀裂が可視化された。それは、石破政権と日本保守党の対立という単純な構図ではない。より根深い、「保守とは何か」をめぐる定義闘争であり、その闘争がもはや対話の余地なく、相手を排除する段階に入ったことの証左である。
日本保守党の戦略は、熱心な支持層の結束を強める一方で、穏健な保守層や無党派層からの支持を失うだろう。しかし、彼らの当面の目標は政権獲得ではなく、国政における確固たる橋頭堡の確保と、自民党内の保守派への影響力行使にある。そのためには、少数でも熱狂的な支持基盤を固めることが最優先される。過激な言説は、この言葉に共鳴する者だけを選別する「ふるい」として機能しているのだ。
我々がこの問題から引き出すべき教訓は、北村議員個人や日本保守党への道徳的な非難に留まらない。問われるべきは、なぜ、このような言葉が一定の求心力を持ってしまうのかという点だ。なぜ、私たちの社会は、複雑な現実を単純な敵味方に二分し、異質な他者を「生き物」と呼んで排除しようとする言説に、居場所を与えてしまうのか。
「醜く奇妙な生き物」という言葉は、鏡である。それは石破首相を映しているように見えて、実はそう叫ぶ人々の内面と、彼らが渇望する政治の姿を映し出している。そして同時に、そのような言説の増幅を許してしまっている、私たちの社会そのものを映し出す鏡でもある。
政治家が放つ言葉は、その社会の健康状態を示すバロメーターだ。対話と理性を重んじる言葉が交わされるのか、それとも断絶と憎悪を煽る言葉が飛び交うのか。北村氏が投じた言葉は、政治的対立が新たな局面に入ったことを示している。この「生き物」という言葉を生み出したのは、他ならぬ私たちの政治と社会に存在する歪みなのかもしれない。その冷厳な事実から目を背けてはならない。