この記事のポイント
- 短期滞在の外国人は日本の公的医療保険に加入できず「自由診療」扱いとなり、医療費は病院側が自由に価格を設定できます。
- 一部の病院は、通訳コストや医療費の未払いリスクを理由に、保険診療の基準(1点10円)を上回る価格(例:1点30円)を設定しており、これが高額請求の原因となります。
- この問題は「国籍による不当な差別」だとする患者側と、「合理的なリスク対価」だとする病院側で見解が対立しており、国の制度設計そのものに課題があることを浮き彫りにしています。
- 個人でできる最も重要な対策は、海外渡航時の「海外旅行保険への加入」と、日本に住む外国人の家族がいる場合の「在留資格と保険加入条件の確認」です。
導入:もしあなたの家族が海外で3倍の医療費を請求されたら?
「短期滞在で入国後、救急搬送された中国人女性が、日本人の3倍にあたる医療費を請求されたのは不当」——。2025年9月、こんなニュースが報じられ、波紋を広げています。
報道によると、亡くなった中国人女性の遺族は、国立循環器病研究センターに対し、日本人と同じ医療費との差額分450万円の支払い免除を求めて提訴に踏み切りました。女性側が「国籍を理由とした差別だ」と訴える一方、病院側は「価格設定は周辺の病院に合わせている」と主張しています。
このニュースを聞いて、「外国人だから仕方ない」「日本の医療制度を知らなかったのが悪い」と感じる人もいるかもしれません。しかし、少し視点を変えてみましょう。もしこれが、海外旅行中に病気になったあなたや、日本に暮らすあなたの外国人のパートナーや友人に起きた出来事だとしたらどうでしょうか?
この問題は、単なる一個人のトラブルではありません。外国人観光客や労働者が増え続ける日本で、誰にでも起こりうる医療格差の問題であり、日本の医療制度が抱える「穴」を浮き彫りにしています。この記事では、なぜこのような高額な医療費請求がまかり通ってしまうのか、その仕組みと背景を紐解き、私たち一人ひとりが自分と大切な人を守るために何ができるのかを徹底解説します。
なぜ3倍請求がまかり通る?日本の「自由診療」と医療保険の穴
なぜ同じ治療を受けたのに、国籍が違うだけで請求額が3倍にもなるのでしょうか。その謎を解くカギは、日本の公的医療保険制度と、そこからこぼれ落ちた人々が直面する「自由診療」という仕組みにあります。
日本の医療費の基本ルール「1点=10円」の国民皆保険
まず、日本の医療制度の根幹を理解しましょう。日本は「国民皆保険制度」を採用しており、原則としてすべての国民が公的医療保険(健康保険や国民健康保険など)に加入しています。
私たちが病院で保険証を提示すると、医療費の自己負担は年齢や所得に応じて原則1〜3割で済みます。残りの7〜9割は、私たちが支払う保険料や税金で賄われる保険から支払われます。
このとき、医療費の計算には全国共通のルールがあります。それは、「診療報酬点数」というものです。一つひとつの医療行為(診察、検査、手術など)に国が定めた点数が決められており、その合計点数に「1点=10円」を掛けて医療費が算出されます。日本医師会のウェブサイトでも解説されている通り、この「1点10円」という単価は、保険診療である限り、日本のどこにいても変わりません。
- 保険診療の計算式: 診療報酬点数 × 10円 = 総医療費 (このうち1〜3割を自己負担)
保険が使えない「自由診療」という世界
しかし、この「1点10円」のルールが適用されない世界があります。それが「自由診療」です。
自由診療とは、公的医療保険が適用されない医療サービスのことで、美容整形や一部の先進医療、そして公的医療保険に加入していない人が受ける医療などがこれにあたります。
自由診療の最大の特徴は、医療費を病院が自由に設定できることです。国が定めた価格はなく、まさに「時価」。治療にかかる費用は、保険の助けがないため全額自己負担となります。SBI損保のがん保険の解説ページでも指摘されているように、同じ治療でも自由診療になると自己負担額が跳ね上がることがあります。
今回のケースで、病院側は診療報酬を「1点30円」で計算しました。これは、保険診療の3倍の単価です。これが「3倍請求」の正体です。
- 自由診療の計算式(今回のケース): 診療報酬点数 × 30円 = 総医療費 (全額自己負担)
短期滞在外国人が陥る「保険の穴」
では、なぜ提訴した中国人女性は公的医療保険に加入できなかったのでしょうか。
日本の法律では、外国人が国民健康保険に加入するには、原則として在留期間が3ヶ月を超える必要があります。今回の女性は、当初「短期滞在(90日)」の資格で来日しました。その後、コロナ禍で帰国できなくなり、国の特別措置で90日間の在留資格更新を繰り返していましたが、1回の在留期間が3ヶ月を超えなかったため、最後まで保険の加入資格を得られませんでした。
まさに、制度の「穴」に落ちてしまったのです。その結果、彼女は日本に滞在していながら「無保険」の状態となり、救急搬送された際には「自由診療」として扱われ、病院が独自に設定した高額な医療費を請求されることになりました。これは、外国人医療が抱える非常に深刻な問題点です。
病院側の言い分は?高額請求の背景にある「通訳」「未払い」という現実
「それにしても、3倍は高すぎる」「困っている人から高額請求するなんて」と感じるかもしれません。しかし、この問題を「病院=悪」という単純な構図で捉えるのは早計です。病院側が高額な価格設定をせざるを得ない、切実な経営上の課題も存在します。
統計データが示す「外国人医療の未払い問題」
病院側が主張する最大の理由の一つが、外国人患者による医療費の未払いリスクです。治療後に連絡が取れなくなったり、そのまま帰国してしまったりするケースが後を絶たず、その未払い分は病院の損失となります。
この問題は深刻で、日本経済新聞が報じた厚生労働省の2023年度調査によると、外国人患者を受け入れた病院の18.3%で診療費の未払いが発生しています。未払い額の最高は一件で1846万円にも上り、たった一件の未払いでも中小病院の経営を揺るがしかねないインパクトがあります。
外国人医療の問題を分析するウェブサイト「いまさらニュース」も指摘するように、後払いが基本の日本の医療文化と、その場で支払う文化を持つ国とのギャップも未払いを助長する一因となっています。
言葉の壁とコミュニケーションコスト
もう一つの大きな負担が、言語の壁です。命に関わる医療現場では、正確なコミュニケーションが不可欠です。症状を正しく伝え、治療方針を理解してもらうためには、専門知識を持った医療通訳が必要になる場面も少なくありません。
しかし、医療通訳の確保には多大なコストがかかります。多くの病院では、この通訳費用を別途請求せず、診療費に含めるか、あるいは持ち出しで対応しているのが現状です。元記事で厚労省の担当者が語っているように、「言葉の壁による負担など、必要経費を反映した算定」が、高額請求の背景にあるのです。
日本人より高い請求は珍しくない?
実は、無保険の外国人に対して、保険診療の基準(1点10円)を超える価格を設定している医療機関は決して少なくありません。
記事でも触れられている通り、厚生労働省の調査では、短期滞在の外国人への自由診療について、回答した医療機関の14%が1点10円を超えて請求していると答えています。その多くは1点20円〜30円で、今回のケースが突出して特殊なわけではないことが分かります。
病院側からすれば、これらの価格設定は、日本人患者と比べて余分にかかるコストやリスクを埋め合わせるための、苦渋の経営判断という側面があるのです。
考察:これは「不当な差別」か、正当な「リスクへの対価」か?
この問題は、私たちの社会に根深い問いを投げかけます。同じ医療行為に対し、国籍を理由に異なる価格を設定することは、許されるのでしょうか。
原告側の主張:「国籍を理由とした不合理な差別」
原告である長女側の主張は明確です。
「法の下の平等」を保障する国連の自由権規約に反した不合理な差別だ
読売新聞オンラインより引用
この主張の根底には、「日本国内にいる人間は、国籍にかかわらず、生命や健康に関わる医療という基本的なサービスにおいて平等に扱われるべきだ」という考え方があります。支払能力があるにもかかわらず、国籍という本人の意思では変えられない属性のみを理由に3倍の対価を要求するのは、人権侵害にあたるという訴えです。
病院側の主張:「リスクに応じた合理的な価格設定」
一方、病院側はこれを「差別」ではなく、ビジネス上の「合理的な区別」だと捉えています。前述の通り、無保険の外国人患者には、日本人患者にはない「未払いリスク」と「コミュニケーションコスト」が付随します。これらの追加リスクやコストを価格に反映させるのは、民間企業として当然の経営判断である、という論理です。
実際にセンター側が「周辺の病院に合わせている」とコメントしているように、これは特定の病院の特殊な方針ではなく、外国人医療の現場で広く見られる「慣行」となっている可能性があります。
【もしもシミュレーション】海外の高額医療と日本の立ち位置
この問題を考える上で、海外の医療事情と比較してみましょう。例えば、国民皆保険制度がないアメリカでは、医療費は日本の比ではありません。
- もしあなたがアメリカ旅行中に盲腸で緊急手術を受けたら…
医療費は300万円〜500万円に達することも珍しくありません。骨折の治療で1000万円を超えたという事例もあります。適切な保険に加入していなければ、一瞬で破産しかねない金額です。
こうして見ると、日本の国民皆保険制度がいかに恵まれているかが分かります。しかし同時に、そのセーフティネットから一度こぼれ落ちて「自由診療」の世界に足を踏み入れた途端、海外と同様の厳しい現実が待ち受けていることも意味します。今回の事件は、日本の医療が持つ「光と影」の両面を象徴していると言えるでしょう。
【今すぐできる対策】自分と大切な人を守るために知っておくべきこと
この構造的な問題を前に、個人が無力だと感じる必要はありません。正しい知識を身につけ、備えることで、リスクを大幅に減らすことができます。
海外へ行く日本人へ:海外旅行保険は「命綱」
海外旅行や出張に行く予定のある日本人にとって、このニュースは他人事ではありません。渡航先であなたが「外国人」となり、高額な医療費を請求される側になる可能性があるからです。
海外旅行保険への加入は、もはや選択肢ではなく必須です。特に以下の点を確認しましょう。
- 治療・救援費用が無制限か: 医療費が高額な国(特にアメリカ、カナダ、スイスなど)へ行く場合は、「治療・救援費用」の補償額が無制限のプランを選ぶのが賢明です。
- キャッシュレス対応か: 現地で高額な医療費を立て替える必要がない「キャッシュレス・メディカルサービス」が付いているか確認しましょう。保険会社が直接病院に支払いをしてくれるため、非常に安心です。
- クレジットカード付帯保険の限界: クレジットカードに付帯する保険は、補償額が低かったり、利用条件(旅行代金をそのカードで支払うなど)があったりします。内容をよく確認し、不安な場合は別途保険に加入しましょう。
日本に住む外国人の家族がいる方へ:在留資格と保険加入のチェックリスト
日本で暮らす外国人や、そのご家族・パートナーがいる方は、以下の点を今すぐ確認してください。
- 在留カードの在留期間を確認する: 在留期間が3ヶ月を超えていれば、原則として国民健康保険に加入する義務があります。未加入の場合は、すぐに市区町村の役所で手続きをしてください。
- 在留期間が3ヶ月以下の場合: 観光や短期商用で来日している家族がいる場合、公的保険には加入できません。日本に来る前に、母国で海外旅行保険に必ず加入してもらうよう伝えてください。日本の民間保険会社が提供する、短期滞在者向けの医療保険もあります。
- 在留資格の更新時に注意する: 今回のケースのように、短期の在留資格を更新し続けている場合は特に注意が必要です。保険加入の条件を満たしているか、専門家(行政書士など)や役所に相談することをおすすめします。
まとめ:問われる日本の「おもてなし」と医療の未来
今回の提訴は、一組の家族と一つの病院との間の金銭トラブルにとどまりません。それは、日本の社会がこれからどのように外国人と向き合っていくのかという、より大きな問いを私たちに突きつけています。
インバウンド観光客は年間3000万人を超え、労働力不足を補うための外国人材の受け入れも拡大しています。そんな中、国籍によって受けられる医療に大きな格差が存在し、いざという時に高額な医療費が壁となって「受診控え」が起きてしまえば、個人の健康問題だけでなく、感染症の拡大など社会全体のリスクにも繋がりかねません。
記事で専門家が指摘するように、日本人との金額差をなくすための仕組みづくりが急務です。国籍や在留資格にかかわらず、誰もが安心して医療にアクセスできるセーフティネットをどう構築していくのか。真の「おもてなし」と「多文化共生社会」の実現に向け、日本の医療制度は大きな岐路に立たされています。今後の裁判の行方を、私たちは社会全体の課題として注視していく必要があります。
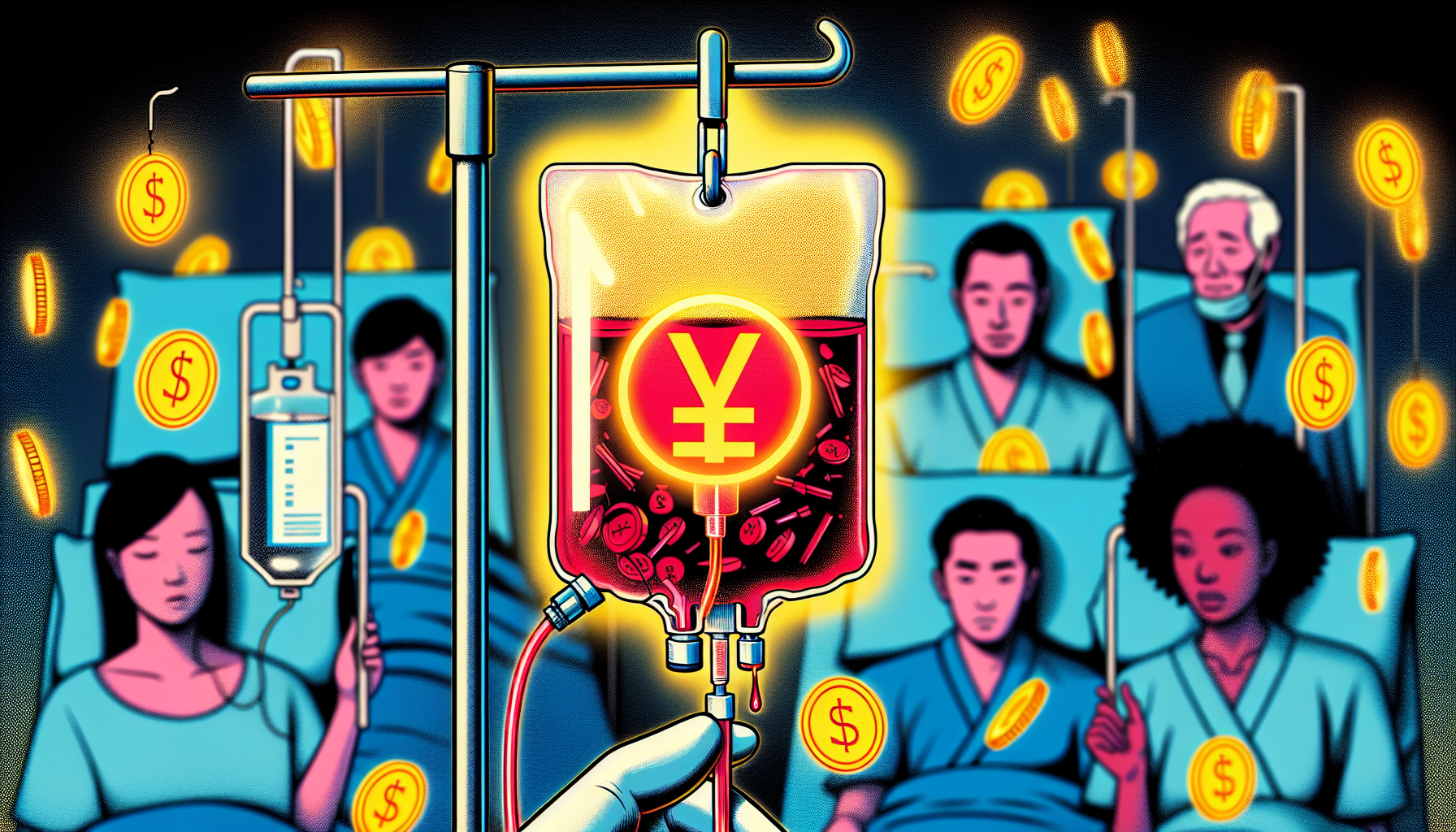


コメント