あなたの「イジり」は大丈夫?萩本欽一『24時間テレビ』炎上から学ぶ、世代を超えるコミュニケーション術
なぜ大御所・萩本欽一は「威圧的」と批判されたのか?
夏の風物詩ともいえる大型特別番組『24時間テレビ-愛は地球を救う-』(日本テレビ系)。今年も多くの感動と話題を呼んだ一方で、ある一幕がSNSを中心に大きな物議を醸しました。それは、お笑い界のレジェンド・萩本欽一さんの言動です。
番組内の人気企画「全日本仮装大賞」に登場した萩本さん。しかし、その司会進行ぶりに対して、視聴者からは厳しい声が相次ぎました。X(旧Twitter)には、以下のようなコメントが溢れたのです。
《欽ちゃんってこんなに偉そうな人だっけ?裏では厳しいと聞いたことはあるけど今日は表でも厳しかったね。これは楽しく見れないやつよ?》
《24時間テレビの仮装大賞の欽ちゃん、あれ大丈夫なの?そういう台本ならいいけど本人の意向であの回しなら放送事故では…》
プロ卓球選手の伊藤美誠さんやタレントのアンミカさんのコメントを「話が長い!」と遮る。総合司会の上田晋也さんへ厳しいツッコミを入れる。その一連の振る舞いは、多くの視聴者に「威圧的」「不快」という印象を与えました。昭和のテレビ界を牽引した「欽ちゃん」の言動が、なぜこれほどまでに炎上してしまったのでしょうか。本記事では、この出来事を深掘りし、その背景にある昭和と令和の価値観の断絶、そして私たちがそこから学ぶべき未来のコミュニケーションのあり方について考察していきます。
昭和の「愛あるイジり」と令和の「ハラスメント」の境界線
今回の炎上の核心を理解するためには、まず萩本欽一さんという芸人が築き上げてきた「芸風」の歴史を振り返る必要があります。
かつて「笑い」として成立していたコミュニケーション
萩本さんの真骨頂といえば、『スター誕生!』などで見せた巧みな「素人イジり」です。彼は、一般の参加者や無名のタレントの卵たちを、時に厳しく、時にユーモラスにイジることで、その人の個性や魅力を引き出し、大きな笑いを生み出してきました。このスタイルは、テレビというメディアが絶対的な力を持っていた時代背景と無関係ではありません。
当時の視聴者は、「欽ちゃんが言うことだから」「テレビの演出だから」という共通認識のもと、それを「愛あるイジり」として受け入れていました。出演者と萩本さんとの間には、たとえ画面上では厳しく見えても、一種の師弟関係のような信頼関係が暗黙のうちに存在していたのです。それは、強固な権威性と共有された文脈の上で成り立つ、特殊なコミュニケーションでした。
なぜ現代では「威圧的」と受け取られるのか
しかし、時代は大きく変わりました。令和の現代において、かつての「常識」は通用しなくなっています。
第一に、コンプライアンスと人権意識の高まりです。パワハラやモラハラといった言葉が社会に浸透し、個人の尊厳を傷つけるような言動に対して、世の中は非常に敏感になりました。たとえ「冗談」「イジり」の意図であったとしても、受け手が不快に感じれば、それはハラスメントと見なされる可能性があります。
今回の『24時間テレビ』での出来事を振り返ってみましょう。
審査員に感想を求められたアンミカ(53)がコメントすると、欽ちゃんが「長すぎ!」とツッコミ。プロ卓球選手の伊藤美誠(24)のコメントにも、欽ちゃんが彼女の話を途中で「話が長い!」とツッコミ。
これらのやり取りは、かつての『仮装大賞』であれば、「時間がない中でのテンポの良い進行」として成立したかもしれません。しかし、チャリティーという真摯なテーマを掲げる番組で、特に深い関係性のないゲストの言葉を一方的に遮る行為は、多くの視聴者にとって敬意を欠いた「威圧的な態度」と映ってしまったのです。
第二に、SNSの普及による視聴者の変化です。かつてテレビは一方的に情報を発信するメディアでしたが、今はSNSを通じて誰もがリアルタイムで感想や批判を発信できます。視聴者はもはや単なる「受け手」ではなく、番組を評価し、世論を形成する「参加者」へと変わりました。彼らの厳しい目は、少しでも時代錯誤な言動や不快な表現を見逃しません。
昭和の「愛あるイジり」が成立していたのは、出演者、制作者、視聴者の間に「これはお約束の笑いだ」という暗黙の了解があったからです。しかし、価値観が多様化した現代において、その「お約束」はもはや存在しません。信頼関係や文脈の共有がないまま、かつてのスタイルを貫くことは、意図せずして「ハラスメント」の境界線を越えてしまう危険性をはらんでいるのです。
これは単なる「老害」問題か?―テレビと視聴者の“すれ違い”
この一件を、単に「大御所芸人が時代についていけなくなった」という「老害」問題として片付けてしまうのは、あまりにも短絡的です。萩本さんを一方的に断罪する前に、この問題の背景にある、より構造的な課題に目を向ける必要があります。
自分の“城”で、いつも通りに振る舞った悲劇
萩本欽一さんは、1978年の第1回『24時間テレビ』で総合司会を務めた、まさに番組の「功労者」です。そして、彼が長年司会を務めてきた『仮装大賞』は、彼自身が作り上げたフォーマットであり、いわば彼の“城”でした。その中で、彼はいつも通りの「欽ちゃん」として、番組を盛り上げようとしただけなのかもしれません。
ここで私たちは、独自の視点として、萩本さんを「変化の速い時代に適応しきれなかった悲劇のヒーロー」として捉え直すことができます。長年、自分のスタイルで成功を収めてきた人物ほど、そのやり方を変えることは難しいものです。これは、テレビの世界に限った話ではありません。企業で長年功績を上げてきたベテラン社員が、新しい働き方や若い世代の価値観に戸惑う姿と重なります。「自分の常識が通用しなくなる」という恐怖は、実は誰もが直面しうる普遍的な課題なのです。
番組が抱える「感動と笑いのジレンマ」
さらに、問題を萩本さん個人に帰するのではなく、『24時間テレビ』という番組自体が抱える構造的なジレンマにも目を向けるべきです。実は同番組では、総合司会の上田晋也さんの「イジり」も、過去に幾度か物議を醸しています。チャリティーランナーへの厳しい檄や、企画の失敗に対するツッコミが「言い過ぎだ」と批判されたことがありました。
これは、『24時間テレビ』が「感動」と「笑い」という、時に相反する要素を両立させようとしていることに起因します。「愛は地球を救う」という崇高なテーマを掲げ、真摯なメッセージを発信する一方で、視聴者を飽きさせないためにバラエティ的な「笑い」の要素も取り入れなければならない。このジレンマの中で、特に昭和・平成のバラエティで主流だった「厳しいツッコミ」や「イジり」という手法は、番組の感動的なムードとは相性が悪く、視聴者に違和感や不快感を与えやすくなっているのです。
萩本さんの今回の言動は、この「感動と笑いのすれ違い」が最も顕著に現れた瞬間だったと言えるでしょう。テレビ局側も、大御所を起用するにあたって、現代の視聴者感覚とのズレをどう埋めるのか、その演出方法やサポート体制をより慎重に検討する必要があったのではないでしょうか。
私たちへの教訓:明日から職場で使える「世代を超えた」コミュニケーション術
萩本欽一さんの炎上は、決してテレビの中だけの対岸の火事ではありません。私たちの職場や家庭でも、同様の「世代間ギャップ」によるコミュニケーションのすれ違いは日常的に起こっています。上司の「良かれと思って」のイジりが部下を傷つけたり、若手社員の「当たり前」がベテランには理解されなかったり…。
この一件から、私たちは何を学び、自身の行動にどう活かせばよいのでしょうか。ここでは、明日からすぐに使える「世代を超えた」コミュニケーションのヒントを3つ提案します。
- 1. 「イジり」から「リスペクトベースの問いかけ」へ
相手のキャラクターを決めつけて笑いを取る「イジり」は、関係性ができていない相手にはハラスメントと受け取られかねません。代わりに、相手への敬意(リスペクト)をベースにした「問いかけ」を心がけましょう。「〇〇さんはユニークだね」と評価するのではなく、「〇〇さんは、この件についてどう思いますか?」と相手の意見や考えそのものに興味を示すのです。これにより、相手は尊重されていると感じ、安心して自分の言葉で話せるようになります。 - 2. 自分の「常識」を疑い、前提を共有する
「昔はこうだった」「普通はこうするものだ」という自分の物差しだけで物事を判断するのは危険です。自分の価値観が絶対ではないことを認め、「私たちの頃はこうだったんだけど、最近はどうなのかな?」と、まず自分の立ち位置を明らかにしましょう。その上で相手の考えを聞くことで、一方的な押し付けではなく、対等な対話が生まれます。 - 3. 心理的安全性を確保するリーダーシップ
特に管理職やリーダーの立場にある人は、チームの「心理的安全性」を高める責任があります。心理的安全性とは、誰もが萎縮することなく、自分の意見や気持ちを安心して表明できる状態のことです。萩本さんの現場で、羽鳥アナや大久保佳代子さんが気を遣い、空気がピリピリして見えたのは、この心理的安全性が損なわれていたからかもしれません。リーダーは、誰かの発言を遮ったり否定したりするのではなく、むしろ積極的に意見を促し、どんな発言も一度は受け止める姿勢を見せることが重要です。
これらのコミュニケーション術の根底にあるのは、相手をコントロールしようとするのではなく、相手を理解しようとする姿勢です。この小さな意識改革が、職場や家庭での無用な摩擦を減らし、より良い関係を築く第一歩となるはずです。
まとめ
『24時間テレビ』における萩本欽一さんの言動が巻き起こした炎上は、単なる一個人の問題ではありませんでした。それは、昭和という時代を象徴するコミュニケーションスタイルが、令和の価値観と衝突した瞬間であり、社会全体の意識が大きく変化していることの象徴です。
私たちは、この出来事を「世代間の断絶」と嘆くだけでなく、新しい関係性を築くためのチャンスと捉えるべきです。かつての「愛あるイジり」が通用しなくなった今、私たちに求められているのは、年齢や立場に関係なく、互いを一人の人間として尊重し、相手の言葉に真摯に耳を傾ける姿勢ではないでしょうか。
この記事を読んでくださったあなたが、明日から少しだけ、ご自身の周りの人とのコミュニケーションを見つめ直すきっかけになれば、これほど嬉しいことはありません。変わりゆく時代の中で、私たち一人ひとりが学び、アップデートし続けること。それこそが、世代を超えた真の繋がりを生み出していくのだと信じています。


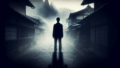
コメント