なぜ、私たちの給料は一向に上がらないのか? なぜ、将来への漠然とした不安は消えないのか? なぜ、国会では私たちの生活に直結する議論が深まらないのか?
その根源は、自民党が断行した『派閥解消』という名の劇薬にあります。政治を浄化するはずだったこの「改革」は、政策論争という政治の心臓を止めてしまいました。今、永田町を支配するのは、麻生、菅、そして岸田という「3人のキングメーカー」の密室談合。理念の旗は降ろされ、議員個人の損得勘定だけが渦巻く、不透明で原始的な権力闘争が繰り広げられています。
これは単なる政局解説ではありません。本稿は、その水面下で静かに進行する「政策の死」と、私たちの未来が盗まれていく新たな権力ゲームの構造を解き明かす警告の書です。あなたの生活が、政策なき密室の論理で決定されてしまう。これは、その悲劇の序章なのです。
【政策、死す】派閥なき自民党を牛耳る「亡霊」たちと、密室政治の陥穽
第1章:漂流する政治──骨抜きにされた「改革」が示したもの
記憶に新しい2024年の政治資金規正法改正の迷走。あれは、政策という羅針盤を失った政権与党が、いかに容易く漂流するかを白日の下に晒した事件でした。
裏金問題を受け、国民の怒りを前に、当初は「企業・団体献金の禁止」や「政策活動費の完全公開」といった抜本改革案が掲げられました。しかし、結果はどうだったか。かつて党内の意見を集約し、良くも悪くも議論をリードした派閥という「中間集団」を失った党内は、司令塔なき烏合の衆と化していました。
各議員の関心は、国家の将来ではなく、次の選挙で自分を支援してくれる業界団体の顔色。党の方針よりも、個別の支援者への義理。国民の期待を乗せた改革案は、そうした議員たちの保身の前に、まるで紙くずのように一つ、また一つと骨抜きにされていきました。最終的に成立したのは、公明党の要求を丸呑みした「成果ゼロ」と揶揄される妥協の産物です。
政策論争ではなく、個々の議員の損得と数合わせがすべてを支配する。 派閥というエンジンを失った巨大与党は、国民の期待という追い風を受けながらも、どこへも進めない漂流船と成り果てたのです。
第2章:永田町を彷徨う3人の「亡霊」──密室談合という新たな権力
では、政策議論が消え去った自民党で、一体誰が意思決定を担っているのか。その答えを示唆する、象徴的な光景がありました。
レントゲン写真に写るもの:7月23日の密室会談
7月23日、石破茂首相は、麻生太郎最高顧問、菅義偉前副総裁、岸田文雄前首相と相次いで会談しました。この動きは、まるで政治の水面下を写し出すレントゲン写真のように、派閥なき時代の権力構造を可視化します。
- 首相の行動: 政権運営の重要局面で、まず党の公式機関ではなく、3人の首相経験者との「根回し」を優先した。
- 浮かび上がる構造: 公の議論の前に、密室での「空気作り」が党の意思決定を事実上支配している実態が浮かび上がる。
- 象徴する意味: これは、派閥に代わる新たな権力装置として、キングメーカーによる非公式な談合が機能し始めたことを示す「儀式」に他ならない。
公式の派閥が消滅した今、党を実質的に動かしているのは、過去の権威を纏ったこの3人の「亡霊」です。彼らは公式の役職やルールではなく、極めて個人的な影響力で政治を動かしています。
- 麻生太郎氏: 存続する自身のグループと財界へのパイプを武器に、党内保守層の「お目付け役」として君臨。
- 菅義偉氏: 自身を慕う無派閥議員と、今なお睨みを利かせる官僚機構。「菅グループ」は政策課題ごとに結集する実動部隊となる。
- 岸田文雄氏: 首相経験者の権威と、旧宏池会の議員への影響力を背景に、キングメーカーの一角として存在感を示す。
党の重要方針は、総務会などの公式の場で議論される前に、この3人との密室談合で大枠が決まってしまう。この「空気」に逆らうことは「和を乱す」とされ、異論は封じ込められる。国民の声が政治に届く前に、政策の運命は密室で決定される。政策集団の死は、より陰湿で、説明責任の果たしようがない個人支配の時代を招いたのです。

第3章:政策家は死に、「選挙屋」が生まれる──政治家の質の劣化という悲劇
この構造がもたらす最大の悲劇は、政治家そのものの質の劣化です。
かつての派閥は、金権政治の温床という大きな「罪」の一方で、政策を学び、議論を戦わせる「教育機関」としての「功」がありました。例えば、旧宏池会はリベラルな外交・経済政策を、旧清和会は保守的な国家観を、それぞれ所属議員に叩き込みました。派閥は、新人議員に「政治家としてこの国をどうしたいのか」という理念の背骨を与える場所だったのです。
かつて若手議員は、派閥の勉強会で国家百年の計を学び、分厚い資料と格闘しました。今は、スマートフォンの画面に映る「いいね」の数と、有権者にウケる短いフレーズを探すことに時間を費やします。
この記事の核心
- 派閥解消の皮肉: 「政治浄化」を掲げた改革は、政策論争を消し去り、一部実力者による説明不能な密室政治を加速させた。
- 新たな権力支配: 麻生・菅・岸田らキングメーカーの個人的な影響力が、民意や公式な議論よりも優先される不透明な構造が定着した。
- 政治家の変質: 理念を学ぶ場を失った議員は「政策家」から「選挙屋」へ。国家の課題解決能力が著しく低下している。
- 有権者の責任: スローガンに騙されず、政治家個人の資質と具体的な行動、そして誰に動かされているのかを、これまで以上に厳しく見抜く必要がある。
政策を学ぶ受け皿が消えた今、議員の行動原理は「次の選挙でどう生き残るか」という一点に収斂します。国家のビジョンではなく、誰につけば有利か。政策のプロではなく、選挙と自己アピールのプロばかりが増殖していく。これは、政治家が「政策の担い手」から「人気取りのタレント」へと変質していく過程に他なりません。党全体の政策立案能力が地に落ち、国家の羅針盤が失われるのは、当然の帰結なのです。
結論:沈黙は、共犯だ──監視者なき時代に、主権者が試されること
派閥解消という「劇薬」は、裏金問題の根本解決には至らず、政治の不透明性を増幅させるという最悪の副作用をもたらしました。政策は一部実力者の胸先三寸で決まり、そのプロセスは国民の目から完全に隠されています。この構造が続く限り、自民党総裁選は未来を語る政策論争の場ではなく、キングメーカーによる「椅子取りゲーム」の代理戦争と化すでしょう。
では、私たちはこの不透明な権力ゲームを前に、ただ沈黙しているしかないのでしょうか。答えは断じて否です。今こそ求められるのは、私たち有権者が、政治家を見る「解像度」を格段に上げることです。
第一に、「改革」という美名に惑わされないこと。 そのスローガンの裏で、誰が得をし、何が失われたのか、権力構造の本質を見抜く知性が必要です。
第二に、政治家の「言葉」ではなく「行動」の記録を追うこと。 先の政治資金規正法改正で、あなたの選挙区の議員は賛成票と反対票のどちらに投じたのか。国会会議録検索システムを使い、彼らがどのような質問をしているか、あるいは全くしていないのか。具体的なファクトで評価する習慣が、政治家への何よりのプレッシャーとなります。
そして最も重要なのは、政治家の背後にある「人間関係」を透かし見ること。 どの議員がどのキングメーカーと頻繁に会合を重ねているのか。その「見えざるグループ」こそが、今の政治を動かす本当の単位なのです。
政治の意思決定プロセスがブラックボックス化する時、私たちの民主主義は静かに窒息します。これは自民党だけの問題ではありません。
民主主義は、私たちが諦めた時に死にます。今、その心臓を再び動かすことができるのは、主権者である私たち一人ひとりの、賢明で、粘り強い監視の眼差し以外にないのです。
📢 この記事をシェア
この記事が役に立った、面白いと感じたら、ぜひお友達やソーシャルメディアでシェアしてください。
💬 コメントをください!
自民党の派閥、なくなって良かったと思いますか? それとも、あった方がマシだったと思いますか?

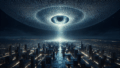

コメント