この記事でわかること
- 国民的番組『芸能人格付けチェック』が、なぜたった一夜でSNSを炎上させるに至ったのか、その全貌。
- 批判の核心にあった、未来ある中学生を“噛ませ犬”として扱った企画コンセプトの構造的な問題点。
- 「誰も褒めない…」一流芸能人たちの残念な態度が、いかにして視聴者の怒りに火をつけたか。
- この問題の根底に横たわる、テレビの“昭和的”な価値観と、私たちの時代の感覚との間に生まれた「致命的なズレ」。
「あれは失礼すぎる」――国民的番組『格付けチェック』は、なぜたった一夜で大炎上したのか?
「あれ、なんだか胸がザワザワする…」――。2025年9月27日に放送された『芸能人格付けチェック 秋の3時間半スペシャル』(テレビ朝日系)を見て、そう感じたのは、あなただけではありません。一流芸能人たちがプライドをかけて“本物”を見抜く、お正月恒例の人気番組。しかしその日、ある企画がSNSに凄まじい批判の嵐を巻き起こし、「芸能人格付けチェック 炎上」という不名誉なトレンドを生み出してしまいました。
問題の渦中にあるのは、「混合アンサンブル」と名付けられた企画。国内外の名門を卒業した一流プロと、全国コンクールで受賞歴を持つ実力派の中学生たちが同じ曲を演奏。どちらがプロの演奏か、芸能人たちが当てる。――文字にすれば、いつもの『格付けチェック』です。では一体、このありふれた企画のどこに、視聴者の心を逆なでする“地雷”が埋まっていたというのでしょうか?
この記事では、なぜあの夜、多くの人が怒りと違和感を覚えたのか、その理由を徹底的に解剖します。そして、この炎上の煙の向こうに見える、テレビと私たちの間に横たわる、無視できない価値観の溝に迫っていきます。
なぜ彼らは“噛ませ犬”にされたのか? 炎上の震源地となった企画の「構造的欠陥」
今回の炎上で噴出した批判の矛先は、何よりもまず、企画そのもののコンセプトに向けられました。番組は、プロの演奏を「正解」、そして中学生の演奏を「不正解」と、あまりにも無邪気に定義してしまった。この構図こそが、すべての問題の始まりだったのです。
未来の音楽家を「不正解の選択肢」と呼ぶ、無神経さ
勘違いしてはいけません。番組に登場した中学生たちは、決して「素人」などではないのです。ある報道によれば、彼らは「有名なコンクールで受賞経験がある“本気で音楽に打ち込む”人たち」。来る日も来る日も血のにじむような練習を重ね、その指先と感性にすべてを懸ける、未来の音楽家たちです。
しかし、番組のフォーマットは、彼らの血と汗の結晶である演奏を、芸能人を間違えさせるための「偽物」「不正解の選択肢」という残酷な役割に押し込めました。この演出に、SNSは敏感に反応します。
格付けチェック、食材や楽器ならいいけど演奏者がプロか中学生かで出題するのはダメでしょ。これは間違えた人を落とすのではなくプロと間違われるレベルの演奏をした中学生を称えるべきものだし、プロに劣るものとして用意された中学生達に対してコンプセプトからして失礼。
ただの中学生じゃない、音楽界の将来のトップミュージシャンでしょ、これを不正解と笑うの失礼だよ
多くの人が感じたのは、才能ある若者たちの尊い努力と情熱が、バラエティ番組の都合のいい“道具”として軽々しく消費されていくことへの強い憤りでした。彼らの演奏は、それ自体がかけがえのない芸術です。それを「プロに劣るもの」というレッテルを貼り、いわば“噛ませ犬”として扱う。この構図そのものが、あまりにも傲慢で、敬意を欠いていたのです。
音楽に「正解」なんてあるのか? 番組が犯した、芸術への冒涜
さらに問題を根深くしたのは、公式サイトがプロの演奏を臆面もなく「正解」と表現していたことです。考えてみてください。音楽や芸術に、絶対的な「正解」など存在するのでしょうか?もちろん技術の優劣はあります。しかし、誰かの心を震わせるかどうかに、プロもアマもありません。事実、SNSには「中学生の演奏の方がグッときた」という声が、決して少なくなかったのです。
「正解」という言葉は、それ以外をすべて「間違い」だと断罪する、一種の暴力を秘めています。番組側に悪気はなかったのかもしれません。しかし、その無自覚さこそが、中学生たちの演奏の価値を一方的に切り捨て、彼らのプライドを踏みにじりかねない危険性をはらんでいた。言葉一つを選ぶセンスに、制作者側の致命的な配慮の欠如が透けて見えた瞬間でした。
「恥ずかしい…」じゃないだろ! 誰も中学生を褒めなかった、一流芸能人たちの“品格”
企画そのものが抱える問題に加え、視聴者の怒りの炎に油を注いだのが、出演者たちのリアクションでした。多くの芸能人が、プロと中学生の演奏を聴き分けられずに、不正解の部屋へと吸い込まれていく。これは、見方を変えれば、中学生たちの演奏がいかに素晴らしかったかの動かぬ証拠です。
視聴者が本当に聞きたかった、たった一言
しかし、不正解を突きつけられた彼らの口から出たのは、「恥ずかしい」「耳が悪い」といった自己保身の言葉や、仲間を揶揄する声ばかり。特に、俳優の生瀬勝久さんが「ちゃんと聞けばわかるでしょう」と声を荒らげたシーンは、多くの人の心に冷水を浴びせました。
私たちが、そして多くの視聴者が本当に聞きたかったのは、そんな言葉ではなかったはずです。
「いや、参った!中学生の演奏、本当に素晴らしかった。完全に騙されたよ」
そう、この一言です。ところが、放送された映像の中では、若き才能の健闘を心から称える声は、驚くほど聞こえてきませんでした。SNSが失望したのは、当然のことだったのかもしれません。
なぜあの場にいた誰もが「中学生が良い演奏をした」と称賛せずに、耳が悪いだの恥ずかしいだの言っているんだろう。ほんと見苦しいな。
もちろん、編集でカットされた可能性も否定できません。しかし、結果として私たちに届けられたのは、自分のミスを嘆くだけで、自分たちを打ち負かした素晴らしい才能へのリスペクトを忘れたかのような姿でした。これが、番組が掲げる「一流芸能人」の振る舞いなのでしょうか。そのあまりのギャップが、視聴者の不信感を決定的なものにしたのです。
もはや笑えない… テレビの“常識”と私たちの“感覚”の間に横たわる、致命的な溝
今回の『芸能人格付けチェック』の炎上は、テレビ業界が今も引きずる古い価値観と、新しい時代を生きる私たちの感覚との間に生まれた、あまりにも大きな断絶が、ついに可視化された事件なのです。
人を“格付け”して笑う時代は、もう終わった
少し前まで、テレビバラエティでは、素人さんをプロと比べて笑い者にしたり、誰かを「格下」としてイジったりする演出は、“お約束”としてまかり通っていました。そして私たち視聴者も、それをエンタメとして消費してきた歴史があります。
しかし、時代は音を立てて変わりました。SNSによって、誰もが声を上げられるようになった今、私たちは一個人の努力や尊厳が軽く扱われることに、かつてなく敏感になっています。特に、人生を懸けて何かに打ち込む人を安易に笑いのネタにしたり、優劣の物差しで測ったりする風潮に対し、社会は明確に「NO」を突きつけるようになったのです。
今回の企画は、この現代の価値観と真正面から衝突しました。「プロ=正解、アマ=不正解」という乱暴な二元論で人を“格付け”し、間違えた大人を笑う。そんな昭和・平成のバラエティ文法が、もはや通用しないどころか、人々を深く傷つける凶器になりうることを、この炎上は残酷なまでに証明したのです。
視聴者はもう黙っていない。テレビに突きつけられた「最後通告」
私たちはもはや、テレビが垂れ流す情報をただ受け取るだけの“物言わぬ大衆”ではありません。番組に違和感を覚えれば、スマホ一つで瞬時に意見を共有し、巨大な世論を形成することができます。そう、私たちは番組の「批評家」であり、時にその存続すら左右する「参加者」なのです。
テレビを作る人々は、この現実を骨の髄まで理解し、番組作りのOSを根本からアップデートしなければなりません。この企画は誰かを傷つけないか。表現に傲慢さはないか。出演者だけでなく、画面に映らない協力者へのリスペクトは存在するか。そんな問いが、これからの番組作りには絶対に不可欠です。今回の『芸能人格付けチェック』の炎上は、テレビ業界全体に突きつけられた、痛烈な警告なのです。
ホンモノの「一流」とは何か? 『格付けチェック』が見失った、たった一つの答え
この騒動は、番組の根幹をなす「一流」というテーマそのものを、私たちに問い直させます。番組が示してきた「一流」とは、高価なワインの味や、高級な芸術品の価値を見抜く能力でした。しかし、本当にそれだけで人は「一流」と呼べるのでしょうか?
問われるべきは耳じゃない、その「人間性」だ
私が思うに、真の「一流」とは、専門的なスキルはもちろんのこと、どんな相手に対しても敬意や思いやりを忘れない、その美しい姿勢にこそ宿るのではないでしょうか。
想像してみてください。もし、不正解の部屋に座る芸能人たちが、悔しがりながらも、晴れやかな笑顔でこう言っていたら。
「参りました!あの中学生たちの演奏、本当に素晴らしかった。将来が楽しみですね。完全に心を掴まれました」
たったこれだけの言葉で、スタジオの空気は、そしてテレビの前の私たちの気持ちは、どれほど救われたことでしょう。それは、自らの過ちを認め、自分を惑わせるほどの若き才能を素直に称賛できる、まさに「一流の振る舞い」として、私たちの目に映ったはずです。番組は、笑いと感動を両立させる千載一遇のチャンスを、あまりにも無残に手放してしまったのです。
問われるべきは、芸能人の耳の良し悪しではありませんでした。問われるべきだったのは、技術や知識を超えた、その人間性や品格。番組は、出演者と制作陣自身に、もっと高い基準を課すべきだったのではないでしょうか。
「他人事」では済まされない。この炎上が、私たち一人ひとりに問いかけるもの
『芸能人格付けチェック』を巡るこの騒動は、決してテレビの中だけの話では終わりません。ここには、今の社会を生きる私たち全員が、心に刻むべき大切な教訓が隠されています。
それは、プロかアマか、大人か子供かといった肩書きで人を判断するのではなく、一人ひとりの人間の努力や情熱、そしてその成果物に対し、誠実な敬意を払うことの重要性です。メディアは、わかりやすさを追求するあまり、時に人を記号として扱います。しかし、その記号の向こうには、私たちと同じように悩み、傷つき、喜ぶ、生身の人間がいることを、決して忘れてはなりません。
この一件は、テレビという巨大メディアのあり方に疑問符を投げかけると同時に、私たち視聴者のメディアリテラシーをも試しています。何に違和感を持ち、なぜそれを「おかしい」と感じるのか。自分の言葉で考え、声を上げること。その小さな行動の積み重ねこそが、より思慮深く、より優しいメディアと社会を築く、唯一の力になるのだと、私は信じています。
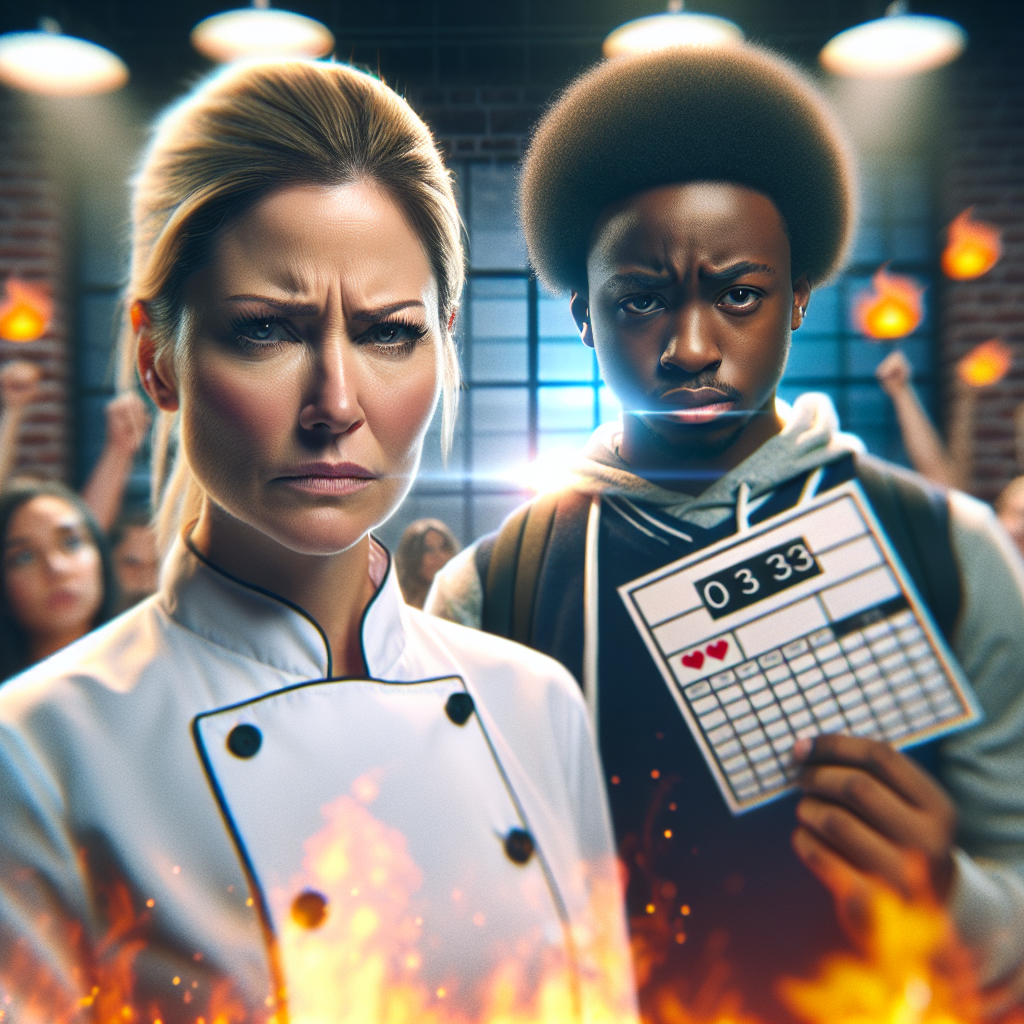


コメント