この記事を30秒で読むなら
- あなたの街でも起きている? バーやクラブなど「夜の街」に倒産の嵐が吹き荒れ、件数は過去最多を記録。
- 原因は物価高だけじゃない。私たちの”飲み会の作法”の変化、特に「二次会に行かなくなった」ことが静かに彼らの首を絞めている。
- 新規客は来ず、限られた富裕層や常連客を店同士で奪い合う、壮絶なサバイバルゲームが始まっている。
- 奇妙なことに、店が次々潰れる繁華街で、なぜか不動産だけはインバウンド需要で高騰。謎の「物件争奪戦」が勃発している。
「二次会、どうする?」――その一言が、あなたの街から消えていく
「最近、あの角にあったバー、見かけないな」「昔、上司に連れて行かれたスナックが、いつの間にか更地になっていた」。そんな寂しさを、あなたも感じたことはありませんか? かつてネオンが煌めき、人々の笑い声が響いていた「夜の街」から、一つ、また一つと灯火が消え始めています。
残念ながら、それはあなたの気のせいではありません。帝国データバンクの調査によれば、2023年度の「バー、キャバレー、ナイトクラブ」の倒産件数は72件。これは過去最多の数字です。飲食業界全体で見ても802件と、まさに記録的なバッドニュース。そう、今この瞬間も、「夜の街」で静かすぎる、しかし深刻すぎる異変が起きているのです。
2023 年度の「飲食店」倒産、802件で過去最多 […] 業態別(11 業態)にみると、最も多かったのは居酒屋を主体とする「酒場、ビヤホール」(207 件)で、[…] 「バー,キャバレー,ナイトクラブ」(72 件)が続いた。
ニュースは決まって「物価高」「人件費の高騰」を理由に挙げます。しかし、本当にそれだけでしょうか? この記事では、東海地方最大の繁華街・名古屋“錦三”のママたちの悲痛な叫びを糸口に、単なる不況では片付けられない、私たちの働き方、そして価値観そのものの地殻変動にメスを入れていきます。あなたの好きだった「あの店」が、なぜ消えなければならなかったのか。その本当の理由が、きっと見えてくるはずです。
「もう限界…」悲鳴が聞こえる。日本屈指の繁華街、名古屋・錦三のリアル
東海地方の夜を彩ってきた、名古屋市中区錦三丁目、通称“錦三(きんさん)”。このきらびやかな街も、時代の巨大なうねりの前では無力です。CBCテレビが伝えたその現場は、私たちの想像以上に過酷な現実を突きつけてきました。
「ボトル1本4万円」それでも赤字…物価高という”見えざる敵”
まず、日本中の飲食店を襲っている悪夢が、錦三にも容赦なく牙を剥きます。ウイスキーや食材は軒並み値上がりし、女の子たちの給料を上げなければ誰も働いてくれない。しかし、そのコストをメニュー価格に正直に上乗せすれば、客の足はピタリと止まってしまう…。
錦三でクラブを経営する村井美咲ママの言葉が、そのジレンマを物語っています。CBCテレビの取材に、彼女は絞り出すようにこう語りました。「本当に頑張らないと生き残れないと感じています」。一番安いボトルを入れても、会計は一人4万円弱。この金額をポンと払える人が、今の日本にどれだけいるというのでしょうか。
東京商工リサーチが言うように、「物価高と人件費高騰の波が一番大きなところ」なのは間違いありません。しかし、錦三のママたちの苦悩の根源は、もっと別の場所にあったのです。
「じゃ、ここで解散!」“二次会スルー”が文化を破壊する
「食事までは錦に来るが『二次会は帰ります』『電車で帰ります』という方が増えた。『二次会はなくなりました』という方が増えた」
美咲ママのこの一言こそ、夜の街のビジネスモデルを根底から破壊する、恐ろしい変化の正体です。思い出してみてください。かつて「一次会は居酒屋で、二次会はスナックかクラブへハシゴ酒」は、日本の会社員にとってお決まりのフルコースでした。この「二次会需要」こそが、彼女たちの店の生命線だったのです。
しかし、その文化は今や風前の灯火。一次会で盛り上がったら、スマホを見て終電を気にして、ハイ解散。この新しい“作法”は、夜の街の生態系を完全に変えてしまいました。焼き鳥屋のような一次会向けの店はむしろ繁盛しているのに、そのバトンを受け取るはずだった二次会、三次会の店だけが、お客の来ないカウンターで静かに夜を明かしているのです。
常連客は”回遊魚”? 太客を奪い合う仁義なきサバイバル
二次会のお客さんが消え、新しい顔ぶれも見なくなった錦三の夜。そこでは一体、何が起きているのか。別のクラブの吉澤もえママが、厳しい現実を打ち明けてくれました。
「同じお客様が(いろいろな店を)行ったり来たりしている状況」
名古屋“錦三”のママ「二次会が減った…」 全国で相次ぐクラブやバーの倒産 物価高や人件費高騰で夜の街ピンチ!? 一方で不動産は“繁華街の物件”争奪戦CBCテレビ10/19(日) 7:35
これはつまり、新しいお客さんは増えず、ごく一握りの「夜遊び好き」な富裕層や古くからの常連客という“回遊魚”を、無数の店が必死で釣り上げようと奪い合っている、ということ。50年間で錦に2億円以上も使ったというツワモノの常連客ですら、「接待とか経費で使えるお金がないと、自分のお金で来る人はそんなにいない」とバッサリ。夜の街は今、ごく一部の愛好家だけに支えられた、先細りの市場へと変貌してしまったのです。
もはや不況のせいじゃない。夜の街を殺した「3つの不都合な真実」
物価高、人件費高騰、そして二次会の消滅。これらは確かに、夜の街を追い詰める直接的な犯人です。しかし、私が本当に恐ろしいと感じるのは、その背後でうごめく、もう後戻りできない3つの社会構造の変化。これこそが、この問題の本質をえぐる鍵となります。
真実①:「経費で落ちない」時代の到来。コンプライアンスが”接待”を過去の遺物にした
かつて、夜の街をジャブジャブのお金で潤していた魔法の言葉、それは「会社の経費」でした。しかし、バブル期のようにタクシーチケットが飛び交う時代は、遠い昔のおとぎ話です。
多くの人はこれを不景気のせいにしますが、本質は違います。犯人は、企業の「コンプライアンス(法令遵守)」という名の、あまりに健全すぎる壁です。不透明なカネの流れは厳しくチェックされ、取引先との過剰な接待は「癒着」のリスクとして徹底的に排除される。パワハラ、セクハラへの意識の高まりが、かつての「無礼講」を許さなくなったことも大きいでしょう。
もちろん、これは社会としてあるべき姿への進化です。しかし私たちは、その健全化のプロセスで、旧態依然の接待文化にどっぷり依存していた夜の街のビジネスモデルを、知らず知らずのうちに破壊してしまったのかもしれません。
真実②:「飲み会より推し活」Z世代の”タイパ至上主義”という鉄槌
次に指摘しなければならないのは、私たちの価値観、特に若い世代のそれがあまりにも劇的に変わってしまったという事実です。
Z世代と呼ばれる彼らが神のごとく崇めるのは「タイパ(タイムパフォーマンス)」。知らないおじさんの武勇伝を延々と聞かされる会社の飲み会に、貴重な夜を捧げる義理はありません。その時間があるなら、自分の趣味や推し活、スキルアップに投資したい。そもそもお酒を飲まない「ソバーキュリアス」という生き方を選ぶ若者も増えています。
飲み会のカタチが根本から変わった今、会社の付き合いで高級クラブのソファに座るという光景は、もはやファンタジーの世界。世代交代という静かな、しかし止められない波が、確実に夜の街から客を遠ざけているのです。
真実③:「給料は上がらない」のに…シビアすぎる私たちのお財布事情
そして最後の、最も身も蓋もない真実。それは、シンプルに「私たちにお金がない」という現実です。ご存知の通り、この国では実質賃金が驚くほど上がっていません。それなのに物価だけは上がり続け、自由に使えるお金は減る一方。
こんな状況で、私たちは「何にお金を使い、何を諦めるか」という残酷な選択を迫られています。旅行やライブ、自分への投資といった「価値ある体験」にはお金を惜しまない一方、目的のよくわからない二次会の高い飲み代は、真っ先に家計の仕分け対象になるのは当然のこと。
錦三のクラブで一人4万円。この金額を見て、今のあなたが「安い」と感じることはありますか? 一部の富裕層を除き、多くの人にとって夜の街は、憧れの「特別な場所」から、自分とは関係のない「縁遠い場所」へと変わり果ててしまったのです。
ゴースト化する店舗、バブル化する土地。なぜ繁華街で「謎の争奪戦」が起きているのか?
ここまで、夜の街の暗い話ばかりをしてきました。しかし、この物語には一つ、奇妙で皮肉な続きがあります。それは、ママたちが悲鳴を上げて店を畳む一方で、その繁華街の土地だけが、まるでバブルのように価格高騰し“争奪戦”になっているという、にわかには信じがたい現実です。
現場の悲鳴を知らない”投資家”たちの論理
なぜ、こんな矛盾したことが起きるのでしょうか? 答えは簡単。店を切り盛りするママたちと、土地を売買する投資家たちが、全く別の世界、別の時間軸を生きているからです。
バーやクラブの経営者は、今日の売上、今月の客足に一喜一憂する短期決戦の世界に生きています。しかし、不動産投資家が見ているのは、もっと遠い未来。その土地が秘める「化ける可能性」です。
シャッターが下りた店の跡地を狙っているのは、次のバーの経営者だけではありません。むしろ、夜の街とは全く関係のない巨大資本が、その優良物件を虎視眈々と狙っているのです。
黒船は”インバウンド”と”再開発”。グローバルマネーが街を買い漁る
その巨大資本の筆頭が、インバウンド(訪日外国人)需要に沸くホテルや商業施設です。記録的な円安の今、海外の観光客にとって日本の都市はまさに黄金郷。繁華街の一等地は、彼らのためのホテルや免税店を建てるには最高のロケーションであり、国内外のデベロッパーが札束を手に土地を買い漁っています。
さらに、多くの大都市で進む「再開発プロジェクト」への期待感が、不動産価格に火をつけます。今は古びた雑居ビルでも、数年後にはピカピカの超高層ビルに生まれ変わるかもしれない――その期待感が、投機マネーを呼び込んでいるのです。
この「倒産ラッシュの現場」と「バブルに沸く不動産」という歪な二極化は、もしかすると現代日本の縮図なのかもしれません。現場で必死に働く人々が苦しむ裏側で、グローバルなマネーゲームが街の景色を根こそぎ変えていく。この静かなる侵食が、私たちの知る繁華街の姿を、もう二度と戻らない場所へと変えようとしているのです。
まとめ:夜の街はどこへ行く?これからの「灯火」を考える
物価高という直接的なボディブロー。そして、接待文化の終焉、価値観の変化、可処分所得の減少という、じわじわと体を蝕むボディブロー。幾重ものパンチを受け続けた「夜の街」は今、明らかにダウン寸前です。
おそらく、かつてのように、誰もが二次会、三次会へと千鳥足で繰り出した、あの熱狂の時代が戻ることはないでしょう。しかし、これは「夜の文化」が完全に消え去ることを意味するのでしょうか? 私は、そうは思いません。むしろ、時代に合わせて新しい形へと“進化”を迫られる、壮大な実験の始まりだと捉えたいのです。
例えば、誰もが知る高級クラブではなく、特定のウイスキーや日本酒をとことん極めた専門店。あるいは、ボードゲームやeスポーツといった共通の趣味で繋がるコミュニティバー。大規模な接待ではなく、地域の顔見知りが愚痴をこぼしに集まる、止まり木のような小さなスナック。そんな、もっと個人的で、もっと目的がクリアな社交場の価値は、むしろこれから高まっていくはずです。
「夜の街の倒産」というニュースは、単なる経済問題ではありません。それは、私たち一人ひとりへの問いかけです。「これからの時代、あなたは誰と、どんな繋がりを求め、何に大切なお金と時間を使いたいですか?」と。あなたの街の灯火が、次にどんな形で、誰のために輝くのか。その変化を他人事とせず見つめていくことこそ、未来の社会を豊かにする第一歩になるのではないでしょうか。

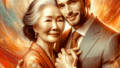
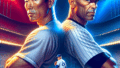
コメント