2025年8月22日、一本の訃報が京都の街だけでなく、日本中の多くの人々に衝撃と深い悲しみをもたらしました。京扇子の老舗「大西常商店」の4代目社長、大西里枝さんが35歳という若さでこの世を去ったのです。
彼女の死を悼む声は、瞬く間にSNSを駆け巡りました。松井孝治京都市長は「いくらなんでも、早すぎます…」と、その早すぎる別れを惜しみました。彼女と親交のあった人々や、お店を訪れた顧客からは、「嘘でしょ」「お会いしたばかりなのに」「気さくでかわいらしい方でした」といった悲痛な声が次々と上がりました。
なぜ、一人の若き女性経営者の死が、これほどまでに多くの人の心を揺さぶるのでしょうか。彼女は一体何者で、何を成し遂げたのか。そして、なぜこれほどまでに愛されたのか。
この記事では、大西里枝さんという一人の女性が、その短い生涯で伝統産業に吹き込んだ新しい風と、彼女が遺した大切なメッセージを紐解いていきます。これは単なる追悼記事ではありません。伝統を未来へ繋ぐとはどういうことか、そして、全力で生きることの意味を、彼女の生き様から学ぶ物語です。
1. 大西里枝さんとは何者だったのか? – 100年続く店の若き4代目女将
大西里枝さんの人物像を語る上で、彼女のユニークな経歴は欠かせません。彼女は単なる「老舗の跡継ぎ」という言葉だけでは到底語り尽くせない、強い意志と行動力を持った改革者でした。
扇子屋の一人娘、一度は選んだ外の世界への道
1990年、100年以上の歴史を持つ京扇子の老舗「大西常商店」に、彼女は一人娘として生を受けました。京都の伝統が息づく環境で育った彼女ですが、大学卒業後に選んだ道は、意外にも家業ではありませんでした。
2012年に立命館大学政策科学部を卒業したのち、東日本大震災での通信インフラの重要性を感じたため西日本電信電話(NTT西日本)に入社。
5%A4%A7%E8%A5%BF%E9%87%8C%E6%9E%9D” rel=”noopener noreferrer” target=”_blank”>大西里枝 – Wikipediaより引用
東日本大震災を機に社会インフラの重要性を感じ、大手通信会社に就職。熊本や福岡で、中小企業向けの営業としてキャリアをスタートさせます。この「一度、外の世界を見る」という経験が、後に彼女が家業に革命をもたらす上で、計り知れない財産となりました。伝統の世界を内側からだけでなく、外側から客観的に見つめる視点。そして、ビジネスの最前線で培った顧客視点とコミュニケーション能力。これらが、後の「若女将・大西里枝」の礎を形作っていったのです。
Uターン、そして伝統への深い愛情とともに4代目へ
NTT西日本の同僚と結婚し、出産を機に京都へ戻った彼女は、大きな決断をします。それは、家業である「大西常商店」を継ぐことでした。それは単なるUターンではなく、彼女自身の意志による選択でした。
その後、扇子を彩る「和の色彩」「伝統文様」に魅了され、家業の大西常商店へ。
一度離れたからこそ、改めて気づいた家業の魅力。扇子に込められた繊細な美しさや、京都の文化の奥深さに心を動かされ、彼女は4代目としての道を歩み始めます。しかし、彼女が目指したのは、ただ伝統を守ることだけではありませんでした。通信会社で培った経験を活かし、この美しい文化をどうすれば現代の、そして未来の人々に届けられるか。彼女の挑戦は、ここから本格的に始まったのです。
2. 伝統を未来へ繋いだ「3つの革命」
大西さんは、若女将、そして社長として、伝統産業が抱える課題に真正面から向き合いました。彼女が実践した取り組みは、まさに「伝統産業のDX革命」と呼ぶにふさわしいものでした。その中から、特に象徴的な3つの革命を紹介します。
革命①:SNSによる「生きた文化」の発信 – 伝統産業のDX革命家
彼女が最も力を入れたことの一つが、SNSを通じた情報発信でした。しかし、それは単なる商品の宣伝ではありません。彼女が発信したのは、扇子を取り巻く京都の「暮らし」や「文化」そのものでした。
着物姿で菖蒲を地面に叩きつける「菖蒲打ち」を実演したり、お盆に家の門口に煮汁を撒く風習を紹介したり。彼女のSNSには、教科書には載っていない、京都に今も息づくリアルな日常が溢れていました。それは、多くの人が「知らなかった京都」であり、彼女の投稿を通じて、人々は京都文化の面白さや奥深さに触れることができました。
この活動の根底には、彼女の強い信念がありました。
私は京扇子の製造を生業にしておりますが、これも京都の文化の1つです。扇子は京都の文化と共に育まれた商品ですから、京都の風習や行事などもあわせて発信していくことに意味があるのではと思っています
彼女にとって扇子はモノではなく、文化の結晶でした。だからこそ、その背景にある物語ごと伝えようとしたのです。これは、デジタルツールを駆使して文化体験そのものを発信する、まさに「伝統産業のDX(デジタル・トランスフォーメーション)」でした。
革命②:常識を覆すコラボレーション – 「いけず」を逆手に取った天才マーケター
2023年、彼女の名をさらに広く知らしめる出来事が起こります。「裏がある京都人のいけずステッカー」のイメージモデルへの就任です。これは、京都人の「本音と建前」をユーモラスに表現したステッカーで、彼女はそのモデルとして、上品な笑顔の裏に隠された「いけず」な表情を見事に演じ分けました。
老舗の若女将が、自ら「いけず」な顔を見せる。この常識を打ち破る大胆なコラボレーションは、大きな話題を呼びました。多くの人が、彼女のユーモアのセンスと、懐の深さに驚かされました。彼女は、京都の「いけず」という、ともすればネガティブに捉えられがちなイメージを逆手に取り、それを「面白い」「カワイイ」というポジティブな魅力へと昇華させてみせたのです。
このステッカーは新しい京都土産として大ヒット。彼女は、伝統を守るだけでなく、時にそれを軽やかに飛び越え、新しい価値を創造する天才的なマーケティング感覚の持ち主でもありました。
革命③:扇子の新たな価値創造 – 暮らしに寄り添う伝統へ
大西さんは、扇子そのものの価値を再定義することにも挑戦しました。NTT西日本での営業経験から、彼女は常に顧客の視点を大切にしていました。「今の時代に、扇子をどう使ってもらうか」「どうすれば若い世代にも魅力を感じてもらえるか」。その問いへの答えが、彼女の商品開発や活動に反映されていました。
伝統的な技法を守りながらも、現代のファッションやライフスタイルに合うデザインを取り入れたり、扇子作りを体験できるワークショップを開催したり。彼女は、扇子を「特別な日の道具」から、「日常に彩りを与える文化的なアイテム」へと変えようとしました。
彼女の店を訪れた人は、ただ扇子を買うだけではありませんでした。彼女との会話を通じて、扇子の歴史や職人の想い、そして京都の文化に触れる。その一連の体験こそが、彼女が提供したかった新たな価値だったのです。
3. なぜ彼女は多くの人を惹きつけたのか? – その人柄と哲学
彼女の功績は素晴らしいものですが、多くの人が彼女の死を悼む理由は、それだけではありません。彼女自身の持つ人間的な魅力と、仕事や文化に対する真摯な姿勢が、多くの人の心を捉えて離さなかったのです。
全力投球の姿勢と、誰からも愛される人柄
松井京都市長が「ほんまにいつも真面目で真剣で、全力投球のお方でした」と語ったように、彼女は仕事に対して常に真摯でした。その真剣さは、SNSの投稿やメディアでの発言からもひしひしと伝わってきました。
しかし、彼女は決して堅苦しい人物ではありませんでした。SNSに寄せられた「気さくでかわいらしい方でした」「お店で対応してもらったばかり」といった声が示すように、彼女は誰に対しても壁を作らず、太陽のような明るさと親しみやすさで接していました。伝統産業の担い手としての誇りを持ちながらも、決して偉ぶることなく、一人の人間として相手と向き合う。そのバランス感覚が、彼女の大きな魅力でした。
「いけずステッカー」で見せたユーモアのセンスも、彼女の人柄を物語っています。伝統の重みを背負いながらも、それを楽しむ余裕と遊び心。そのしなやかさが、世代や立場を超えて多くの人を惹きつけたのです。
言葉から滲み出る、文化への深い敬意と愛情
彼女の発する言葉には、常に京都の文化への深い敬意と愛情が込められていました。前述の「扇子は京都の文化と共に育まれた商品」という言葉は、彼女の哲学そのものです。
彼女は、自分たちの仕事を単なる「モノづくり」とは捉えていませんでした。先人たちが築き上げてきた歴史と文化を受け継ぎ、それを未来へ繋いでいくという、大きな使命感を持っていたのです。
結婚・出産を機に京都へと戻り、扇子屋の4代目を承継し、前職での経験を生かした新商品の開発・販売などを行う。
この言葉の裏には、一度外に出たからこそ客観的に見えた家業の価値と、それを自らの手で発展させていきたいという強い決意が感じられます。彼女の言葉と行動の一貫性が、人々に信頼と共感を与えました。彼女は、同世代の、特に伝統的な世界で生きる女性たちにとって、まさに希望の星のような存在だったのです。
4. 彼女が遺したものと、私たちが受け取るべきメッセージ
35年というあまりにも短い生涯。しかし、彼女が遺したものは、計り知れないほど大きく、そして深い意味を持っています。彼女の生き様は、私たちに何を問いかけているのでしょうか。
伝統は「守る」だけでなく「アップデート」するもの
大西さんの最大の功績は、伝統はただ守り継ぐだけではなく、時代に合わせて「アップデート」していくべきだということを、身をもって示したことです。彼女は、伝統の本質的な価値を深く理解した上で、SNSという現代のツールを使いこなし、異業種とのコラボレーションも厭いませんでした。
「古いものは良いものだ」とただ言うのではなく、「なぜ良いのか」「どうすれば現代の生活の中で楽しめるのか」を翻訳し、伝え続けたのです。この姿勢は、扇子業界だけでなく、全国のあらゆる伝統産業や、変化の時代に悩む老舗企業にとって、大きな希望と具体的なヒントを与えてくれました。彼女が示した道は、これからも多くの人にとっての道しるべとなるでしょう。
35年という時間で示した「全力で生きる」ということ
彼女の訃報に触れた多くの人が、そのあまりの早さに言葉を失いました。しかし、同時に、彼女がこの35年間で成し遂げたことの大きさに改めて驚かされます。彼女は、与えられた時間を誰よりも濃密に、そして情熱的に生きました。
その姿は、私たちに問いかけます。「自分は今、全力で生きているだろうか?」「本当にやりたいことに、情熱を注げているだろうか?」と。
人生の長さは、誰にも決められません。しかし、その密度は自分自身で決めることができる。大西里枝さんの生き様は、時間の長さではなく、その一瞬一瞬をいかに輝かせるかが大切であるという、シンプルで力強いメッセージを私たちに遺してくれました。
まとめ
大西里枝さんは、京扇子の伝統を守りながら、SNSやユニークなコラボレーションといった現代的な手法でその魅力を果敢に発信した、まさに「伝統産業の革命家」でした。彼女の真摯な姿勢、文化への深い愛情、そして太陽のような人柄は、多くの人を惹きつけ、愛されました。
彼女の早すぎる死は、本当に残念でなりません。しかし、彼女が灯した光は、決して消えることはありません。彼女が示した「伝統を未来へ繋ぐ」という意志と情熱は、残された人々によって必ずや受け継がれていくでしょう。そして、彼女が全力で駆け抜けた35年の生涯は、これからも私たちの心に残り、自分の人生をどう生きるべきかを考えるきっかけを与え続けてくれるはずです。
心よりご冥福をお祈りいたします。


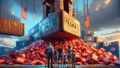
コメント