毎年夏、多くの感動と議論を巻き起こす日本テレビ系の『24時間テレビ』。しかし、今年の放送で視聴者の心に最も深く刻まれたのは、感動の涙ではなく、ある種の“違和感”だったかもしれません。その中心にいたのは、総合司会を務めた「くりぃむしちゅー」の上田晋也氏。日本屈指の「天才司会者」として知られる彼が、番組内で見せた言動に対し、SNSでは厳しい批判の声が殺到しました。
問題となったのは、バドミントン企画での宮川大輔氏への“失敗イジり”。「大輔さん、いま国技館、いや日本列島が引いております」という強烈な一言は、笑いを誘うどころか、多くの視聴者に不快感を与えました。なぜ、彼の十八番であるはずの「イジり」は、これほどまでに拒絶反応を生んでしまったのでしょうか。これは単なる一個人の失言ではありません。現代のテレビ、お笑い、そして私たち視聴者の価値観が複雑に絡み合った、時代の転換点を象徴する“事件”だったのです。本記事では、この炎上の深層を多角的に分析し、これからのテレビと笑いのあり方を考えます。
炎上の深層①:『チャリティー』という名の”聖域”
今回の炎上を理解する上で、まず考えなければならないのは、『24時間テレビ』という番組が持つ特殊な空気感です。この番組は単なるバラエティではありません。「愛は地球を救う」というテーマの下、「感動」「挑戦」「真剣さ」「共生」といった価値観が重んじられます。視聴者は、障がいを持つ方々のひたむきな努力や、困難に立ち向かう人々の姿に心を寄せ、涙します。いわば、番組全体が一種の“聖域”として機能しているのです。
上田氏の言動が問題視されたのは、まさにこの聖域の文脈においてでした。問題の企画「みんなで挑戦! パラアスリート スゴ技チャレンジ」には、パラリンピックのメダリストや一般の参加者も多数参加していました。
パラリンピックのメダリストである里見紗李さんや山崎悠麻さんらアスリートに加えて、企画の発案者である宮川大輔さん、『三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE』の岩田剛典さん、氷川きよしさん、さらに一般人が挑戦しました。
ギネス世界記録を目指すという真剣な挑戦の場で、宮川氏のミスを執拗に、そして大声で責め立てるような上田氏の態度は、多くの視聴者の目に「場の空気を読めない不謹慎な行為」と映りました。普段のバラエティ番組であれば、それは「愛あるイジり」として成立したかもしれません。しかし、真剣な挑戦を見守る“聖域”においては、そのイジりは挑戦そのものを茶化し、失敗を嘲笑う「攻撃」として受け取られてしまったのです。
さらに、この炎上の背景には、独自の視点として「『24時間テレビ』という番組自体に視聴者が抱く潜在的な不満」があった可能性も指摘できます。長年続くマンネリ化した構成、「感動の押し付け」とも揶揄される演出に対し、一部の視聴者は以前から冷ややかな視線を送っていました。その鬱屈した感情が、総合司会者である上田晋也という格好のターゲットを見つけ、彼の“不適切な”言動をきっかけに一気に噴出した、という見方もできるのではないでしょうか。つまり、これは上田氏個人の問題だけでなく、『24時間テレビ』というコンテンツが抱える構造的な問題が露呈した瞬間でもあったのです。
炎上の深層②:時代遅れになった『イジり』というお笑いの型
「昔はこれくらい許されたのに」「最近の視聴者は厳しすぎる」。そう感じた方もいるかもしれません。しかし、今回の炎上は、単なる過剰反応ではなく、社会全体の価値観の変化を浮き彫りにしています。かつてテレビの中心にあった「イジり」というお笑いの手法が、なぜ現代では機能しなくなったのでしょうか。
視聴者意識の変化:多様性とインクルージョンの時代へ
昭和から平成にかけて、テレビのお笑いは「誰かを落として笑いを取る」というスタイルが主流でした。容姿をイジる、失敗を責める、天然な言動を笑う。それは出演者同士の信頼関係の上で成り立つ「プロレス」であり、視聴者もそれを暗黙の了解として楽しんでいました。
しかし、時代は大きく変わりました。SNSの普及により、誰もがメディアの批評家となり、声を上げられるようになりました。「いじめ」や「ハラスメント」に対する社会全体の感受性も格段に高まっています。個人の尊厳や多様性を重んじる現代の価値観において、誰かの失敗やコンプレックスを大勢の前で指摘し、笑いものにする行為は、たとえ悪意がなくとも「公開処刑」や「いじめの助長」と見なされやすくなったのです。
SNS上では、上田氏の言動に対して、以下のような厳しい意見が相次ぎました。
《くりぃむ上田って、あんなに他人を傷つけるタイプの芸風だったっけ?最近番組見てないからかなあ。凄い嫌な気持ちになった》
特に今回の企画では、一般参加者にほとんど順番が回らずに終わってしまったという後味の悪さもありました。
結局、全てのチャレンジにおいて滑り出しからラリーが止まってしまい、ほとんどの一般人参加者には順番が回ってこないという事態に。出演者陣も真剣に取り組んでいましたが、番組を牽引する側である出演者らのミスは後味の悪い結果とな…
この状況で失敗したタレントを執拗にイジる姿は、真剣に準備してきた一般参加者の気持ちを踏みにじる行為と受け取られても仕方がなかったでしょう。「失敗を笑う文化」から「挑戦を称える文化」へ。視聴者の求めるものが変化していることに、番組側も演者側も、もっと敏感であるべきだったのかもしれません。
コンプライアンスの壁とテレビの“安全運転”
一方で、テレビ業界自体も大きな変化の渦中にあります。視聴者からのクレームを過度に恐れるあまり、コンプライアンス遵守が最優先され、表現はどんどん“安全運転”になっています。毒舌や過激なイジりで人気を博した芸人たちも、その芸風をマイルドにせざるを得ない状況です。
この流れの中で、上田氏の「イジり」は、ある意味で時代から取り残された“遺物”のように見えてしまった側面もあります。かつては彼の真骨頂であったはずの鋭いツッコミが、現代のフィルターを通すと、単なる「配慮に欠けた乱暴な言葉」に聞こえてしまう。このギャップこそが、今回の炎上の根源にあるのではないでしょうか。
上田晋也は変わったのか?他番組で見せる『神がかりな司会術』との乖離
今回の件で「上田晋也は劣化した」「もともと嫌いだった」という声も聞かれます。しかし、本当にそうでしょうか。彼の司会者としての実力は、多くの人が認めるところです。『しゃべくり007』で見せる、百戦錬磨の芸人たちを自在にコントロールする手腕。『Going!Sports&News』での、アスリートへの敬意に満ちた的確なインタビュー。その卓越した司会術は、まさに「神がかり」と評されてきました。
成功体験が招いた“判断ミス”
では、なぜ『24時間テレビ』では失敗してしまったのか。ここに、「天才司会者ゆえの慢心」や「成功体験が招いた判断ミス」という視点を持ち込むことができます。長年の経験で培われた「この場面では、こうすれば盛り上がる」という成功の方程式。彼は、それを無意識に『24時間テレビ』という特殊な舞台にも当てはめてしまったのではないでしょうか。
彼のイジり芸は、気心の知れた芸人仲間や、バラエティの文脈を理解しているタレントとの間で交わされる「プロレス」的なやり取りにおいて、その真価を発揮します。相手が必ず面白く返してくれるという信頼があるからこそ、多少手荒なツッコミも成立するのです。しかし、今回は相手が違いました。真剣な挑戦の場にいる一般参加者、パラアスリート、そして「チャリティー」という看板。そこは、彼のホームグラウンドである深夜バラエティのリングではなかったのです。
いつもの感覚で「場を温めるため」に放った言葉が、文脈を読み違えたことで“凶器”に変わってしまった。これは、彼の能力が劣化したのではなく、自らの成功体験を過信し、適用する場面を誤った「判断ミス」だったと分析できます。どんな天才にも、アウェーの戦いはあるのです。
番組構造が引き起こした悲劇か?
さらに言えば、この悲劇は上田氏一人の責任なのでしょうか。「感動」を主軸にしながら、視聴率獲得のために人気タレントを集めてバラエティ企画を行う。『24時間テレビ』が内包するこの根本的な矛盾が、司会者に「感動の案内人」と「笑いの仕掛け人」という二律背反の役割を強いています。この歪な番組構造が、上田氏のような百戦錬磨の司会者でさえも判断を誤らせる土壌を作ってしまった、という見方もできるでしょう。
結論:テレビと視聴者が向き合うべき『新しい笑いのカタチ』
上田晋也氏の『24時間テレビ』での炎上は、私たちに多くの問いを投げかけています。この一件を単なる個人の失態として消費し、彼を断罪して終わらせるのは簡単です。しかし、それでは何も生まれません。私たちはこの教訓から、未来のテレビと笑いのあり方を考えるべきです。
テレビ制作者は、番組の趣旨や社会的文脈を深く理解し、それに最も適した演出とキャスティングを行う必要があります。「とりあえず人気者を」という安易な起用が、今回のような悲劇を生む可能性があることを、肝に銘じるべきでしょう。
演者側もまた、変化を求められています。誰かを傷つける可能性のある「イジり」や「毒舌」に代わる、新しい笑いの武器を磨く時が来ています。それは、相手へのリスペクトに基づいた共感の笑いかもしれませんし、知性や教養に裏打ちされたユーモアかもしれません。
そして最後に、私たち視聴者も問われています。SNSで感情的に批判の石を投げるだけでなく、なぜ自分が不快に感じたのか、どうすればもっと良い番組になるのかを建設的に考える姿勢が必要です。メディアとの健全な向き合い方、すなわちメディアリテラシーが、これまで以上に重要になっているのです。
今回の炎上は、テレビと視聴者の関係が新たなフェーズに入ったことを示す象徴的な出来事でした。この痛みを乗り越えた先に、誰もが心から笑え、誰も傷つかない、より成熟したエンターテインメントの世界が待っていることを願ってやみません。

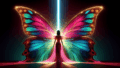

コメント