「関税は外国が払う」は本当?トランプ氏の“嘘”と、あなたの財布を守る経済リテラシー
米国人が『関税は誰が払うか』を今さら知った衝撃
「関税は誰が払うものなのか、我々はようやく知った」
これは、世界有数の経済紙ウォール・ストリート・ジャーナル(WSJ)に掲載された社説の見出しです。経済のプロフェッショナルである彼らが、まるで新しい発見のように語るこの言葉。にわかには信じがたいかもしれませんが、これが現代アメリカで起きている現実の一端なのです。
元大統領ドナルド・トランプ氏は、長年にわたり「関税は中国などの輸出国が支払うもので、アメリカ国民の負担にはならない」と公言してきました。このシンプルで力強いメッセージは多くの支持者の心を掴みましたが、その裏で静かに、しかし確実に、アメリカ国民の生活費は上昇していました。
そして今、多くの人々がその「勘違い」に気づき始めています。スーパーのレジで、レストランの会計で、じわじわと財布を圧迫する物価上昇。その原因の一つが、自分たちが払うはずはないと思っていた「関税」だったとしたら…?
この記事では、「なぜ経済大国アメリカでこんな壮大な誤解が広まってしまったのか?」という謎を解き明かしていきます。関税の基本的な仕組みから、トランプ氏の巧みなプロパガンダ戦略、そしてこの出来事が私たち日本人に突きつける「対岸の火事ではない」教訓まで。あなたの生活を守る「武器」となる経済リテラシーを、一緒に学んでいきましょう。
子供でもわかる関税の仕組み
そもそも「関税」とは何なのでしょうか?複雑に思えるかもしれませんが、仕組みは至ってシンプルです。ここでは、商品の流れとお金の流れを追いながら、その基本構造を解説します。
関税を支払うのは「輸入する人」
結論から言えば、関税を支払うのは、商品を輸入する国の人や企業です。輸出する側ではありません。これは世界共通のルールであり、日本の税関も次のように説明しています。
輸入貨物には、無税品でない限り、原則としてそれぞれの実行税率により関税が課されます。
三菱UFJ銀行のコラムでも、この点は明確に述べられています。
関税の納付者は、対象となる貨物の輸入者です。輸入品を海外から自国へ持ち込む企業や個人が、輸入国の税関へ関税を納めます。
【モデルケース】中国製スマホが米国で売られるまで
具体的な流れを、仮のモデルケースで見てみましょう。仮に米国が中国製のスマートフォンに25%の関税をかけるとします。
- ステップ1:製造
中国の工場が、1台400ドルのスマートフォンを製造します。 - ステップ2:輸入
米国のIT企業(輸入業者)が、このスマートフォンを400ドルで買い付けます。 - ステップ3:関税の支払い
商品が米国の港に到着した際、米国のIT企業は米国政府(財務省)に対し、商品価格の25%にあたる100ドル(400ドル × 25%)を関税として支払います。この時点で、中国の工場はすでにお金(400ドル)を受け取っており、この関税の支払いには一切関与しません。 - ステップ4:コストの上昇
米国のIT企業にとって、このスマートフォンの仕入れコストは、商品代400ドル+関税100ドル=合計500ドルになります。 - ステップ5:価格転嫁と最終的な負担
IT企業は、この500ドルのコストに自社の利益を上乗せして、国内の小売店に卸します。そして最終的に、米国の消費者が店舗でそのスマートフォンを購入します。つまり、関税分の100ドルは商品価格に上乗せされ、最終的に米国の消費者が負担することになるのです。
このように、関税は輸入国の政府にとって重要な税収源となる一方で、国内の物価を押し上げる要因にもなります。トランプ氏の主張とは真逆で、関税は「外国から富を奪う」魔法の杖ではなく、「自国の消費者が負担する税金」なのです。
トランプはなぜ『嘘』をついたのか?その巧妙なプロパガンダ戦略
経済の基本を理解していれば、「関税は輸出国が払う」という主張が事実に反することは明らかです。では、なぜトランプ氏はこれほどまでに、この「嘘」を繰り返し訴え続けたのでしょうか。そこには、彼の支持層の心理を巧みに突いた、計算高いプロパガンダ戦略がありました。
「強いアメリカ」を演出する分かりやすい物語
トランプ氏のメッセージは、常にシンプルで、敵と味方が明確です。「アメリカの富が中国のような国に不当に奪われている。だから、彼らに関税を払わせて、その富をアメリカに取り戻すのだ」という物語は、経済の複雑な理屈を抜きにして、感情に直接訴えかけます。
彼は大統領在任中から、一貫してこう主張してきました。
「中国が米国に関税を払っているのであって、我々の消費者ではない」
この言葉は、経済的な正しさよりも、「我々は被害者であり、トランプがその問題を解決する強いリーダーだ」という政治的メッセージとして絶大な効果を発揮しました。支持者たちは、自分たちの生活が苦しい原因を「外国」という分かりやすい敵に見出し、トランプ氏に関税という名の「制裁」を科す姿を喝采したのです。
トランプ流「単純化の魔力」の心理学
なぜ人々は、複雑な真実よりも単純な嘘に惹かれてしまうのでしょうか。ここには心理学的なメカニズムが働いています。
- 認知的な怠惰: 人間の脳は、できるだけエネルギーを使わないようにできています。「関税は自国消費者の負担となり、物価上昇や企業のコスト増に繋がるが、長期的には国内産業を保護する効果も期待できる…」という複雑な現実を理解するより、「外国が払う税金だ」という単純な話を受け入れる方が遥かに楽なのです。
- 確証バイアス: 人は、自分の信じたい情報を無意識に探してしまう傾向があります。「トランプは我々の味方だ」と信じている支持者にとって、「関税は外国が払う」という言説は、その信念を補強する心地よい情報です。そのため、メディアや専門家がそれを否定する情報を提示しても、「フェイクニュースだ」と一蹴し、耳を貸そうとしません。
- 内集団バイアス: 「我々(アメリカ国民) vs 彼ら(外国)」という対立構造を作ることで、集団内の結束を強める効果があります。共通の敵を設定することは、支持者を団結させるための古典的かつ強力な政治手法です。
トランプ氏は、この「単純化の魔力」を天才的に利用しました。彼の言葉は経済学の教科書には反していても、人々の感情と心理を揺さぶる「政治の教科書」としては、極めて効果的だったと言えるでしょう。
データで見る、関税が米国人の財布を直撃した現実
「関税は外国が払う」という物語が浸透する一方で、現実の経済データは全く異なる事実を突きつけていました。トランプ政権下で課された様々な関税は、アメリカの企業や消費者の懐を確実に蝕んでいったのです。
苦し紛れの側近と、メディアの追及
この矛盾に最も苦しんだのが、経済を担当する政権の側近たちです。元記事で紹介されているスコット・べッセント財務長官(※元記事の役職名を引用)とキャスターのやり取りは、その苦境を象徴しています。
キャスターが「誰が財務省に小切手を書くのですか?」と本質を突くと、長官は「代替調達が可能だ」などと論点をずらそうとします。しかし、執拗な追及の末、ついに「(小切手を書くのは)米国の港で貨物を受け取る人です」と、つまり米国の輸入業者であることを認めざるを得ませんでした。このやり取りは、「トランプの関税は米国人が払うものと財務長官が認めた」と大きく報じられ、政権の説明の矛盾を露呈させました。
洗濯機から鉄鋼まで、値上がりの連鎖
実際に、関税は米国の物価にどのような影響を与えたのでしょうか。
- 洗濯機: トランプ政権は2018年、輸入洗濯機に最大50%のセーフガード(緊急輸入制限)関税を発動しました。シカゴ大学の研究によると、これにより洗濯機の平均価格は約12%上昇し、米国の消費者は年間15億ドルの追加負担を強いられたと試算されています。
- 鉄鋼・アルミニウム: 2018年に発動された鉄鋼(25%)とアルミニウム(10%)への追加関税は、自動車や建設、機械など幅広い産業のコストを押し上げました。米国の鉄鋼メーカーは一時的に潤ったものの、それを使用する遥かに多くの企業がコスト増に苦しみ、結果的に製品価格の上昇という形で消費者に転嫁されました。
- 対中関税: 最も影響が大きかったのが、中国からの輸入品に対する大規模な関税です。ニューヨーク連銀の調査では、対中関税によって米国の輸入企業と消費者は、年間で数百億ドル規模の損失を被ったと分析されています。
冒頭で紹介したWSJの社説は、こうした現実を的確に指摘しています。
「『経済は絶好調だ』と言い張っても、スーパーやファミリーレストランでの現実がそれと矛盾すれば、有権者は信じない」
どんなに力強い言葉で国民を鼓舞しても、日々の買い物のレシートに刻まれる数字という「現実」には勝てないのです。この生活実感との乖離が、多くの人々を目覚めさせるきっかけとなりました。
これは対岸の火事ではない。日本人が学ぶべきメディアリテラシー
「アメリカ人はどうしてこんな簡単なことを見抜けなかったのか」と、対岸の火事のように感じるかもしれません。しかし、政治家が経済の基本原則を捻じ曲げ、国民をミスリードしようとする構図は、決して他人事ではありません。この一件から、私たち日本人が学ぶべき教訓は非常に大きいと言えます。
なぜ多くの米国人は信じてしまったのか?
背景には、単なる知識不足だけではない、根深い社会問題があります。
- 社会の分断: 近年のアメリカでは、政治的な信条による社会の分断が深刻化しています。支持する政党やメディアによって見る世界が全く異なり、自分の信じる「事実」だけが流通する「エコーチェンバー現象」が起きています。
- メディア環境の変化: ソーシャルメディアの台頭により、誰もが情報発信者になれる一方、事実確認が不十分な情報や意図的な偽情報が拡散しやすくなりました。アルゴリズムはユーザーが見たい情報を優先的に表示するため、ますます考えが偏りやすくなります。
- 経済教育の課題: 義務教育の段階で、税金や国際貿易といった実生活に直結する経済の仕組みを学ぶ機会が十分でないことも、こうした誤解が広まる土壌となっている可能性があります。
日本の消費税と「負担者」論争
この構図、どこかで見覚えはないでしょうか。実は日本でも、消費税を巡って似たような議論が過去にありました。
消費税増税の際、「消費税は事業者が預かって納める『預り金』ではなく、事業者の売上に対する税金であり、価格に転嫁するかは事業者の自由。だから消費者の負担ではない」といった趣旨の主張が一部でなされました。これは、税の最終的な負担者(担税者)と納税義務者を意図的に混同させるロジックです。
法律上、消費税を国に納めるのは事業者(納税義務者)ですが、その原資は商品やサービスの価格を通じて消費者が支払っています(担税者)。関税のケースと同様に、税の負担が最終的に誰の懐から出ていくのかという経済的な実態を無視した、政治的な言説と言えます。
このように、「誰が税を負担するのか」というテーマは、国民の反発をかわしたい政治家によって、意図的に複雑化・歪曲されやすいのです。
情報の真偽を見抜くために
政治家の発言やメディアの情報を鵜呑みにせず、自分の頭で考えるためにはどうすればいいのでしょうか。
- 一次情報を確認する: 可能であれば、政府の公式発表や統計データ、研究機関のレポートなど、元の情報にあたる癖をつけましょう。
- 複数の情報源を比較する: 一つのメディアや論者の意見だけでなく、対立する意見も含めて複数の情報に触れることで、物事を多角的に見ることができます。
- 「誰が得をするか?」を考える: その発言や情報が広まることで、誰が政治的・経済的に利益を得るのかを考えてみると、裏にある意図が見えてくることがあります。
アメリカで起きた「関税の勘違い」は、私たちにとって、情報の受け手としての責任とスキルを問い直す貴重なケーススタディなのです。
まとめ:経済知識は、あなたの生活を守る『武器』になる
今回は、トランプ氏の関税を巡る言説から、経済の基本、プロパガンダの手法、そして私たちに必要なメディアリテラシーまでを掘り下げてきました。
本記事のポイントを振り返ってみましょう。
-
- 関税の基本: 関税は輸入国の輸入業者が自国政府に支払い、そのコストは商品価格に上乗せされ、最終的にその国の消費者が負担する。
- トランプ氏の戦略: 「関税は外国が払う」という嘘は、経済的には誤りだが、「強いアメリカ」を演出し、分かりやすい敵を作ることで支持者を熱狂させる強力な政治的メッセージだった。
- 単純化の魔力: 人々は複雑な真実よりも、認知的に楽で感情に訴える単純な物語を信じやすい傾向がある。
- 現実の影響: データは、関税が米国の物価を押し上げ、消費者や多くの企業の負担を増やしたことを示している。
- 私たちへの教訓: この事例は対岸の火事ではない。政治家の言葉を鵜呑みにせず、経済の基本原則に立ち返り、情報の真偽を見抜くリテラシーが不可欠である。
「経済は難しくてよくわからない」と感じるかもしれません。しかし、今回の事例が示すように、経済の知識は、専門家だけのものではなく、私たちの生活や財産を政治的な思惑から守るための強力な『武器』になります。
日々のニュースに触れるとき、政治家が声高に何かを主張しているとき、少しだけ立ち止まって「そのお金は、結局誰が払うのだろう?」と考えてみてください。その小さな疑問こそが、誤った情報に流されず、賢明な判断を下すための第一歩となるはずです。

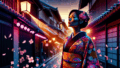

コメント