この記事のポイント
- EXIT兼近氏の「遅刻を責める人は能力が低い」という発言は、現代の働き方における「成果主義」と「時間厳守」という価値観の対立を象徴しています。
- 遅刻を執拗に責める人の深層心理には、単に時間を守りたいだけでなく、自分の権威性や場のコントロール感を維持したいという欲求が隠れている場合があります。
- 時間に対する価値観は、国や文化、さらには業界(芸能界、IT業界、一般企業など)によって大きく異なり、画一的な「正解」は存在しません。
- 重要なのは善悪を問うことではなく、個人と組織の両面から「遅刻が問題にならない仕組み」を構築し、チーム全体の生産性を高めることです。
導入:なぜ今、EXIT兼近の「遅刻論」がこれほど物議を醸すのか?
「遅刻を責める人は、能力低いなと思う」
お笑いコンビEXITの兼近大樹氏がテレビ番組で放ったこの一言が、今、大きな波紋を広げています。SNSでは「よくぞ言った!」という称賛から、「社会人としてありえない」という批判まで、まさに賛否両論の嵐。この議論に油を注ぐかのように、過去には実業家のひろゆき氏も「遅刻しないだけで自分の地位が安泰だと誤解してる」といった趣旨の発言をしており、「遅刻」というテーマが根深い問題であることが浮き彫りになりました。
それに対して、兼近さんが持論を展開。遅刻する人のことはなんとも思わないとしたうえで、『遅刻を責める人は能力低いなと思う』とコメントしました。『その時間なんかしたほうがよくない?』『はっきりと言えることは、遅刻を許さない人は仕事ができないということ』と、かなり強めに主張したのです。
なぜ、たかが「遅刻」の話が、これほどまでに私たちの心をざわつかせるのでしょうか?
それは、この問題が単なる時間管理の話ではないからです。遅刻する同僚にイライラした経験、寝坊して罪悪感に苛まれた朝、5分前行動を徹底するあまり息苦しさを感じる毎日……。この論争は、私たちが職場で日々直面しているストレスや、世代・立場によって異なる「正義」のぶつかり合いを映し出す鏡なのです。
この記事では、兼近氏の発言をきっかけに再燃した「遅刻論争」を徹底的に深掘りします。単に「遅刻は良いか悪いか」を議論するのではなく、対立する双方の心理的背景から、文化や業界による価値観の違い、そして明日から使える具体的なアクションプランまで、多角的な視点からこの問題に切り込んでいきます。この記事を読み終える頃には、あなたの「時間」に対する考え方が少し変わっているかもしれません。
【徹底解剖】「遅刻許容派 vs 絶対悪派」それぞれの正義と心理的背景
この論争は、大きく分けて「遅刻許容派」と「遅刻絶対悪派」の2つの立場に分かれます。両者の主張はなぜこうも食い違うのでしょうか。それぞれの正義と、その裏にある心理を紐解いていきましょう。
遅刻許容派の主張:「結果が全て」という成果主義の論理
兼近氏やひろゆき氏に代表される「許容派」の主張の根幹にあるのは、「プロセスよりも結果が重要」という成果主義的な考え方です。
彼らの主張をまとめると、以下のようになります。
- 優秀な人ほど多忙:多くの仕事を抱え、スケジュールが詰まっているため、少しのズレが遅刻に繋がるのは仕方ない。
- 時間厳守は目的ではない:時間を守ること自体に価値はなく、最終的に良いアウトプットを出すことの方が重要。
- 待つ時間を有効活用すればいい:人を待たせるのは良くないが、待っている側もその時間を無駄にせず、別の作業をすれば生産性は落ちない。
ひろゆき氏は「社会では、時間を守るより良い結果が重要になる」と語っています。これは、特にIT業界やクリエイティブな職種など、個人のスキルや成果が直接評価に結びつきやすい環境で支持されやすい考え方です。彼らにとって、定時に出社することよりも、画期的なアイデアを出すことや、高い品質のコードを書くことの方がはるかに価値があるのです。
遅刻絶対悪派の主張:「時間は信頼の礎」という協調性の論理
一方、SNSでの反応の多くを占めたのが「絶対悪派」です。彼らの主張は、「時間は個人のものではなく、チームや相手との共有財産である」という考えに基づいています。
主な主張は以下の通りです。
- 時間は有限な資源:他人の時間を一方的に奪う「時間泥棒」であり、相手への敬意を欠いた行為だ。
- 信頼関係の崩壊:「時間を守る」という基本的な約束を守れない人は、他の仕事においても信用できない。
- チームワークの阻害:一人の遅刻が、会議の開始遅れやプロジェクト全体の遅延に繋がり、周囲の士気を下げる。
《自分1人の仕事ならば好きにすれば良いが、他の人との仕事ならば時間泥棒に過ぎないよ》というネット上のコメントは、まさにこの考え方を象徴しています。特に、多くの人が連携して動く製造業や、顧客とのアポイントメントが重要な営業職など、チームでの協調性や規律が求められる職場で強く支持される傾向があります。
【独自視点】なぜ人は「遅刻」を執拗に責めるのか?
では、なぜ一部の人は遅刻に対して、必要以上に厳しく、感情的に反応してしまうのでしょうか。もちろん、実務的な迷惑を被っている場合も多いでしょう。しかし、その怒りの根源には、さらに深い心理が隠れている可能性があります。
それは、「コントロール感の喪失」への恐れです。
時間を守る、ルールに従うといった行為は、組織や社会の秩序を保つための基本的な約束事です。遅刻という行為は、この「皆が守るべき約束事」を破る行為に他なりません。遅刻を責める人は、この秩序が乱されること、つまり自分の予測可能な範囲(コントロールできる範囲)から逸脱する事態を極端に嫌う傾向があるのかもしれません。
彼らが本当に守りたいのは、5分や10分という「時間」そのものではなく、「ルールは絶対である」という秩序や、「自分は正しくルールを守っている」という自らの正当性、そしてその場を支配する自らの権威性なのかもしれません。遅刻してきた部下を皆の前で叱責する上司は、時間の大切さを説いているように見えて、実は「この場のルールを決めるのは私だ」という無言のメッセージを発しているのです。
その常識、日本だけ? 海外事例から見る「時間」という文化
「時間に厳しい日本人」というイメージは、海外でも広く知られています。電車の秒単位での正確な運行は、その象徴と言えるでしょう。しかし、この日本の常識は、世界的に見れば必ずしもスタンダードではありません。
「on time」は当たり前じゃない?世界の多様な時間感覚
世界に目を向けると、「時間」の捉え方は実に多様です。
- ラテン文化の「マニャーナ(Mañana)」:スペイン語で「明日」を意味するこの言葉は、「急がずに、また今度」というニュアンスで使われます。約束の時間に多少遅れるのは日常茶飯事で、時間よりもその場の人間関係や会話を優先する文化です。
- 中東の「インシャラー(Inshallah)」:「神が望むなら」という意味のアラビア語で、物事が予定通りに進むかどうかは神のみぞ知る、という価値観が根底にあります。そのため、未来の約束に対して日本人のような確実性を求めません。
もちろん、これらの国々でもビジネスのグローバル化に伴い時間厳守の意識は高まっていますが、根底にある時間感覚は日本とは大きく異なります。彼らにとって、時間は絶対的なものではなく、より流動的で柔軟なものなのです。
シリコンバレーに学ぶ「成果」を最大化する時間の使い方
一方、世界の最先端を走るアメリカのシリコンバレーでは、また違った時間感覚が主流です。彼らは決して時間にルーズなわけではありません。むしろ、生産性を最大化するために、時間の使い方を徹底的に合理化しています。
フレックスタイム制や完全リモートワークが普及し、「何時に会社に来るか」よりも「いつまでに何を成し遂げるか」が問われます。朝のコアタイムに縛られることなく、エンジニアが最も集中できる深夜にコードを書いても、誰も文句は言いません。そこにあるのは、ひろゆき氏の主張とも通じる、徹底した成果主義です。重要なのは「規律」ではなく「アウトプット」なのです。
日本の時間厳守の文化は、集団で同じ作業を行う工場労働や農作業において生産性を最大化するための、非常に優れたシステムでした。しかし、個人の創造性が求められる現代の働き方において、その「常識」は果たして絶対的なものなのでしょうか。海外の事例は、私たちの固定観念に揺さぶりをかけます。
【明日から使える】「遅刻問題」でもう悩まないための実践的アクションプラン
価値観の議論だけでは、職場の問題は解決しません。ここでは、個人レベルと組織レベルで、明日から実践できる具体的なアクションプランを提案します。
個人でできること:遅刻する側・される側のストレス軽減術
まずは、自分自身でコントロールできることから始めましょう。
【遅刻しがちなあなたへ】
- 原因を分析する:なぜ遅刻するのか、自己分析してみましょう。単なる寝坊なのか、準備に時間がかかりすぎる完璧主義なのか、あるいはADHDのような発達特性が関係している可能性も。原因が分かれば対策も立てやすくなります。
- 「逆算」と「バッファ」を徹底する:家を出る時間から逆算してアラームを複数設定する、突発的なトラブルに備えて常に15分以上の「バッファ(余裕)」を持った計画を立てる、などを習慣化しましょう。
- 正直に、迅速に連絡する:遅刻が確定した時点で、すぐに連絡を入れ、正直な理由と到着予定時刻を伝えること。誠実な対応が、失った信頼を少しでも取り戻す鍵です。
【待たされることが多いあなたへ】
- 待ち時間を「ボーナスタイム」と捉える:イライラして待つ時間は無駄でしかありません。最初から「5分は遅れてくるかも」と想定し、その時間を読書やメールチェック、タスク整理など、自分のための「ボーナスタイム」と位置づけましょう。
- 「I(アイ)メッセージ」で伝える:「なぜ遅刻するんだ!」(Youメッセージ)と相手を責めるのではなく、「あなたが遅れると、私は会議の準備ができなくて困る」(Iメッセージ)と、自分がどう感じ、どんな影響があるかを伝えましょう。相手も受け入れやすくなります。
組織でできること:遅刻を「問題化」させない仕組み作り
個人の努力には限界があります。遅刻が頻発する、あるいは遅刻に対する不満が蔓延している職場では、組織としての仕組み作りが不可欠です。
- ルールの明確化と共有:何分以上の遅れを「遅刻」とするのか、遅刻が評価にどう影響するのか、といったルールを明確にし、全員で共有します。曖昧さが、不公平感や人間関係の軋轢を生みます。
- 業務フローの見直し:「〇〇さんが来ないと会議が始まらない」といった属人性の高い業務フローを見直しましょう。アジェンダや資料を事前に共有し、全員が揃わなくても議論を進められるようにするなど、個人の遅刻がチーム全体の生産性を下げない工夫が重要です。
- 「心理的安全性」の確保:電車の遅延や子供の急な発熱など、やむを得ない遅刻は誰にでも起こり得ます。そうした際に、正直に理由を報告でき、チームメンバーが「お互い様」とサポートし合えるような「心理的安全性」の高い職場環境を作ることが、結果的に無用な対立を防ぎます。
結論:「遅刻」は悪か? この論争が私たちに問いかける、これからの働き方
さて、ここまで長々と議論してきましたが、結局のところ「遅刻」は悪なのでしょうか。
結論から言えば、この問題に唯一絶対の答えはありません。この論争の本質は、単なる時間管理の是非ではなく、「個人の成果」と「組織の規律」という2つの価値観の、どちらをより重視するのかという、現代の働き方が直面する大きな問いなのです。
ここで重要なのが、兼近氏のいる「お笑い界」やひろゆき氏のいる「IT業界」、そして多くの読者が属するであろう「一般企業」では、「遅刻」の持つ意味が全く異なるという視点です。元記事でも触れられていたように、お笑いの世界では、遅刻が笑いのネタになり、注目を集める「おいしい」状況になり得ます。個人のキャラクターや才能が何よりも重視される世界です。IT業界では、先述の通り、場所や時間に縛られない成果主義が浸透しています。
しかし、多様な人々が協力して価値を生み出す多くの企業では、成果と規律のバランスが求められます。一人の天才的な成果が、チーム全体の信頼関係や秩序を乱してまで許容されるべきかは、慎重に判断しなければなりません。
この「遅刻論争」は、私たち一人ひとりに問いかけています。
「あなたの職場が本当に大切にしている価値は何か?」
「時間厳守というルールの先に、チームとして達成したい本当の目標は何か?」
遅刻を無条件に許容する必要はありません。しかし、遅刻した人を感情的に断罪する前に、一度立ち止まってみませんか。その遅刻は、なぜ起きたのか。それによって、チームの目標達成にどれだけの支障が出たのか。そして、それを防ぐために、もっと良い仕組みは作れないのか。
EXIT兼近氏の投げかけた一石は、私たちが自らの働き方や組織のあり方を、改めて見つめ直す絶好の機会を与えてくれたのかもしれません。

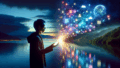
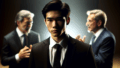
コメント