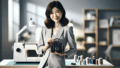「醜い生き物」という呪文――日本保守党が仕掛ける”言葉のプロレス”と、我々が支払う代償
「どこまでも醜い、奇妙な生き物」。日本保守党の北村晴男参院議員が、石破茂首相に向けて放った言葉だ。この一撃に、橋下徹元大阪府知事が「誹謗中傷が酷すぎる」「公人の自覚を」と噛みつき、リングは一気に熱を帯びた(Yahoo!ニュース, [1])。世間の関心は「これは許される批判か、許されざる誹謗中傷か」という一点に集約されていく。だが、この分かりやすい対立構造の裏で、もっと厄介で根深い問題が進行していることに、我々は気づいているだろうか。
この論争の本質は、言葉の品位や公人の定義をめぐる法廷闘争ではない。これは、SNSという新たなコロッセオで繰り広げられる、現代政治のショービジネス化そのものである。そして我々有権者は、その熱狂の観客であると同時に、知らず知らずのうちに、民主主義の質という見えざるチケット代を支払わされているのかもしれない。
■ 「言葉のプロレス」が覆い隠す、政策不在のリング
今回の騒動を注意深く観察すると、そこには極めて現代的な政治戦略が透けて見える。それは、複雑な政策課題を脇に追いやり、感情に訴えかける言葉で「敵」を仕立て上げ、注目(アテンション)を独占するという手法だ。
敵を設定し、感情を刈り取る「アテンション・エコノミー」の政治
日本保守党は、石破首相という格好の「敵」を設定した。そして、「醜い」「奇妙な生き物」という、生理的嫌悪感すら誘う強烈な言葉を投げつけた。これは政策論争ではない。これは、SNSのアルゴリズムが好む、感情的で、過激で、拡散されやすいコンテンツの生成である。朝日新聞GLOBE+が指摘するように、SNS上では「過激な言説や真偽不明の情報、センセーショナルなものほど拡散しやすい」([2])。日本保守党の戦略は、この「アテンション・エコノミー」のルールに極めて忠実だ。
さらに深刻なのは、北村氏の投稿が、ネット掲示板の声をまとめただけの信憑性の低いサイトを引用していた点だ。報道によれば、元の投稿にはXのコミュニティノートで「石破首相が発言したという内容は示されていません」と注釈がつけられている(Yahoo!ニュース, [3])。事実(ファクト)の正確性よりも、感情を増幅させる「物語(ナラティブ)」を優先する。これは、まさにポピュリズムが「敵」への敵意を刺激して熱狂を生み出す典型的な手口と重なる(東京新聞, [4])。
💡 ポイント
日本保守党の戦略は、単なる失言ではない。それは、SNS時代の情報流通メカニズムを計算に入れた、高度な「注目獲得戦略」である。政策論争を避け、人格攻撃に近い言葉で「敵」を作り出すことで、政治的エネルギーを創出している。

議論のすり替え:「誹謗中傷」論争という巧妙な罠
橋下氏の「税金で活動する公人としての自覚を」という批判([1])は、一見すると正論だ。公人への批判であっても、人格を貶める侮辱表現は許されない。法的な観点からも、「『最低な人間』『恥知らず』といった表現はアウト」であり、「事実と意見を明確に分ける」必要があると専門家は指摘する(note, [5])。
政治家・公務員などの公人は、公的な言動や職務に対する批判は、表現の自由として広く認められます。ただし、侮辱や誹謗中傷、感情的な悪口、私生活への言及があれば、保護されなくなります。
出典: [5]
しかし、この「誹謗中傷か否か」という論争に社会の注目が集中すること自体が、日本保守党が仕掛けた術中にはまっている状態ではないだろうか。この論争は、より本質的な問いから我々の目を逸らす煙幕として機能する。例えば、先の参院選で与党が過半数を割り込んだという「民意」をどう受け止めるのか。物価高騰に喘ぐ国民生活に、政府はどう応えるのか。そうした喫緊の政策課題は、”言葉のプロレス”のリングの下へと追いやられてしまう。
■ 「保守」の断層:エスタブリッシュメント vs アウトサイダー
この対立は、単なる党派間の争いではない。それは、現代日本における「保守」そのものが抱える深刻な断層を露呈させている。なぜ、攻撃の矛先が石破首相に向けられたのか。その理由を探ると、新しい政治の対立軸が見えてくる。
なぜ石破茂は「醜い」と断じられたのか
石破茂という政治家は、長年自民党内で「異端」「党内野党」として振る舞い、主流派を批判することで一定の存在感を保ってきた。しかし、首相の座に就いた瞬間、彼は紛れもない「エスタブリッシュメント(既成勢力)」の頂点に立った。日本保守党から見れば、その経緯は「変節」であり、敵であったはずの自民党中枢と一体化した姿は、まさに「醜い」ものとして映るのだろう。
彼らは、石破氏の複雑な政治的立ち位置や、漸進的な改革を目指す姿勢を「分かりにくさ」として切り捨て、「純粋な保守」「筋を通す存在」としての自らを際立たせるための鏡として利用している。百田尚樹代表が「容姿ではなく生き方や政治姿勢への言及だ」と反論したのは、この戦略を裏付けている。彼らにとって石破氏は、打倒すべき「古い政治」の象徴なのだ。
▼ 2つの「保守」の衝突 ▼
【エスタブリッシュメント保守】(石破氏)
伝統的な議会制民主主義の枠内で現実的な解を求める
vs
【アウトサイダー保守】(日本保守党)
既存の秩序や作法を破壊し、SNSを通じて直接的な民意に訴えかける
昨日までのアウトサイダー、今日のモラリスト
興味深いのは、今回「公人の品位」を説く側に回った橋下徹氏の立ち位置だ。彼自身、かつては大阪府知事・市長として、既存政党やメディアを「敵」とみなし、過激ともいえる言葉で民衆の支持を集めた、典型的なアウトサイダーだった。その彼が、今や「税金で飯を食う公人」の規範を説く。これは単なる心変わりではない。政治の舞台における「アウトサイダー」の座が、より過激なプレイヤー(日本保守党)に取って代わられ、相対的に彼が「エスタブリッシュメント」側に押し出されたことを示している。
この構造変化は、政治の対立軸が「保守 vs リベラル」という旧来のイデオロギー対立から、「エスタブリッシュメント vs アンチ・エスタブリッシュメント(ポピュリズム)」へと、静かに、しかし確実に移行しつつあることを物語っている。
■ 我々が消費する「言葉」の重い代償
この問題を「一部の過激な政治家」の言動として片付けることはできない。なぜなら、彼らを生み出し、その影響力を増幅させているのは、他ならぬ我々有権者と、我々が日常的に使うSNSというメディアだからだ。我々が何気なく消費する「言葉」には、民主主義の未来を左右するほどの重い代償が伴う。
アルゴリズムが育てる「過激な政治家」
SNSのアルゴリズムは、倫理や品位を判断基準にしない。ただひたすらに、ユーザーの反応(エンゲージメント)が高いコンテンツを優先する。政治家がこのシステムの中で注目を集めようとすれば、発言は必然的に先鋭化し、より扇情的になる。北村氏のような投稿に、我々が怒りや嘲笑、あるいは賛同の「いいね」や「リポスト」で反応するたびに、アルゴリズムは「この種のコンテンツは需要がある」と学習し、さらに多くの人々の目に触れさせる。
このフィードバックループは、熟慮や対話よりも、瞬発的な罵倒や単純なレッテル貼りを重んじる政治家を育てる温床となる。
- 政治家が過激な言葉を投稿する
- ↓
- ユーザーが感情的に反応(いいね、リポスト、コメント)する
- ↓
- アルゴリズムが投稿を拡散し、政治家の影響力が増大する
- ↓
- 政治家はさらに過激な言葉を選ぶようになる(以下、無限ループ)
我々は、自らの指先で、政治全体の質を低下させる共犯者になってはいないだろうか。
「分かりやすさ」という名の思考停止
「醜い」「奇妙」といった言葉は、極めて「分かりやすい」。それは、複雑な政治の現実を「善 vs 悪」「味方 vs 敵」という単純な二元論に還元し、我々を思考の労力から解放してくれる。だが、その「分かりやすさ」は、民主主義にとって最も危険な劇薬だ。
政治とは本来、利害の異なる多様な人々の中で、妥協点や最適解を探る、泥臭く、分かりにくいプロセスである。それを「醜い」の一言で断罪することは、そのプロセス自体を否定し、対話の可能性を閉ざす行為に他ならない。感情的な言葉の濁流に身を任せ、思考を停止した先に待っているのは、健全な批判精神が失われ、熱狂と憎悪だけが渦巻く不毛な政治空間だ。
■ 結論:誰が「醜い」のか、何を「醜く」しているのか
北村氏の発言を、単に「品位がない」と切り捨てるだけでは、何も解決しない。それは、SNSが政治を再定義し、新たなポピュリズムが根を張るという、現代社会が直面する構造的な課題から目を背ける行為だ。
この一件が我々に突きつけているのは、見世物としての「言葉のプロレス」を、安全な観客席から楽しむだけでよいのか、という問いである。リングの上で繰り広げられる罵り合いに熱狂するあまり、そのリングが立つ土台、すなわち我々の生活を支えるべき政策論争が、少しずつ浸食されている現実から、いつまで目を逸らし続けるのか。
今、我々が向き合うべきは、「誰が醜いのか」という犯人捜しではない。「何が、我々の政治をこれほどまでに醜くしているのか」という、より本質的な問いだ。その答えの一端は、政治家を映す鏡である我々自身の内側と、我々が作り上げたこの情報社会の仕組みそのものの中にあるのかもしれない。
参考資料
- [1] 橋下徹氏、日本保守党・北村晴男参院議員に苦言「誹謗中傷が酷すぎる」「税金で活動する公人としての自覚を」, Yahoo!ニュース
- [2] SNSはなぜ、過激な言説や偽情報であふれるのか 専門家に聞く, 朝日新聞GLOBE+
- [3] 日本保守党・北村晴男参院議員の「醜い、奇妙な生き物」投稿に批判殺到…百田尚樹代表「容姿への言及ではない」と反論も火に油, Yahoo!ニュース
- [4] 「敵」をつくり、あおるのが得意なトランプ氏の手法 4年前と今回は何が違うのか, 東京新聞 TOKYO Web
- [5] 【弁護士解説】どこからがアウト?政治家・公人への批判と誹謗中傷の境界線, note(Voice Japan)