導入:教室に忍び寄る「言葉」の影
「夏休み明け、学校に行くのが怖い」。もし、あなたの子どもがそう呟いたとしたら。その原因が、大人たちの世界で生まれた一つの「言葉」にあるとしたら、どうしますか?
間もなく全国の多くの学校で新学期が始まります。しかし今、教員や保護者の間で、ある言葉が子どもたちに与える影響について、静かな、しかし深刻な懸念が広がっています。その言葉とは、「日本人ファースト」です。
夏の参院選を通して社会に広まったこの言葉は、一見すると自国を大切にするポジティブな響きを持っているかもしれません。しかし、その言葉の影が、多様なルーツを持つ子どもたちが共に学ぶ教室に忍び寄ろうとしています。選挙後、X(旧Twitter)では、小学生がこの言葉を使い始めたという教員の投稿が1.4万回以上も再投稿され、多くの大人が不安を共有しました。
大人の世界の政治的なスローガンが、なぜ子どもの世界で危険な刃に変わりうるのでしょうか。そして、最も大切な我が子を、誰かを傷つける「加害者」にも、言葉によって傷つけられる「被害者」にもしないために、私たち親に、大人に、一体何ができるのでしょうか。この記事では、専門家の知見や現場の声をもとに、この根深い問題と向き合うための具体的なヒントを探ります。
そもそも「日本人ファースト」とは何か?支持と批判の構造
この問題を考える前に、まず「日本人ファースト」という言葉がどのような背景から生まれ、なぜこれほどまでに社会の注目を集めているのかを冷静に理解する必要があります。
この言葉が広く知られるきっかけとなったのは、2022年夏の参議院議員選挙で、参政党が公約のキャッチコピーとして掲げたことです。選挙期間中、街頭演説やSNSで繰り返し使われ、多くの人々の耳に届きました。
毎日新聞が選挙後に実施した世論調査では、この言葉が社会を二分している実態が浮かび上がります。参政党に「期待できる」と答えた19%の人が、その理由として「日本人ファースト」を挙げ、「日本国なので日本人ファーストは当然だ」といった声が上がりました。ここには、長引く経済の停滞やグローバル化の中で、自国の利益や文化、国民の生活を最優先に守ってほしいという切実な願いが透けて見えます。自分たちの暮らしが良くならない中で、まずは日本人を大切にしてほしい、という思いに共感する人がいるのは、ある意味で自然な感情かもしれません。
一方で、同調査では「期待できない」と答えた人が46%に上り、その理由としても「日本人ファースト」が挙げられました。その背景には、「外国人を差別する考え方に全く同意できない」といった強い懸念があります。この言葉は、特定の集団を「ファースト(第一)」と位置づけることで、必然的に「セカンド(第二)」や「サード(第三)」の存在を生み出してしまう危険性をはらんでいます。「〇〇ファースト」という言葉は、歴史的に見ても、しばしば排外主義や差別、分断と結びついてきました。
このように、「日本人ファースト」は、一方では自国を思う純粋な愛国心や生活防衛の意識に訴えかけ、もう一方では、他者を排斥しかねない危険な思想へとつながる、という極めて多面的な性格を持っています。だからこそ、この言葉を単に「良い」「悪い」で片付けるのではなく、なぜこの言葉が生まれ、支持され、そして批判されるのか、その両面の構造を理解することが、子どもたちの世界への影響を考える上での第一歩となるのです。
【専門家が解説】なぜ子どもの世界で危険なのか?
大人の世界では複雑な背景を持つ「日本人ファースト」という言葉。しかし、この言葉が子どもの世界に持ち込まれると、その意味は驚くほど単純化され、時として凶器に変わります。なぜ、子どもたちの間でこの言葉は特に危険なのでしょうか。
「からかい」という、いじめの芽
学校教育学を専門とする学習院大学の梅野正信教授は、元記事の中で「いじめは、多くが『からかい』から始まります」と警鐘を鳴らしています。子どもたちの世界では、大人の政治的な主張の複雑なニュアンスは抜け落ち、「日本人」と「そうでない人」を区別する便利な道具として使われかねません。
例えば、教室でこんな会話が生まれるかもしれません。
- 「給食のおかわり、日本人ファーストだから僕が先ね」
- 「お前、ハーフだから日本人じゃないじゃん」
- 「なんで日本語がヘタなの? 日本人じゃないから?」
最初は軽い「からかい」や「冗談」のつもりでも、言われた側の子どもにとっては、自分のアイデンティティを揺るがす深刻な言葉です。特に、外国にルーツを持つ子どもたちは、日本で生まれ育ったとしても、見た目や名前が違うだけで、こうした「からかい」のターゲットになりやすいのです。
軽くぶつかられたりたたかれたり、けられたりした。 例)遊びでプロレスや柔道、相撲などをさせられて、自分だけ技をかけられた。 通りすがりに背中をたたかれたり、 体をぶつけられたり、 足をかけられたりした。
いじめ対策に係る事例集より引用
こうした身体的ないじめも、最初は「日本人じゃないから」といった言葉の暴力から始まるケースは少なくありません。
「変えられない属性」を攻撃する残酷さ
元記事に登場したある教諭は、「本人の意思では変えようのない属性を順位付けするような言葉は、いじめのきっかけにもなる」と危惧しています。国籍やルーツ、肌の色、話す言葉。これらは、子ども自身が選んで生まれてきたわけではありません。自分ではどうすることもできない「属性」を理由に優劣をつけ、仲間外れにすることは、子どもの心を深く、永続的に傷つけます。
発達心理学的に見ても、特に小学生から中学生にかけての子どもたちは、自分がどのグループに属しているかを強く意識する「内集団バイアス」が働きやすい時期です。「自分たちは多数派(日本人)で、あの子は少数派(外国人)」という単純な線引きは、いじめの構造を簡単に作り出してしまいます。そこに「ファースト」という、多数派の行動を正当化するかのような言葉が加われば、いじめはさらにエスカレートしかねません。
歴史を振り返っても、特定の政治スローガンが子どもたちの間で単純化され、同調圧力や排斥の道具として使われた例は数多くあります。大人たちが社会で繰り返し使う言葉は、子どもたちにとって「使っても良い言葉」としてお墨付きを与えられたようなもの。だからこそ、大人はその影響にもっと自覚的になる必要があるのです。
【今日から家庭でできること】子どもを「加害者」にも「被害者」にもしない対話術
では、この難しい問題について、家庭でどのように子どもと向き合えばよいのでしょうか。大切なのは、頭ごなしに禁止したり、一方的に教え込んだりすることではありません。子ども自身の心に「なぜ、それは良くないのか」を考え、共感する力を育む対話です。ここでは、すぐに実践できる具体的な対話のヒントを提案します。
ステップ1:まずは親が冷静に、フラットな姿勢で聞く
もし自分の子どもが「日本人ファースト」という言葉を口にしたら、親としては動揺してしまうかもしれません。しかし、ここで感情的に叱りつけるのは逆効果です。
学校側やいじめ被害者と称する子どもの親から、自分の子どもがいじめの加害者であると告げられたら、まず冷静になって子どもと話をすることが大切です。親としては、「自分の子どもがいじめをするわけがない」と考えたくなるかもしれません。しかし、そのような気持ちはいったん横に置き、まずは客観的な事実が何であるかを把握することに努めるべきです。
これは加害者になった場合の対応ですが、問題の言葉を口にした時も同じです。まずは「うちの子に限って…」という思い込みを脇に置き、「その言葉、どこで覚えたの?」「どういう意味だと思う?」と、冷静に、そして興味を持って尋ねてみましょう。子どもがどこで、誰から、どんな文脈でその言葉に触れたのかを知ることが、対話の出発点になります。
ステップ2:身近な例え話で「相手の気持ち」を想像させる
「差別はダメ」と正論を言っても、子どもには響きにくいことがあります。それよりも、子どもの日常にある身近な出来事に置き換えて、想像力を働かせる手助けをしましょう。
<会話例>
親:「もしね、クラスで『サッカー部ファースト!』っていうのが流行ったとするじゃない?」
子:「うん」
親:「そうしたら、サッカー部の子たちがいつも一番で、給食のおかわりも、遊び場の場所も全部先に取っちゃう。野球部やバスケ部の子たちは、いつも後回し。〇〇ちゃんが野球部だったら、どんな気持ちになるかな?」
子:「えー、ずるい! 悲しいよ」
親:「そうだよね。『日本人ファースト』も、もしかしたらそれと似ていて、日本以外の国につながりがあるお友達を、悲しい気持ちにさせちゃうかもしれないんだ。〇〇ちゃんが悲しい気持ちになることは、お友達にもしてほしくないな、ってお母さん(お父さん)は思うんだ」
このように、具体的なシチュエーションを設定することで、子どもは抽象的な「差別」という概念を、「相手の悲しい気持ち」という具体的な感情として理解しやすくなります。
ステップ3:多様性の「すばらしさ」をポジティブに伝える
「〇〇はダメ」というネガティブなメッセージだけでなく、「〇〇は素敵だ」というポジティブな価値観を伝えることも非常に重要です。
- 色々な国の文化に触れる:一緒に世界地図を見たり、様々な国の料理を作って食べたり、外国の映画を観たりする。「世界にはこんなに面白い文化があるんだね!」と親子で楽しむ経験が、自然と多様性へのリスペクトを育みます。
- 違いを面白がる:「〇〇ちゃんは足が速いね! △△くんは絵が上手だね。みんな違うから面白いし、助け合えるんだよね」というように、日常的に「違い=豊かさ」であることを伝えます。
- 一緒に本を読む:多様性や共感をテーマにした絵本や物語は、子どもの心を育む素晴らしい教材です。『せかいのひとびと』や『すてきな三にんぐみ』など、様々な文化や価値観に触れられる本を一緒に読んで、感想を話し合ってみましょう。
家庭でのこうした地道な対話の積み重ねが、子どもが安易な言葉に流されず、自分の頭で考え、他者の痛みに共感できる心を育むための、何よりのワクチンになるのです。
学校と社会の責任:教員だけの問題ではない
家庭での対話が重要である一方、この問題を学校や教員だけの責任に押し付けることはできません。元記事で紹介されているように、外国人の児童生徒数はこの10年で倍増しており、教育現場は日々、多様化する子どもたちと向き合っています。教員らは、オンライン署名活動などを通じて「子どもたちを守りたい」と必死に声を上げています。
しかし、学校だけでできることには限界があります。なぜなら、子どもたちが耳にする言葉は、学校の中だけで完結しているわけではないからです。テレビのニュース、YouTube、そして親や地域の大人たちの日常会話。社会全体が発信するメッセージを、子どもたちはスポンジのように吸収しています。
「日本人ファースト」という言葉がこれだけ広まった背景には、社会全体の不満や不安があります。その根本的な問題から目をそらし、教育現場にだけ「人権教育を徹底しろ」というのは酷な話です。私たち保護者も、PTAや地域活動などを通じて学校と連携し、「子どもたちを分断から守る」という共通の目標のために何ができるかを考える必要があります。
そして何より、政治家やメディアといった公の立場で発言する大人たちは、自らの言葉が子どもたちの教室でどのような影響を及ぼすかについて、より一層の自覚と責任を持つべきです。分断を煽るのではなく、対話を促す言葉を。排斥を容認するのではなく、包摂を促す社会の空気を。それを創り出すのは、私たち大人一人ひとりの責任に他なりません。
まとめ:私たちが子どもたちに残したい社会とは
「日本人ファースト」という一つの言葉を巡る問題は、単なる言葉狩りの話ではありません。これは、私たちが未来を生きる子どもたちに、どのような社会を手渡したいのかという、根源的な価値観を問うものです。
私たちは、出身や国籍によって人が順位付けされる社会を望むのでしょうか。自分と違うというだけで、誰かが肩身の狭い思いをする社会を、子どもたちに残したいのでしょうか。
きっと、答えは「ノー」のはずです。私たちが望むのは、誰もが自分のルーツに誇りを持ち、互いの違いを尊重し、共に支え合って生きていける社会でしょう。そのためには、まず私たち大人が、安易な言葉がもたらす分断の危険性を理解し、家庭で、地域で、そして社会で、粘り強く対話の輪を広げていく必要があります。
夏休み明けの教室が、すべての子どもたちにとって、安心できる居場所であり続けるように。そのために何ができるのか、この記事が、あなた自身の答えを見つけるための一助となれば幸いです。

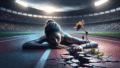
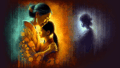
コメント